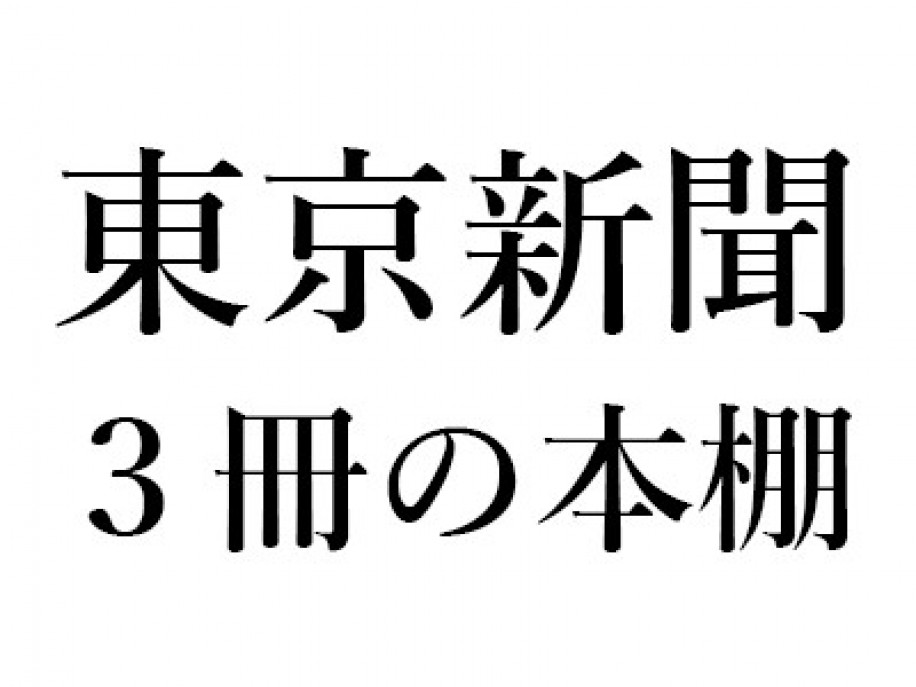前書き
『新潮文庫20世紀の100冊』(新潮社)
「20世紀の100冊」について
20世紀最後の年であった2000年、私は新潮文庫編集部の求めに応じて、「20世紀の100冊」の「解説」を書いた。100冊は編集部内で討議して選んだのだが、そのすべてについて、短いとはいえ「解説」するのである。私は100冊を読み、または読み直した。そのうえで編集部があつめてくれた関連情報を精読して準備した。結構な力仕事であったという記憶は、まだ色褪(いろあ)せない。
そうして書かれた「解説」は、文庫本の既存カバーの上にもう一枚着せられた「20世紀の100冊」特別カバーに印刷された。
このたび読み返してみたが、読書案内としてそんなに悪くないように思えたので、新潮新書の一冊にとの申し出に喜んで応じることにした。その際、作品の「内容解説」と当該年のできごとなどを付し、20世紀のイメージをより具体的にするべくつとめた。
100冊の選択におおむね異論はなかった。しかし素直にはうなずきにくいものもないではなかったし、読むにあたって苦労した作品もあった。そのあたりの事情は、「水先案内人」の意図するところではないにしろ、原稿上にあらわれているだろう。
100年を旅していくばくかの感慨を抱いた。
まず、作家と出版人の努力に対する敬意である。
日本では18世紀末からすでに商業的出版と専業作家が成立し、さらにそれ以前から王侯や貴族のスポンサーシップなしに定期的演劇興行が行われるなど、その先進性は世界に類を見なかった。まことに豊饒(ほうじょう)な「日本型近代」であった。
しかし明治革命前後、文芸も出版も一時衰退した。「西欧型近代」に転換するのに多忙で、それどころではなかったというのが実情だろう。
しかし1890年代に至ると、再び青年が文学を志すようになる。それはたしかに一種の「ベンチャー・ビジネス」であった。だが、出版産業はまだ確立していないから「利益率」はきわめて低く、本人と家族を養うに足りなかった。樋口一葉は、いち早く「ベンチャー」を試みた果敢な女性であったが、経済的には報われなかった。
尾崎紅葉も19世紀末に職業作家として立とうとした。その代表作『金色夜叉』には官途の出世をあきらめて高利貸しになる主人公のほか、主人公を「カネの夜叉」にかえるきっかけを与えた女性や、彼女がなびいた富豪青年の敵(かたき)役が登場する。
しかし紅葉の文体はあたらしくはない。1888(明治21)年、二葉亭四迷がツルゲーネフ「めぐりあひ」を翻訳しながら苦労してつくりだしたあたらしい日本文の影響を受けていない。「経済」と「人情」の相克を小説の動力とした点でも、近松、西鶴にはるかに先立たれている。
どこがあたらしいかといえば、アメリカ人作家バーサ・クレイの通俗小説を下敷きにした「ハイブリッド」であるところだ。元がアメリカ小説でも妥当に翻案すれば、毎朝、お店の小僧さんが『金色夜叉』の載った読売新聞を門口で待ち、熊本五高の先生だった夏目漱石が切り抜きを送ってくれと奥さんの実家に頼むほどに浸透するのだという発見は、紅葉の仕事によってもたらされた。
この小説では、結婚相手の選択権は実は女性にあり、敵役は紅葉が嫌った、当時最大の版元博文館の若社長、大橋新太郎に姿かたち言動を似せてある。その当時の「現在」を反映している点も、あたらしい。
独自のリアリズムから叙景と批評がともに可能な文体「写生文」を確立、本人が思っていたより大きな影響を後世に残した正岡子規は、20世紀に入って1年半後に死ぬ。その訃報(ふほう)を帰国直前のロンドンで受けた漱石は、まだ小説を書きはじめてはいない。しかし日本文学は20世紀初頭、大きな転回点を迎えようとしている。
ふたつの世界戦争といくつかの大革命、およびそれら革命の破産が明らかになった20世紀を文学の流れからふり返れば、日本文学にとっては、西洋文学と西洋思想を咀嚼(そしゃく)・吸収し、さらには変容させて、江戸近世文学以来の日本独自の近代文学を完成させるまでに要した100年間だといえるだろう。青年たちは誠実に貧欲であった。先人の営為は偉大であった。
私は、ここにあげた100冊を「鑑賞」しなかった。むしろ「歴史」を読みとろうとした。私の考えでは「読書」とはそういうものだからだ。やや口数多い水先案内人ではあるが、このガイドを一助に、日本文学とそれに影響を与えた世界文学の厚みを感じていただけるなら、著者としては満足である。
2009年3月
関川夏央
ALL REVIEWSをフォローする