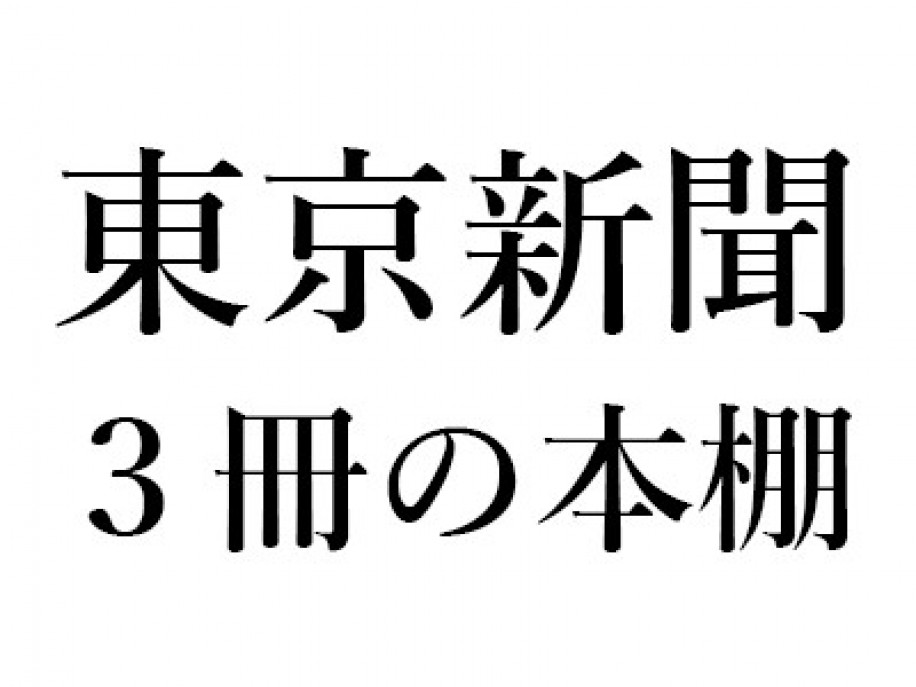書評
『二葉亭四迷の明治四十一年』(文藝春秋)
関川夏央と我らが「隣人」四迷
九三年から九五年にかけて、わたしは雑誌「文學界」の頁を開くのを楽しみにしていた。関川夏央の「窓外雨蕭々」が連載されていたからである。以前も以降も、わたしは文芸誌の連載を楽しんで読んだ覚えはない。その「窓外雨蕭々」に手を入れて成ったのが『二葉亭四迷の明治四十一年』(文藝春秋)である。
すでに関川夏央には、ようやく完結した大作にして途方もない傑作『「坊っちゃん」の時代』がある。そこで、関川は明治とその時代に生きた文学者の姿に目を凝らした。関川のとった方法は、歴史上の名前を生きる人格として蘇らせることであった。作品は作家によって書かれる。時代は個人によって生きられる。関川は、その簡明な真理を自らの作品の中で証明してみせた。伊藤整が『日本文壇史』(講談社文芸文庫)でとった方法もそれであったし、およそ優れた歴史書や批評は、そのように書かれていたはずである。
『二葉亭四迷の明治四十一年』は歴史書であり、また物語でもある。歴史書でありかつ物語であることは決して不可能ではない。鷗外森林太郎はすでに百年前にそのことを証明している。
関川夏央は明治への偏愛を折に触れて告白している。その理由は何であろうか。それが、アナクロニズムに発するものでないことは明白である。
また、わたしも明治への、あるいは明治期に生きた作家たちへの共感と関心が薄れたことは一度もない。それは、彼らが活き活きしていると感じられるからである。九十年以上も以前に生きた人間たちが「生きている」と感じられるのはなぜであろう。考えてみれば、それは奇妙なことではないか。三十年で一世代、数年前の流行がたちまち廃れ、夏のファッションが秋には忘れられることをわたしたちは知っている。ならば、自分の記憶として覚えている人間などとうに死滅してしまった遠い時代のことなど、わたしたちになんの関係があるというのか。
たとえば、漱石夏目金之助の『明暗』を読む時、驚愕するのは、その会話が古びていないことである。いや、現代に書かれる小説のどれほどに、『明暗』ほど読者を刺激してやまない会話が書かれているか。
人は、漱石が古びぬのはそこに「不易の真理」を描いたからという。紫式部や芭蕉は「不易の真理」を描いたから、いまでも読むことができる。しかし、『明暗』が面白いのは、「不易」だからではない。漱石が、わたしたちの「隣人」だからではないか。紫式部や芭蕉は「偉人」ではあっても「隣人」たりえぬのである。
では「隣人」とはなにか。それが関川のこの書物の中に書かれていることである。
「隣人」は、わたしたちと少しも変わらない。そのことにわたしたちはまず驚く。この九十年間、わたしたちは少しも進歩しなかったのだ。それはいい。その次に驚くのは、実のところ「隣人」とわたしたちは少し違うことである。彼らは、わたしたちより、鮮明な意志と意見を持ち、それ故、わたしたちより鮮やかな輪郭を持っている。それに対して、わたしたちの輪郭はボヤけている。それがなぜなのか、いま詳細に語ることは、わたしにできない。
もし、遠い時代の彼らがわたしたちを眺めたら、やはり違いはほとんどなく、ただ輪郭がボヤけているだけだと思うであろう。そして、その理由を、距離の遠さに求めるだろう。だが、それは間違いなのだ。こちらから見える彼ら「隣人」は遠くにあって、なお鮮明な姿を保っているからである。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする