書評
『ガートルードとクローディアス』(白水社)
芝居好きなもので、これまで色んなパターンのハムレット劇を観てきたけれど、な~んか共感できなくて、肝心の主人公に。この若造の軽挙妄動のせいで、どれだけたくさんの命が無駄に犠牲になっていくことか。「生きるべきか、死ぬべきか」なんてカッコつけて悩んでる間に、神経衰弱になりかけてる己の恋人の世話でもしたらんかいっ! 思わず一喝したくなるナルシスト坊やなんである。
で、そんな困った君の母親ガートルードがまた、存在感が希薄というか、意志薄弱というか、同性としてイラつく存在で。再婚相手の義弟と息子の間にはさまれて右往左往するばかり。「あたし、何にも自分で決めらんな~い」てな手合いで、シェイクスピアにしちゃあ手抜きの人物造型すぎだろー、と思わざるをえない女性像になっているのだ。そんなこんなの欠点の目立つ作品なのよ、『ハムレット』は。
ところがここに一冊の小説が現れて、この作品にまつわる不満や疑問を一気に解決してくれた。『走れウサギ』(白水uブックス)といった数々の名作で知られるアメリカの巨匠、ジョン・アップダイクの『ガートルードとクローディアス』。これは、目からウロコの傑作なのである。
自由闊達な少女時代を満喫していたのに、一六歳で粗野な大男とピンとこない結婚をさぜられて、イマイチ愛せないまま悶々とした結婚生活を送っていたガートルード。そんな時、夫の弟クローディアスが現れる。諸国を遍歴していたから話題は豊富だし、武骨な夫と比べると繊細。とっても大事に扱ってくれて、おまけにちょっといい男。でもって、どうやら自分を愛してくれてるらしい。――そりゃ、心魅かれるよねえ。マッチョな夫が死んでくれた暁にゃあ、クローディアスと再婚したくもなるのも「わかる、わかる」ってなもんでしょ?
とまあ、そんな具合にアップダイクは原作には描かれていない、亡き夫とガートルードの味気ない結婚生活や、ガートルードとクローディアスが愛しあうに至った経緯、クローディアスがなぜ兄殺しという大罪を犯さざるを得なかったのかという理由を丹念に語りおこしてみせる。とりわけ、シェイクスピア劇では意志のないお人形さんのように描かれているガートルードを、血肉をまとう生きた女として再生させている点が見事。『メイプル夫妻の物語』や『結婚しよう』(ともに新潮文庫)などでも見られる、アップダイクの女性理解の深さ、温かさが、ここでもちゃんと活かされているのだ。
この小説に描かれているのは、ハムレットの物語が始まる直前までの出来事。だから、本来の主人公は後景のひとつとして登場している。ワガママな幼児として、早くから母親をはじめとする女性全般への侮蔑的視線を獲得した生意気な青年として、政治なんて無粋なものにかかわりたくないから、三〇歳すぎても外国の洗練された都市でふらふらしているプータローとして。まだ危険人物とは言い難い放蕩息子だけれど、不穏な雰囲気はすでに漂わせていて、それがまた今後の不幸を予感させてヤな感じなのである。だって、この物語につきあってきた読者にとって、今や感情移入の対象はガートルードとクローディアスなんであって、ハムレットじゃないんだから。
そして、その感情移入の転移ゆえに、読者はクローディアスが物語の最後にもらす「すべてよし」という言葉に戦慄を覚えないではいられないのだ。だって、わたしたちはハムレットの復讐がまさにこれから始まることを、この青二才がどうやって周囲の全ての人間を悲劇の渦に引きずりこむのかを知っているんだから。ハムレットの物語のプロローグとして、これほど皮肉な締め括りもあるまい。巧い、本当に巧い小説だ。
【この書評が収録されている書籍】
で、そんな困った君の母親ガートルードがまた、存在感が希薄というか、意志薄弱というか、同性としてイラつく存在で。再婚相手の義弟と息子の間にはさまれて右往左往するばかり。「あたし、何にも自分で決めらんな~い」てな手合いで、シェイクスピアにしちゃあ手抜きの人物造型すぎだろー、と思わざるをえない女性像になっているのだ。そんなこんなの欠点の目立つ作品なのよ、『ハムレット』は。
ところがここに一冊の小説が現れて、この作品にまつわる不満や疑問を一気に解決してくれた。『走れウサギ』(白水uブックス)といった数々の名作で知られるアメリカの巨匠、ジョン・アップダイクの『ガートルードとクローディアス』。これは、目からウロコの傑作なのである。
自由闊達な少女時代を満喫していたのに、一六歳で粗野な大男とピンとこない結婚をさぜられて、イマイチ愛せないまま悶々とした結婚生活を送っていたガートルード。そんな時、夫の弟クローディアスが現れる。諸国を遍歴していたから話題は豊富だし、武骨な夫と比べると繊細。とっても大事に扱ってくれて、おまけにちょっといい男。でもって、どうやら自分を愛してくれてるらしい。――そりゃ、心魅かれるよねえ。マッチョな夫が死んでくれた暁にゃあ、クローディアスと再婚したくもなるのも「わかる、わかる」ってなもんでしょ?
とまあ、そんな具合にアップダイクは原作には描かれていない、亡き夫とガートルードの味気ない結婚生活や、ガートルードとクローディアスが愛しあうに至った経緯、クローディアスがなぜ兄殺しという大罪を犯さざるを得なかったのかという理由を丹念に語りおこしてみせる。とりわけ、シェイクスピア劇では意志のないお人形さんのように描かれているガートルードを、血肉をまとう生きた女として再生させている点が見事。『メイプル夫妻の物語』や『結婚しよう』(ともに新潮文庫)などでも見られる、アップダイクの女性理解の深さ、温かさが、ここでもちゃんと活かされているのだ。
この小説に描かれているのは、ハムレットの物語が始まる直前までの出来事。だから、本来の主人公は後景のひとつとして登場している。ワガママな幼児として、早くから母親をはじめとする女性全般への侮蔑的視線を獲得した生意気な青年として、政治なんて無粋なものにかかわりたくないから、三〇歳すぎても外国の洗練された都市でふらふらしているプータローとして。まだ危険人物とは言い難い放蕩息子だけれど、不穏な雰囲気はすでに漂わせていて、それがまた今後の不幸を予感させてヤな感じなのである。だって、この物語につきあってきた読者にとって、今や感情移入の対象はガートルードとクローディアスなんであって、ハムレットじゃないんだから。
そして、その感情移入の転移ゆえに、読者はクローディアスが物語の最後にもらす「すべてよし」という言葉に戦慄を覚えないではいられないのだ。だって、わたしたちはハムレットの復讐がまさにこれから始まることを、この青二才がどうやって周囲の全ての人間を悲劇の渦に引きずりこむのかを知っているんだから。ハムレットの物語のプロローグとして、これほど皮肉な締め括りもあるまい。巧い、本当に巧い小説だ。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
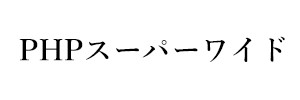
PHPスーパーワイド(終刊) 2002年9月
ALL REVIEWSをフォローする








































