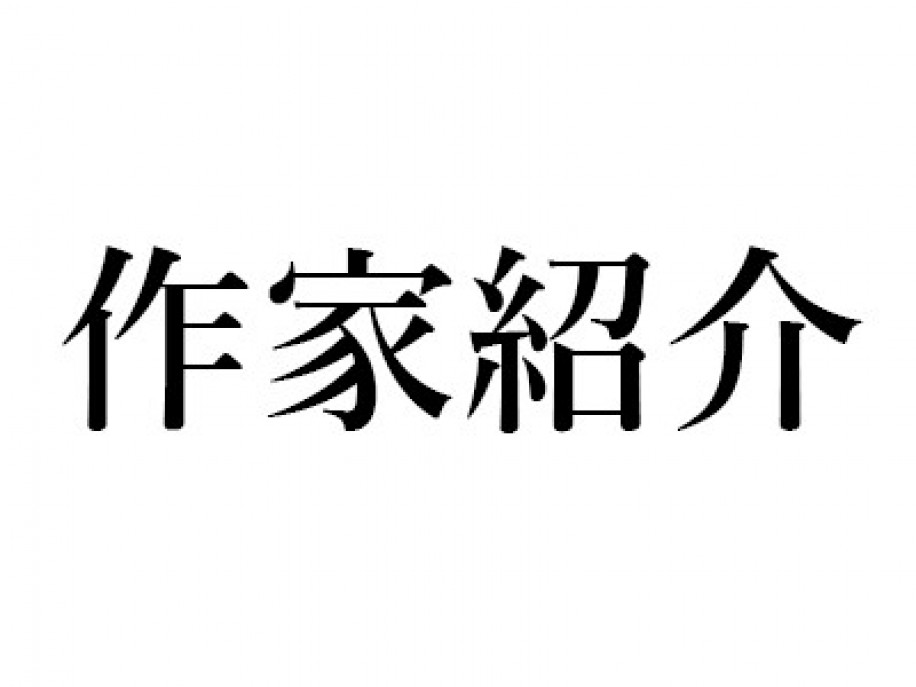書評
『台所のおと』(講談社)
耳を済ませて読む
女房には読んでもらいたくないな。小説を読んでいて、そう思ったのははじめてのことだ。いかがわしいポルノのたぐいではない。神品中の神品、幸田文の『台所のおと』。ずいぶん前に一度、初出の雑誌のバックナンバーで読んだせいか、妻の立てる音に耳を澄ます男の話だったな、という程度にしか覚えていなかった。
ローベルト・ムシールというドイツの作家の遺稿集に、隣室の妻の一挙一動をベッドにいる夫が耳で追う掌篇がある。その掌篇に引きずられて、印象がぼやけてしまったのかもしれない。それにこちとら、初読のときはまだ結婚してなかった。
家の中にいる妻の動静を耳で追う、エアポケットに入ったような時間が結婚生活にはある。そこをいじってみたら何か出てきはしないか、と先日、思い立ったら、女房の書棚の『台所のおと』文庫本がふと目に入った。そうだ、先覚者はどんなふうにひねくっていたっけ? 再読の動機は、不届きなくらい単純且つ不純である。
ひねくっていたっけ、なんてとんでもなかった、読み進むうちに思わず居ずまいを正した。
妻の立てる音に耳を澄ます男の話にはちがいない。中小の繊維問屋の多い街で小料理屋をやっている佐吉は、ぶらぶら病いをやんでいたが、一ヵ月前から寝こんでしまい、二十歳年下の妻、あきが台所で立てるもの静かな音に耳を傾けることで病気の憂さをはらしている。佐吉の耳は微細な音を聞きわける。
……佐吉はその水音で、それがみつばでなく京菜でなく、ほうれんそうであり、分量は小束が一把でなく、二把だとはかって、ほっとする安らぎと疲れを感じる。
台所と佐吉の寝ている四畳半とは障子一枚の隔てしかない。寝こむまで佐吉が仕切っていた台所にいまはあきが入っている。台所をはさんで客室二つと居室二つが並ぶだけの、戦後すぐに建ったバラック建て。終戦の荒涼のなかで二人が結ばれてから十五年がたっている。
医者からは胃だと診断されていたのだが、日ならずして、あきは病状が絶望的だと告げられる。
悟られまいと取り繕う苦しみと、自分ひとりだけが知っているための孤独。それは佐吉へのいっそうこまやかな気配りになるのだが、奇妙なことに、弾んだ張りきりにもなり、いっきにしゃべってしまおうかという気持さえ生まれる。だからなおさら立居にも音をはばかり、台所のなかでは、静かに静かに、と音をぬすむようにふるまおうとする。
あきのそうした心根が、心魂を耳にしているような佐吉に聞きわけられないはずがない。
「……おまえはもとから音をたてないたちだったけど、ここへ来てまたぐっと小音になった。〈……〉水でも包丁でも、なにかこう気病みでもしているような、遠慮っぽい音をさせてるんだ。あれじゃ、味も立っちゃいまい、と思ってた」
佐吉はやがて寝言のように、
「あと何日ある?」と言ってあきをぎょっとさせる。
はじめからおわりまで、音だけをたよりに語られるといってもいい。台所の音、二人のかわす会話、二人の内心の声……。音にみちているのに、物語はしいんと静まっている。あきという波紋が立ってひろがり、佐吉という波紋とひめやかにぶつかって干渉波のあえかな縞が生まれる。こんなこまやかな夫婦物語なんて、めったにあるものではない。こまやかすぎてこわいくらいだ。これをとっくに女房のやつも読んでいたことにおそまきながら気がついて、もっとこわくなった。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする