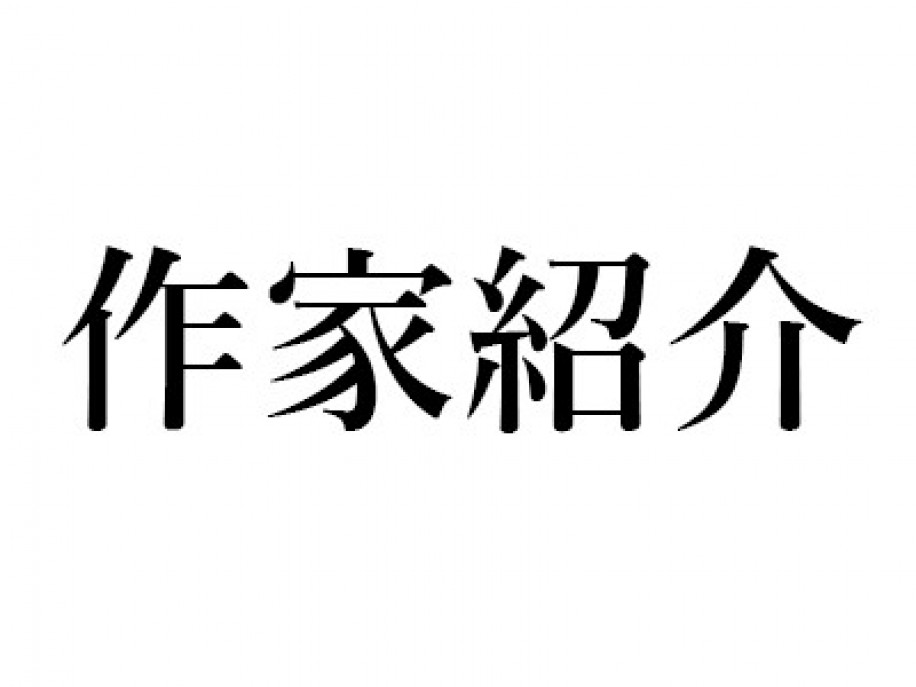書評
『台所のおと』(講談社)
表題作。静かな、しずかな小説である。
佐吉とあきはたがいに何度目かの妻であり、夫である。二十も年の離れた二人は小さな料理屋をいとなんでいた。
熟練した料理人の耳には、水音で、洗っているのがみつばでなく、京菜でなく、ほうれんそう、しかも二把だとわかる。手つきも見える。夫の病がなおりがたい、と知り、覚悟が強いられたあと、あきの台所の音が変わる。佐吉は気づく。「小音(こね)でもいいんだけど、それが冴えない。いやな音なんだ」
さしたる大仰な展開があるわけではない。エッセイの延長のように淡々と描いていく。それにしてもなんという〈音〉のゆたかさ。むしろ音が主役だ。砥(といし)と刃を擦る音は「互いに減らしあい、どちらも負けない、意地の強い音」である。「真夜中だな、と思いつつ、茶筒の蓋を抜く。蓋はいい手応えで抜けてくる」。すり鉢ときたら「とろろをすればくぐもった音をだすし、味噌はしめった音、芝海老は粘った音、胡桃は油の軽くなさを音に出す」。
あたかも精霊のごとく、道具たちは自己主張をする。それぞれの空間にしんとおさまりながら、それでも何か事あれば、歌いだし踊りだそうと待ちかまえ、それが台所を充実させている。懐かしい風景だ。
あらためて、この作家がいかに生活にずっぶりと腰を沈めているか、を思う。絵空事につきあわされるという感じがない。伴走してより多くを教えてもらおうと読みすすむ。「だれでもうでの上の人の代理をつとめるときには、不断より冴えるんだ。見劣りしたくないと思うからね」
佐吉にとって、越しかたの三人の女は、台所の音で思い分けられるのだ。「女はそれぞれ音をもってるけど、いいか、角だつな。さわやかでおとなしいのがおまえの音だ」
これはいっしんにいとしみあい、いたわりあった男女の物語で、集中の白眉にはちがいない。露伴晩年の父娘の姿も投影されているのかもしれないと思う。が他の作には、婚家の没落や生活能力のない夫が描かれ、こちらも作家の生活から取り出されたものか、とよぶんなことを考える。「つまらない男だと突っ放しているくせに、そのひとの金には連添ってきた親しさが残っていて」「いのちの瀬へ来ていてなんというぐずな」「みじめなものを見て気に入り、情けないものを見て優しくなるのだな」「ひとの取込事をきくとハッスルしちゃうのは家庭的な女のいやらしい癖」……これはこわい。だが、こわさと情味と両面あって幸田文である。
ひきしまった文体と表現の的確さは定評があるが、聞き抜く、心組む、見惚れる、といった複合動詞がすさまじい効果をあげている、と思った。
その人がいなくなって日ごとに欠落感が増す。幸田文はそんな人だ。誰が逆立ちしたってこうは書けない。エッセイ『木』や『崩れ』が好評のうちに版を重ねているのもその証(あかし)だろう。全集はすでに絶版である。大判で活字も大きいこの本を、私はありがたく受けとり、もったいないように頁をめくった。
【この書評が収録されている書籍】
佐吉とあきはたがいに何度目かの妻であり、夫である。二十も年の離れた二人は小さな料理屋をいとなんでいた。
佐吉は寝勝手をかえて、仰向きを横むきにしたが、首だけを少しよじって、下側になる方の耳を枕からよけるようにした。台所のもの音をきいていたいのだった
熟練した料理人の耳には、水音で、洗っているのがみつばでなく、京菜でなく、ほうれんそう、しかも二把だとわかる。手つきも見える。夫の病がなおりがたい、と知り、覚悟が強いられたあと、あきの台所の音が変わる。佐吉は気づく。「小音(こね)でもいいんだけど、それが冴えない。いやな音なんだ」
さしたる大仰な展開があるわけではない。エッセイの延長のように淡々と描いていく。それにしてもなんという〈音〉のゆたかさ。むしろ音が主役だ。砥(といし)と刃を擦る音は「互いに減らしあい、どちらも負けない、意地の強い音」である。「真夜中だな、と思いつつ、茶筒の蓋を抜く。蓋はいい手応えで抜けてくる」。すり鉢ときたら「とろろをすればくぐもった音をだすし、味噌はしめった音、芝海老は粘った音、胡桃は油の軽くなさを音に出す」。
あたかも精霊のごとく、道具たちは自己主張をする。それぞれの空間にしんとおさまりながら、それでも何か事あれば、歌いだし踊りだそうと待ちかまえ、それが台所を充実させている。懐かしい風景だ。
あらためて、この作家がいかに生活にずっぶりと腰を沈めているか、を思う。絵空事につきあわされるという感じがない。伴走してより多くを教えてもらおうと読みすすむ。「だれでもうでの上の人の代理をつとめるときには、不断より冴えるんだ。見劣りしたくないと思うからね」
休んでみな。一日分は言訳があるが二日目はないぜ。神経がだんだんしなびてきた時には休んじゃいけないんだ
佐吉にとって、越しかたの三人の女は、台所の音で思い分けられるのだ。「女はそれぞれ音をもってるけど、いいか、角だつな。さわやかでおとなしいのがおまえの音だ」
これはいっしんにいとしみあい、いたわりあった男女の物語で、集中の白眉にはちがいない。露伴晩年の父娘の姿も投影されているのかもしれないと思う。が他の作には、婚家の没落や生活能力のない夫が描かれ、こちらも作家の生活から取り出されたものか、とよぶんなことを考える。「つまらない男だと突っ放しているくせに、そのひとの金には連添ってきた親しさが残っていて」「いのちの瀬へ来ていてなんというぐずな」「みじめなものを見て気に入り、情けないものを見て優しくなるのだな」「ひとの取込事をきくとハッスルしちゃうのは家庭的な女のいやらしい癖」……これはこわい。だが、こわさと情味と両面あって幸田文である。
ひきしまった文体と表現の的確さは定評があるが、聞き抜く、心組む、見惚れる、といった複合動詞がすさまじい効果をあげている、と思った。
その人がいなくなって日ごとに欠落感が増す。幸田文はそんな人だ。誰が逆立ちしたってこうは書けない。エッセイ『木』や『崩れ』が好評のうちに版を重ねているのもその証(あかし)だろう。全集はすでに絶版である。大判で活字も大きいこの本を、私はありがたく受けとり、もったいないように頁をめくった。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア

DIY(終刊)
ALL REVIEWSをフォローする