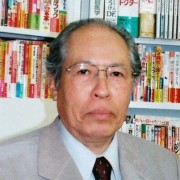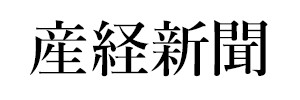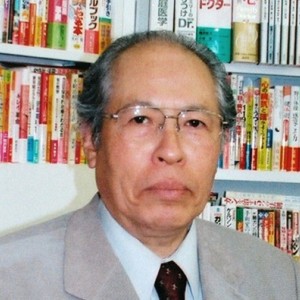書評
『百代の過客 日記にみる日本人』(講談社)
日記から見た日本人論
日本人ほど日記を好む民族はない。日本文化研究者としてのドナルド・キーンはこの点に着目し、日記による日本人論を構築した。著者は早くから平安時代の日記文学に着目していたようだが、日本人を理解するカギとして意識しはじめたのは第二次大戦中、戦場に遺棄されていた日本兵士の手帳を翻訳する仕事をしたことからだったようだ。そのなかには、隣接の軍艦が魚雷に撃沈されたときの恐怖や、七人の生き残りの兵士が新年を祝うのに、わずか十三粒の豆を分け合ったことなどが記されていたという。
アメリカの兵士は、機密保持のため日記は禁じられていたが、日本では日記をつけるという行為が伝統の中にあまりにも確固たる地位を占めているため、禁じるのは逆効果であることを知っていたのかもしれない、というのが著者の推測である。このような指摘は、国文学の専門家からは出てこないものだ。
本書は平安時代初期の僧侶から、幕末の武士にいたるまでの日記や紀行七十七篇をとりあげながら、関連分野として平安時代の歌集と歌物語にも言及している。これまで一般にはあまり知られなかった日記まで、ていねいに紹介し、文学史の欠落をうめていることは評価すべきであろう。
しかし、本書にあげられている日記を、いざ手にとってみようとすると、一般読者が読めるような形にはなっていないものも多い。たとえば藤原定家の「明月記」などは、原文が漢文のうえ長大なので、さすがのキーン氏も解読に苦しんだらしい。「定家がこれを日本語で書かなかったのはいかにも残念である」という評言もある。ここで気がつくのは、漢文は日本人にとっては、何となく国語の一種という感覚があるが、外国人にとってはそうではないということである。
「誰かすぐれた学者が出て、この日記文学の記念碑的作品を現代語(あるいは英語)に訳して、私や私のような読者を、助けてはくださらぬものだろうか」という願いは、いつになったら満たされるのだろうか。
日記というものに対し、著者は資料性のみを求めているのではない。たとえば「奥の細道」には「一家(ひとつや)に遊女もねたり萩と月」という有名な句があるが、同行の曾良の日記にはこの記述が見当たらないので、虚構ではないかという意見がある。しかしキーン氏によれば、「事実からの乖離は、作品の永続的な全体的真実感を、かえって高めている」という。この観点から文学一般の存在理由を記した結論部分は、非常に説得力に富んでいる。
生活環境の変化により、日記に無関心な世代が増えつつある。ワープロ日記なども、一般化しているとはいえない。このような背景の中で、日本文化における日記の魅力と重要性を説いた本書の意義は、きわめて大きなものがあるといえよう。
ALL REVIEWSをフォローする