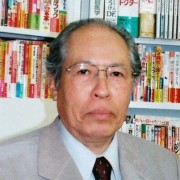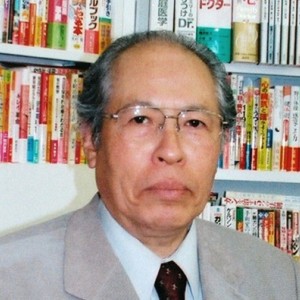書評
『世界大博物図鑑 2 (魚類)』(平凡社)
荒俣博物学の原点
いつも思うのだが、退屈したときには水族館に行くがよい。五百羅漢のどれかに死者の面影が彷彿されるように、水槽の魚には生きた人間に無気味なほどそっくりな顔が発見できる。いまだったら宇野総理、中曽根、江副……(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は1989年)。けれども、なぜ水槽の魚でなければならないのか。本書の「水界という異界に棲む魚類は、いわば半分隠された生物なのだ」という解説を読んで氷解した。釣りあげた魚は、本来の姿を異界に残してきた抜け殻にすぎない。この点がほかの陸上生物とは根本的にちがうところであり、水中博物学が特殊な展開を示すことになった根因であるという。
本書は全五巻におよぶ『世界大博物図鑑』の第三冊目であるが、幻想文学である以前に魚博士であった著者にとっても、最大の力点が置かれて当然な、いわば荒俣博物学の原点ともいうべき位置にある。とくに一七〇〇年代における最初の魚類博物誌(ルナール著)出現当時への興奮を追体験することから、博物学の原理的な意味を再構築していくところはじつに見事であり、余人には到底不可能な発想といってよい。
一口に博物学といっても、専門分化の甚だしい現代生物学からすれば、ほとんどアクセスが不可能となってしまった総合的ジャンルであるが、著者はその大胆な構想と超人的な集中力にあわせて、博捜力と細心な学究的方法により、見事に”現代の博物学”を創造しつつある。荒俣宏にとっての魚類は南方熊楠における粘菌類のようなものだが、その時代的意義においてすでに南方を超えたことが、どのページにも明らかだ。全巻完結の一日も早いことを祈りたい。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
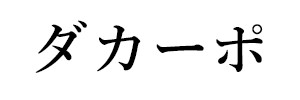
ダカーポ(終刊) 1989年8月2日
ALL REVIEWSをフォローする