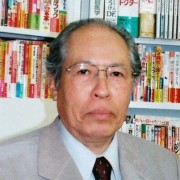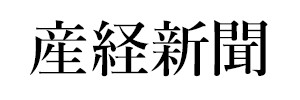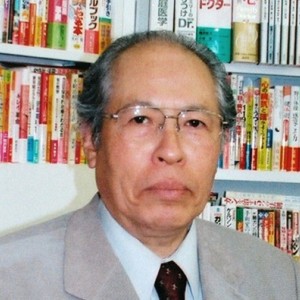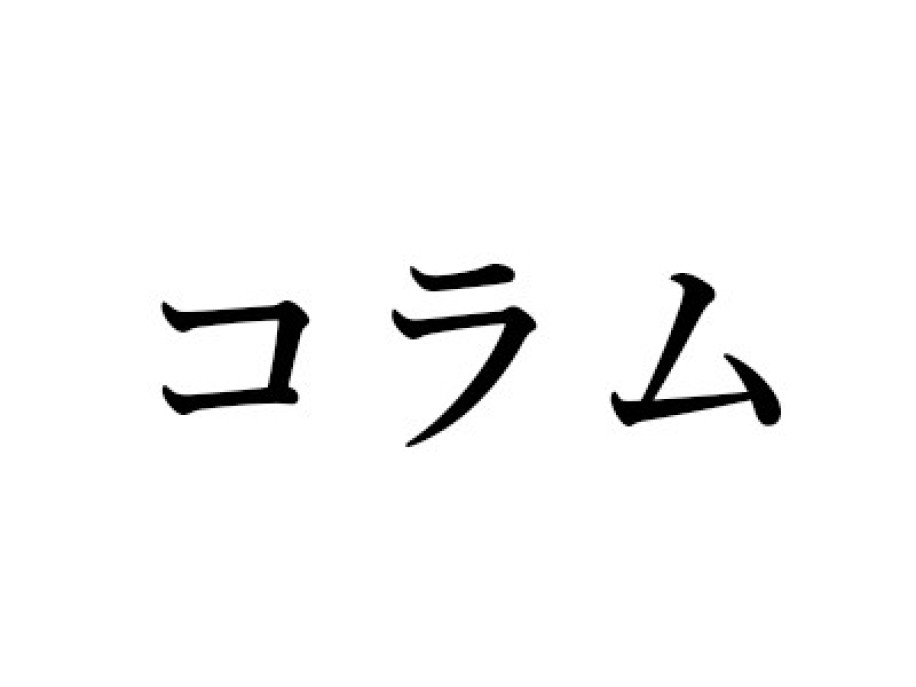書評
『関西古本探検―知られざる著者・出版社との出会い』(右文書院)
一過性でない書物文化語る
古書店めぐりをテーマとしたエッセーが流行しているが、その中でも本書は題名通り関西が舞台であることに加え、詩や、小説などの文芸書を主体としている点、昨今にはみられない特色といえる。たとえば梅田の古書店で「六甲」という古雑誌を見つけた著者は、300円という値札に「足立巻一他」とあるので、何かの文芸同人誌にちがいないと直感し、喜んでレジにさし出す。足立は神戸在住の作家・詩人で、『やちまた』で芸術選奨文部大臣賞を受けている。帰って読んでみると、はたして日ごろ関心の深い神戸の短歌同人誌であった。
雑誌の内容は別として、その歴史がわからない。ふと、数年前に古本で買った足立巻一の『親友記』(1984年、新潮社)を思いだし、この機会に読んでみた。結果は「六甲」の由来ばかりか、戦前の神戸の同人活動、その濃密な人間関係など、通常の文学史や出版史にはふれられない事実が浮かび上がってくる。
著者はフリーの編集者だが、4年ほど前に出した『古本が古本を呼ぶ』(青弓社)という本のように、ー冊の本や雑誌から連鎖的に発見があり、読み手の関心に即して本が見つかっていく様子は、古本あさりの醍醐味である。これらの本から、懐かしい古本屋のたたずまいや、その空間にただよう独特の香りを貪(どん)らんに感じ取ろうとする著者の姿には共感を呼ぶものがある。店主が力バーをかける仕草ひとつ見逃さない。戦前の多くの文芸書が古本屋から出版されていたという発見もある。
それどころか、むかしの古書店は、地域文学活動の拠点であり、文芸愛好家のサロンともなっていたことが、あらためて想起されてくる。最近、一部のブーム的現象をよそに、従来の古本屋らしい古本屋が姿を消しつつあることを思うとき、文芸書や思想書を中心に、一過性でない書物文化を語ることのできる著者のような存在は、きわめて貴重なものといわなければなるまい。
ALL REVIEWSをフォローする