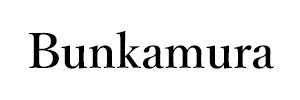選評
『古本屋散策』(論創社)
第29回(2019年)Bunkamuraドゥマゴ文学賞 選評「新しいものは常に古いもののなかにある」/ 選考委員 鹿島茂
選考委員が一人だけというのが意外に重荷になったと歴代の選考委員が例外なく述懐しておられますが、ジャンルを問わないというのもまた困惑を誘う規定でした。出版不況が叫ばれて久しいのに新刊点数は増加し続けているので、一人でフィクションとノンフィクションの全領域をカバーするのは大変なのです。しかし、そんなときにふと、新刊の洪水という現象そのものにメスを入れた本はないのだろうかという考えが閃きました。そう思ったとき、たまたま眼についたのが小田光雄さんの『古本屋散策』でした。小田さんは『出版社と書店はいかにして消えていくか』『出版状況クロニクル』Ⅰ~Ⅴなどの著作を通して、出版と流通の問題を社会構造から考えるという視点を採用している数少ない著者の一人で、出版不況が激化すればするほど出版点数が増えるという出版流通業界の謎にも取り組んでおられます。
『古本屋散策』はというと、こちらは、日々、古書店の均一本コーナーなどで購入した古本を介して、自分と本とのかかわりを個人史的に回想しながら、先に述べた謎の淵源に迫る試みと解することができます。本書のコアは、古本収集そのものにあるのではなく、入手した古本に含まれる様々な情報(著者、編集者、出版社、発行人等々)を量的に蓄積することで初めて見えてくる「日本の出版・流通文化」の「無意識」の分析です。
神田に代表される日本の古書業界は、世界に匹敵するものがないといわれているが、それは取次を中心とする特殊な流通システムが必然的に誕生させたものであり、近代出版流通システムの補完装置として始まったのではないかと考えられる。
すなわち、明治末に返品可能な委託制が導入されたことから取次が書籍流通と金融の主体を担うようになり、大量生産、大量消費という近代出版流通システムが出来上がっていったのですが、そのなかで、古書業界がこの量産システムからこぼれ落ちた本たちを救い上げるセーフティネットとして機能するようになったのです。その意味で、「日本の出版・流通文化」の「無意識」はこの古書業界からの逆照射というかたちでしか解明のしようがないのです。
通説では昭和初期の円本ブームが量産システムの嚆矢となったといわれますが、その一方では大手取次のネットワークに拠らない中小出版社の流通ルートが存在し、文学史に残る作家たちの処女作の多くはこうした中小出版社の流通ルートを通って読者のもとに届けられたはずです。小田さんが本書で企てようとしたのはこの幻の流通ルートの解明です。
その(近代出版流通システムの成長の)かたわらで、現在の言葉でいえば、リトルマガジン、少部数の文芸書、翻訳書、研究書を主とするインディーズ系出版社は、読者に向けての作品を出版し、予約直接販売、会員制方式、組合システムといった近代出版流通システムとは異なる流通と販売に立脚し、成長していく出版資本とは別の出版活動を模索していたのではないだろうか。
では、なぜ幻の出版流通システムの復元がいま必要なのでしょうか?それは、近代出版流通システムがいずれ機能不全に陥ることが明らかな以上、代替システムを模索しておく必要があるからです。新しいものは常に古いもののなかにあるというのが古本収集の与える最大の教訓ですが、この場合も例外ではありません。
しかし、手掛かりとなる資料はほとんどありません。古本を手に入れ、内容を読み込むと同時に、後書きや奥付に記された編集者、発行人、出版社といった情報を抽出して「失われたネットワーク」を復元してゆくしか方法がないのです。本書はまさにこの絶望的に困難な企てを、著者個人の読書史・集書史と絡めながら綴った傑作古書エッセイです。
一人の選者が勝手な基準で受賞作を選ぶことができるというBunkamuraドゥマゴ文学賞のユニークな基準をうまく利用できたことをまことにうれしく思います。
ALL REVIEWSをフォローする