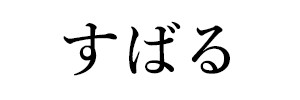書評
『イタリアのしっぽ』(集英社)
歓待の精神
人間と動物のつきあいは、かつてはかなり、実利的な性格を帯びていたのではないだろうか。人は動物を使役することで自らの労苦を軽減し、暮らしを楽にしたいと願ったはずである。現代社会ではもはや使役という要素は影をひそめ、コンパニオン・アニマルとしての役割が増す一方である。精神面での助けを求めて動物にすがっているというべきか。イタリアの人々の日常においても、そうした事態は顕著であることが本書を読むとよくわかる。動物たちは人間たちのあいだに割って入り、夫婦や親子の関係にさざ波をたてたりもする。夫ではなく猫を選ぶという人生だってありうる。猫や犬ばかりか、猿や馬との驚くべきつきあいもあるし、毛虫やバッタ、蛍とのささやかな触れあいもある。
いずれにせよ、ここに集められた物語の数々が示すのは、人の心に苦もなく入り込み、魅了し、日々の支えともなる動物たちの及ぼす力の大きさである。建設現場での仕事に、猿を伴ってやってくる青年の姿は、そのもっとも印象的な例証だ。暑い日、タンクトップを着ているのかと思ってよく見ると、彼は愛するメス猿を胸元に張り付かせていたのだ。何者かとともに生きたいという人間の根源的欲求が、動物との関係において見事なまでにあらわになる。人間はだれしも独りでは生きていけないという事実を、動物たちはよく知っているというべきか。
動物とのつきあいには、人の心のもっとも親密で傷つきやすい部分が表れ出る。だからこそ、さらりとした筆致で描かれた十五の物語のいずれもが、たまらなくこちらの胸を揺さぶるのである。
『ジーノの家』で著者の作品に初めて触れ、実に面白くて他の本も読んでみるといずれ劣らぬ充実ぶりでいよいよ驚いた。本書もまた、エッセーにして小説であり、かつほとんど映画的でもあるような魅力を湛えた一冊だ。同時に、著者その人への興味もかきたてられる。通念とは異なり、陽気であけっぴろげな〝ラテン系〟ばかりではないイタリア人たちの感情の深奥にまで、すっと入っていく能力に瞠目させられる。著者は自らをあちこち嗅ぎまわる犬に譬えている。しかし、著者が他者とうちとけ、自宅に招き、手料理でもてなす達人である点も決定的に重要だろう。寂しがり屋たちの慈悲深い〝飼い主〟としての側面すら窺える。しかもとびきりの逸話の数々をわれわれにまで惜しげもなくふるまってくれるのだ。歓待の精神をどこまでも貫くその姿勢に、尊いものを感じずにはいられない。
ALL REVIEWSをフォローする