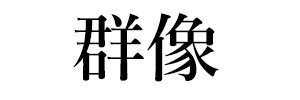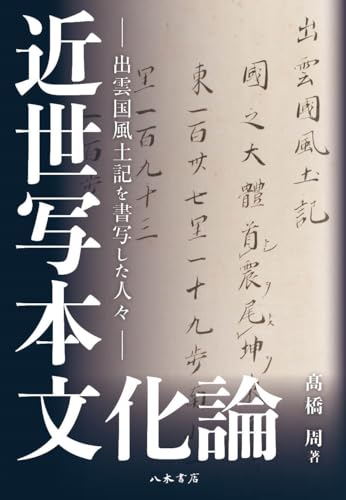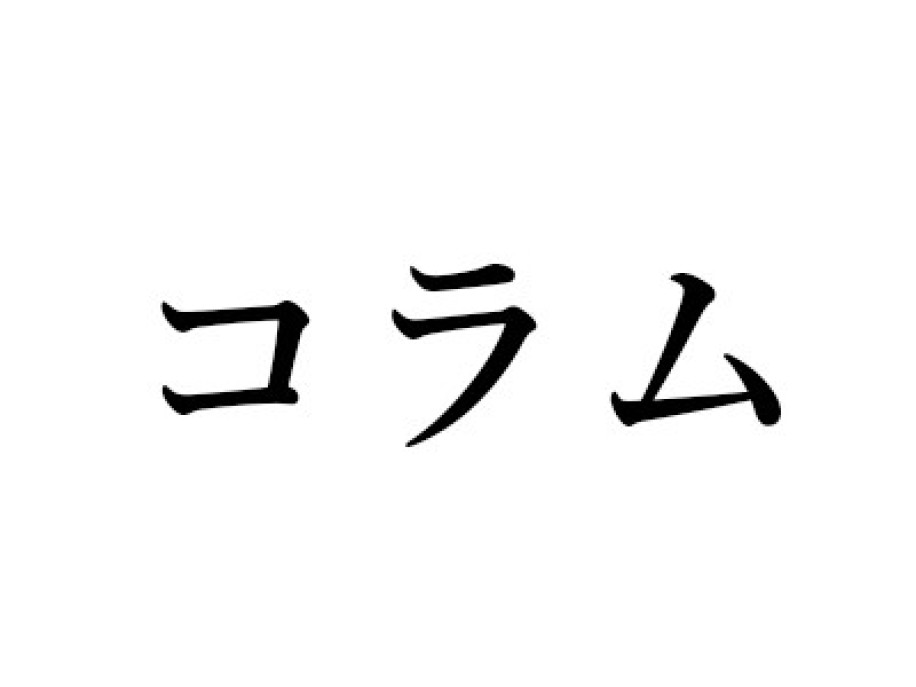書評
『双子は驢馬に跨がって』(河出書房新社)
地図が領土になるとき
目が醒めてから再び眠りに就くまでのあいだ、今日も「君子危うきに近寄らず」は辛抱強く待ち続けていた。
書き出しの一文である。何と変てこな名前の登場人物であることか。相変わらずやってくれるなと嬉しくなってしまう。冒頭からふわりと現実を遊離して、虚構の世界に身を移すのが金子作品の流儀なのだ。
前作『鳥打ちも夜更けには』の冒頭はこうだった。「沖山が架空の港町で鳥打ちを始めてから、すでに十年が経とうとしていた」。いきなり「架空の」とは恐れ入った。デビュー作『アルタッドに捧ぐ』はといえば、主人公の青年が書いていた物語中の人物が鉄道自殺し、轢死体の一部が原稿用紙の上に投げ出されるという摩訶不思議な事態から始まっていた。これはまったくの空想ですよとあからさまに告げておきながら、理屈っぽい“メタフィクション”にも、ひとりよがりな夢物語にもならない。また、ファンタジーノベルやSFといった既成のジャンルの内側で書かれているという感触もない。分類を拒む金子作品のたまらない魅力は、何といってもその筆致の伸びやかさにある。絵空事を丹念に綴る文章の心地よい息づかいに身をゆだね、明晰で滑らかな行文を辿るうち、そこに広がり出すまぼろしの世界が何とも親しみのあるものに思えてくる。
そうした金子作品のユニークな特質が、いよいよ見事に発揮されている。なにゆえにか部屋に幽閉された「君子危うきに近寄らず」とその息子「君子」は、日々ひたすら、双子の少年と少女が驢馬に跨って彼らを助けに来るのを待つ。それはらちもない空想にすぎないのかと思いきや、実際に双子が存在することを読者はすぐに知ることになる。小学五年生の双子は、驢馬との出会いを機に両親に別れを告げて放浪の旅に出発する。やがて二人は、どこかに閉じ込められている人たちがいるという噂を聞きつけて彼らの救出を目指す。父子の物語と双子の物語を交互に並べる構成は、やがて二筋が一点で交わる瞬間を期待させる。実際、その瞬間はやがて訪れ、物語のクライマックスを形作る。
しかしそうした劇的な展開とは別に、そこに至るまでの過程に何とも味わいがあり、発見がある。いったいどこに向かうのかわからないスリルがあり、かつまた一歩一歩をじっくりと掘り下げる構えがある。その結果、決して長大な物語ではないのに、何か現実の時が引き延ばされたような特異な時間が流れ出す。実際、父子も双子も、およそ非日常的な時間を生きている。父子は監禁状態によって強いられた無限反復的な日々のうちにあるし、双子のほうは、どこかにいるはずのだれかを救いに行くというあまりに儚い目標に向かってひたすら進むうち、過去の記憶を失い、現在時のみを生きるようになる。どちらの場合も、一見何とも空漠とした、のっぺらぼうな時間のうちに捕らえられているように思える。
ところが、そんな状況を閑雅な余暇であるかのように受け容れ、楽しもうとする姿勢が金子の小説を支えている。『アルタッドに捧ぐ』の主人公は大学院受験に失敗して「丸一年間の休暇をもらったかの如く時間を持て余していた」。だからこそ彼は物語を綴り、愛嬌ある爬虫類動物アルタッドとの共棲を享受することができた。『鳥打ちも夜更けには』にも、蟄居状態とそれを満たす想像力の充溢が示されていた。そうしたモチーフを受けつぎながら、ここでは時間を持て余す存在にこそ実現しうるちょっとした“奇跡”が描き出されている。
父子は双子の到来を願いながら、自分たちと彼らのあいだに広がる土地の地図を、部屋の壁いっぱいに描く。双子はまさにその地図に従ってやってくる。そして建物のそばまで到達すると、今度は双子が建物周辺の地図を自分たちで描き、それを手掛かりに内部に踏み込む。先に現実があって地図があるのではない。地図ができあがれば、そのとおりに現実が立ち上がり、領土が生み出されるという魔法のような事態を、父子と双子が共有するのだ。
あまりにメルヘン的な展開というべきだろうか? それが決して安易な設定と感じられないのは、奇跡の実現を待ち望みながらも、非力と無為をかみしめる者たちの姿が丹念に描かれているからだ。朝の「白米と冷水」と夕の「鶏肉入り南瓜スープ」で命をつなぐ父子は、実は自分たちが本当に父と子であるのかどうかさえ確信がもてない。自明ではないその絆を、二人は囲碁に打ち込むことで育んでいく。監視の目を盗み、トイレの扉に書いた升目を用いて盤上の豊饒な空間に精神を遊ばせる二人の姿もまた、徐々に双子化しているといえるかもしれない。あるいはまた、驢馬を連れた双子のかたわれがふと述懐するとおり、ひょっとすると彼らは「本当はただひとりの人間」なのかもしれない。
そのただひとりの人間とは結局のところ、白い紙の上に忽然とこれらの人物たちを出現させた作者自身に送り返されるのだろうか? この物語を支える、あり余るほどの時間という感覚や、幽閉と彷徨、そして空想による現実の侵食といった主題は、すべて金子の創作にとって本質的な条件であるにちがいない。そこから出発してどこにもない場所へと読者を導いていくわざを、金子は鍛え上げている。しかも飄逸な軽みや、一種アマチュア的な遊戯性が失われることはなく、いっそうその輝きを増している。今日、あまり類例のないほど純乎とした作品世界なのである。金子の小説はまだ広範に知られてはいないかもしれないが、その貴重な個性は特筆すべきものだ。今後も彼は、引き延ばされた時間から滴り落ちるしずくのような作品を紡ぎ続けるにちがいない。
ALL REVIEWSをフォローする