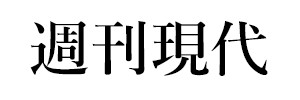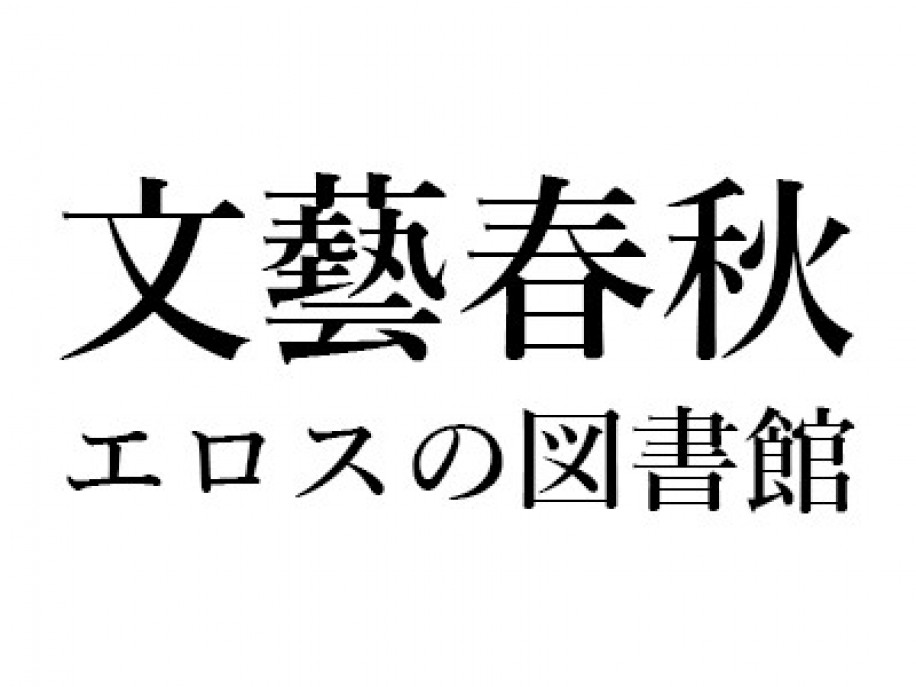書評
『神の値段』(宝島社)
幻の芸術家の過去作と経営者の死に隠された真実とは。美術業界が舞台の鮮烈なミステリー
読みながら、未知の世界への扉が開くのを感じた。いや、自らそれを開けたい気持ちになる。現代美術という扉を。第十四回『このミステリーがすごい!』大賞受賞作の一色さゆり『神の値段』は、美術商取引の業界を舞台とした長篇作品である。物語の鍵を握るのは川田無名(かわたむめい)という美術家だ。川田の特徴はメディアだけではなく美術関係者の前にも一切姿を見せないことで、専属契約を結んでいる永井唯子(ゆいこ)、アトリエを監督する土門正男の両者としかつながりを持っていない。神秘性が人気の一因でもあるのだ。ある日、唯子の経営するギャラリーに、無名の過去作が運び込まれてくる。制作年は一九五九年、美術家が勇名を轟かせることになった個展の前年に描かれた作品だ。コレクターにとっては垂涎の対象で、間違いなく高値で取引されるはずである。しかし不慮の事態が起き、唯子は落命してしまう。
ギャラリーのアシスタントを務める田中佐和子の視点を通じて、読者は美術の世界に入っていくことになる。おそらく作者はこの世界に通暁しているのだろうが、知識をひけらかしすぎることはなく、情報も程よい調子で提供される。
小説の影の主役は舞台になかなか登場してくれない川田無名だが、彼の存在が説得力をもって語られている点もいい。美術市場は、作品を世に送り出す作家をも商品として消費しようとする。そうした生臭い現実が、川田無名を追い求める動きの中で表現されるのだ。永井唯子の死と幻の芸術家の正体、その二つの謎が合流したところに真相はある。幕切れの情景も非常に印象的だ。
小説を一つの芸術品だとすれば、プロットやキャラクターといった要素は構図や色彩などのわかりやすい「部品」である。しかし、細かな筆遣いや素材選びの妙で生まれた表面の質感のように、注視したり、手で触れてみたりしなければわからない要素もある。『神の値段』はそうした部分にも細心の注意が払われた作品なのだ。ゆえに楽しく、愛玩したくなる。
ALL REVIEWSをフォローする