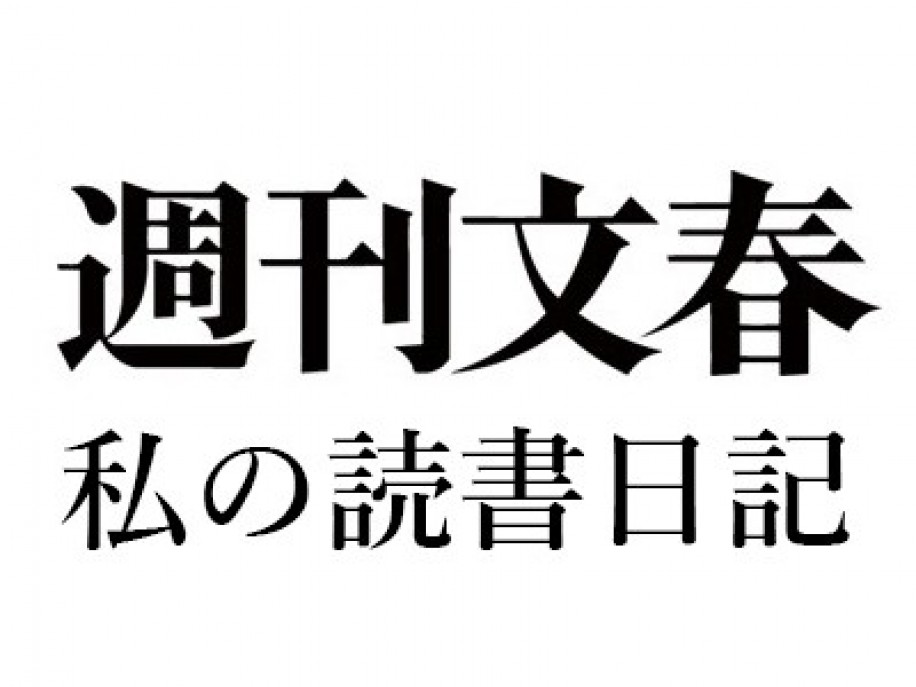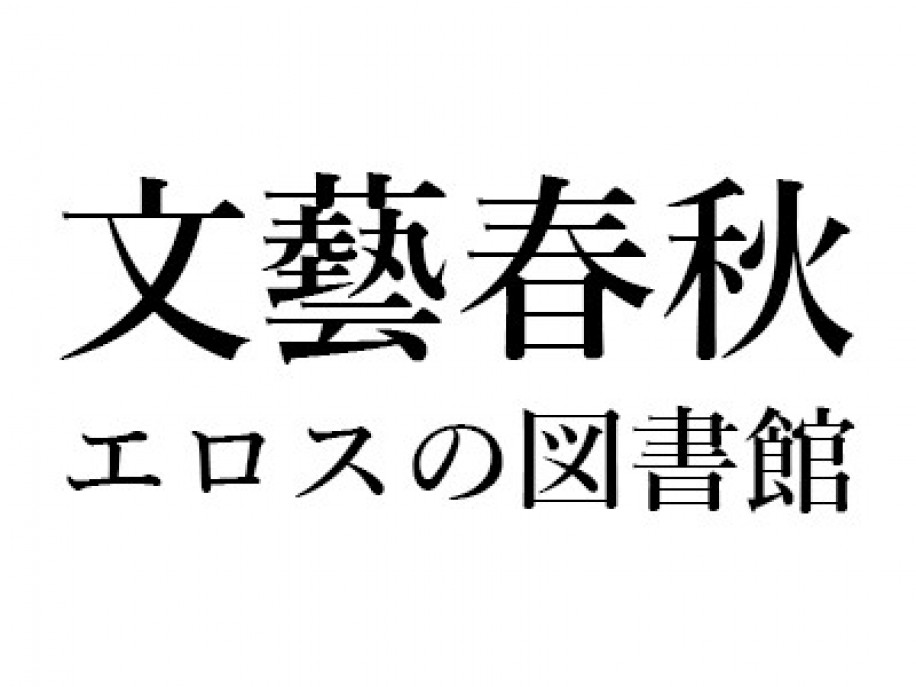書評
『恋愛の日本史』(宝島社)
日本は性におおらかなのか? 日本史が専門の著者の質問だ。答えはイエス。宮本常一ら民俗学者が各地を巡り埋もれた資料を集めた。著者は昔、資料の「土佐源氏」を読み衝撃を受けた。馬喰(ばくろう)の老人が自分の性遍歴を告白して自慢する内容だ。
日本は父系社会でない。昔は妻問い婚で女性に主導権があった。中国の宮廷のような後宮も宦官もなかった。源氏物語をはじめ王朝文学は、そうした背景で花開いたのだ。
仏教が独身主義を持ち込んだ。稚児を愛でる男色文化が蔓延した。武士も家を離れ共同生活するので、男色はありがちだった。大名は跡継ぎを確保するため、側室を置いた。
江戸時代には儒学が普及し、武家社会は窮屈になった。女性は貞淑を求められた。重苦しいイエ制度だ。庶民はまだしも自由だった。江戸は男性過剰の都市で、遊廓が繁盛。お伊勢参りも息抜きの機会だった。
日本の男女のあり方は、儒教どっぷりの中国と違う。キリスト教の性道徳とも別系統だ。日本人のこの感覚は、海外の人びとには理解されにくい。それを踏まえておくのは大切だ。気軽に読める新書だが、しっかりしたワンテーマの一冊である。
日本は父系社会でない。昔は妻問い婚で女性に主導権があった。中国の宮廷のような後宮も宦官もなかった。源氏物語をはじめ王朝文学は、そうした背景で花開いたのだ。
仏教が独身主義を持ち込んだ。稚児を愛でる男色文化が蔓延した。武士も家を離れ共同生活するので、男色はありがちだった。大名は跡継ぎを確保するため、側室を置いた。
江戸時代には儒学が普及し、武家社会は窮屈になった。女性は貞淑を求められた。重苦しいイエ制度だ。庶民はまだしも自由だった。江戸は男性過剰の都市で、遊廓が繁盛。お伊勢参りも息抜きの機会だった。
日本の男女のあり方は、儒教どっぷりの中国と違う。キリスト教の性道徳とも別系統だ。日本人のこの感覚は、海外の人びとには理解されにくい。それを踏まえておくのは大切だ。気軽に読める新書だが、しっかりしたワンテーマの一冊である。
ALL REVIEWSをフォローする