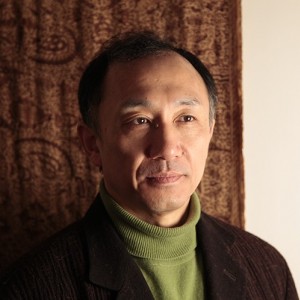書評
『現実の向こう』(春秋社)
不気味な「他者」を不気味でなくすには
日本国憲法を生かしながらイラク撤兵や北朝鮮戦略、国連改革に具体的な提言を行おうとするならば、「改憲命」の保守派から現実離れを嗤(わら)われるのが近年の相場。だが極東アジアの動乱から国土を保守しようとしてアメリカに頼り、負い目からイラクに派兵するという論理にも無視しえぬねじれがある。著者は難解な思想で知られるが、「イラク派兵」「オウム事件」「『砂の器』リメーク版」を手がかりに、ハーバーマス、デリダ、ローティら現代思想の大御所連を助演俳優にかり出して、提言を引き出す論の進め方は劇的かつスリリング。また書店で行った講演集だけあって読みやすい。
強引に要約すると、ポイントは二つある。第一は時代診断で、欧州は普遍的正義を追求して「話せばわかる」モダン状況にあり、アメリカは各文化が追求する価値に優劣をつけがたく「話してもわかりあえない」ポストモダン状況にある、という。日本ではさらに両者が戦後史に投影されて、モダンの「理想の時代」がアメリカに憧(あこが)れた70年まで、サブカルチャーに耽溺(たんでき)するポストモダンの「虚構の時代」が95年まで続いた、とみる。
第二に、欧と米、モダンとポストモダンは話し相手たる「他者」の扱いをめぐり抜き差しならぬ対立関係にあり、アメリカの先制攻撃ドクトリンは、理解しえぬ他者への不寛容に由来する。
提言は、ポストモダンの乗り越えを目指している。他者は不気味であっても攻撃せず、逆に「歓待」ないし「贈与」してみよう。自他ともに変質する(気心が知れる)はずだ。「北」で言えば、日本が無数の難民受け入れを覚悟するという「難民ピクニック作戦」で東欧的な民主革命を期待できる、というのである。
自他の転変は対話の本質であってポスト・ポストモダンに特有の現象ではないし、難民でなく戦闘員がやってきたら、などと疑念も湧(わ)くが、金体制が崩壊すればいずれ難民問題は不可避となる。派兵を拒否するなら何を負担しなければならないのか。護憲派も哲学まで総動員で検討しようという主張に共感した。
朝日新聞 2005年3月13日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする