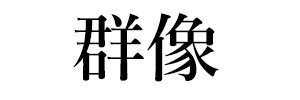書評
『恋愛の不可能性について』(筑摩書房)
論理の物狂おしさ
いきなり部屋に入ってきてただ「レーナ」とだけ名乗り、そのまま語り手の「ぼく」と暮らしはじめた女性との関係を描くセルゲイ・ドヴラートフの短篇「これは愛じゃない」を素材にしながら、「愛」の問題を職業や外面的な性質に返すことのできない固有名の問題にむすび、「他者」の、そして「私」のありように関する先鋭な考察へと一挙に飛躍させる書き下ろしの「序章」は、『恋愛の不可能性について』と題された本書を見わたすうえできわめて有益な緒言であるばかりでなく、恋愛に内包されている不意打ちの出会いを、すなわち「愛の理由が相手の性質に還元しえない」事情を、簡潔に解きあかしたエッセイとしても秀逸である。顔立ちや年齢や出身地がどうであれ、その相手が自分にとって離れがたい存在となる不可思議な「愛」の現実をとらえるために、著者はドヴラートフのタイトルにふくまれる指標語「これ」の重要性へと読者を導き、命名に際して不可欠なこの指標語が、「名指す私を中心=原点とする宇宙の内部における要素として、その個体を指示する」ためにどうしても必要であり、それは「対象とともに宇宙そのものを同時的に指示すること」だとしたうえで、同様の理路が「私」という一人称にも適用できるはずだと述べる。「私」もまた、具体的な記述に還元しようのない存在だからだ。
自問はここでふたたび「愛」へと返され、以下のように定義される。「愛とは、私であるということと、他者(あなた)であるということが、同じことになってしまう体験」であり、「私であるということが、すでに、私の固有性に還元できない外部性を帯びており、差異性=他者性としてあるということ。愛とは、こうしたことを私に対して告げ知らせる体験なのである」。おのれの性格や想いを投影できない、絶対の距離としてある他者。「私」はそういう他者なくしてはありえないし、また絶対的な他者のほうも、それに依存している者なくしてはけっして顕現しない。愛はこの逆説を内包してのみ成立する。
クリプキ、パーソンズ、ウィトゲンシュタイン、パットナム、ルーマン、サール……。それこそ幾人もの固有名に結びついた学説を敷衍しながら、著者は逆説の生じる一点に、「外部へと繋がる開口部」に眼を凝らし、この開口部から生まれるはずの他者との共生空間があくまで抑圧されていなければならないことを、「貨幣」とその背後につらなる超越的な第三者の関係に、「他者の享受を享受する」レヴィナスの「自己貨幣化」の主張に、「待つこと」と「待たれること」が厳しく反転しつづけるベケットの世界に、あるいは「数学的な探求が、同時にそれ自身で社会学」となる関係に、さらには表現されえないことを通じてのみ表現されるユダヤの神に連結して鮮やかに立証する。
ただし、自己「表現」の存立にかかわる「他者」の影が、中途半端な徳に返されることはない。「単一の宇宙=自己」の殻に楔を打ち込む、それじたいもうひとつの宇宙である「他者」の招来が、具体的な映画や小説や詩との遭遇の不意打ちに代替されることもない。
ベケットの『ゴドーを待ちながら』、カサヴェテスの『オープニング・ナイト』などが引き合いに出されているにもかかわらず、それらに対する具体的な「愛」の表明はかたくなに禁じられているのだ。自己の宇宙を一篇の作品がつよく揺さぶり、揺さぶられた自己がそれによって露出したなにかをもう一度その作品に送り返すこと。これは文字どおりの「反復」ではなく、「異なるもの(他者)が、同じもの(私)として再来する運動」なのであって、「他者」に相当する真の「作品」とは、「本性上、未規定な空無でしかありえない」からである。だとすれば、いったいこれほど執拗にその虚にむけて言葉を発しつづける理由はどこにあるのか。「能動的・自律的であろうとする」行為が、例外なく「他者の承認に依存してしか構成されえない」という定理は、一、二章で証明されているではないか。そのような終わりなき反復になぜ身を投じる必要があるのか。
たぶん大澤氏は、そうした宇宙の内部で「他者」と遭遇する機会の訪れを悶々と待ちつづけるひとりのゴドーなのだろう。一見したところ私のような門外漢に対する善意の配慮とも受け取れる徹底的な主題の変奏は、じつは著者自身が、「愛する他者」をもとめて、破壊された橋の橋脚と橋脚のあいだをオートバイでジャンプするパーヴェヴ・ヒューレの「初恋」の主人公のような、決死の跳躍を反復していることの証なのである。つまり本書は、「異なるもの(他者)が、同じもの(私)として再来する運動」にほかならぬ「愛」を、けっして相対化されえない純粋な差異=絶対の距離を抱えた体験としての「愛」をひたすらに追い求めている男の、求愛の症例集なのだ。
大澤氏が探り当てようと躍起になっているのは、ありうべきコミュニケーションの不動の軸である。それが貨幣であれ愛であれ言語であれ、出会いの一撃にいかなる言葉を与え、いかなる「他者」に邂逅しうるか。「恋愛の不可能性」はこうして裏返しの可能性を明示することになる。最終章で新興宗教や電子メディアの問題に触れられているのも、社会学者としての責務という以上に、「他者の他者性」を排したところにはごくあたりまえの意思疎通すら成立しないのだと訴える「単一の自己=宇宙」の住人の、否応ない欲求の帰結だと感じられる。
いずれにせよ、「後続の他者」をつねに意識している書き手の、止揚に止揚を重ねる筆づかいは、欠如の時代から欠如の不在の時代へ、さらに欠如の不在が欠如に反転する戦後日本の動向を柔らかな語り口で明らかにした『戦後の思想空間』よりも、かえって濃厚な肉声を、いわば論理の物狂おしさとでも呼ぶべきものを響かせて、じつに生々しい。
ALL REVIEWSをフォローする


![オープニング・ナイト [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/41MMsNKNnUL.jpg)