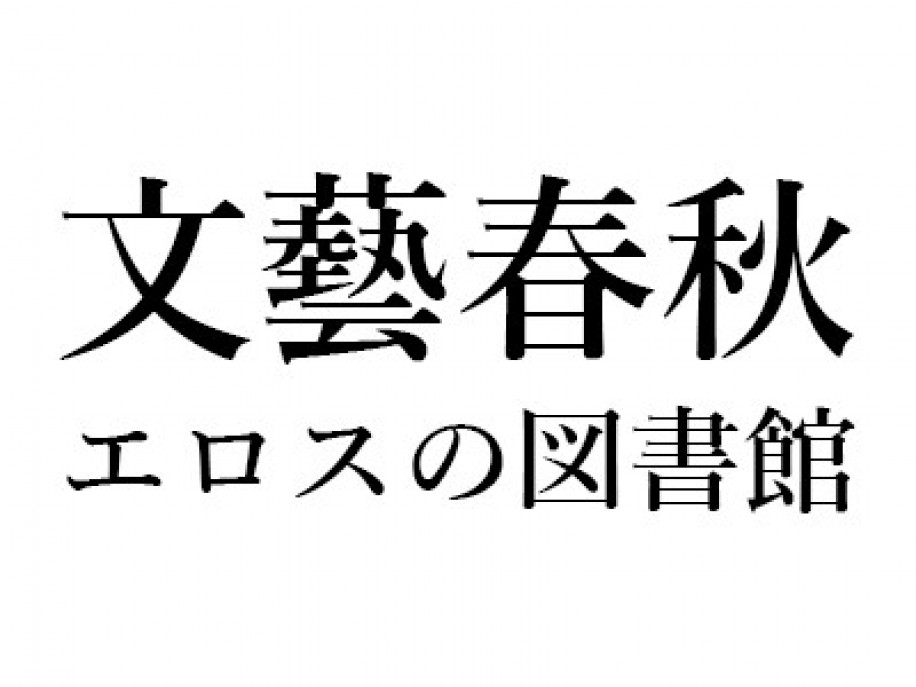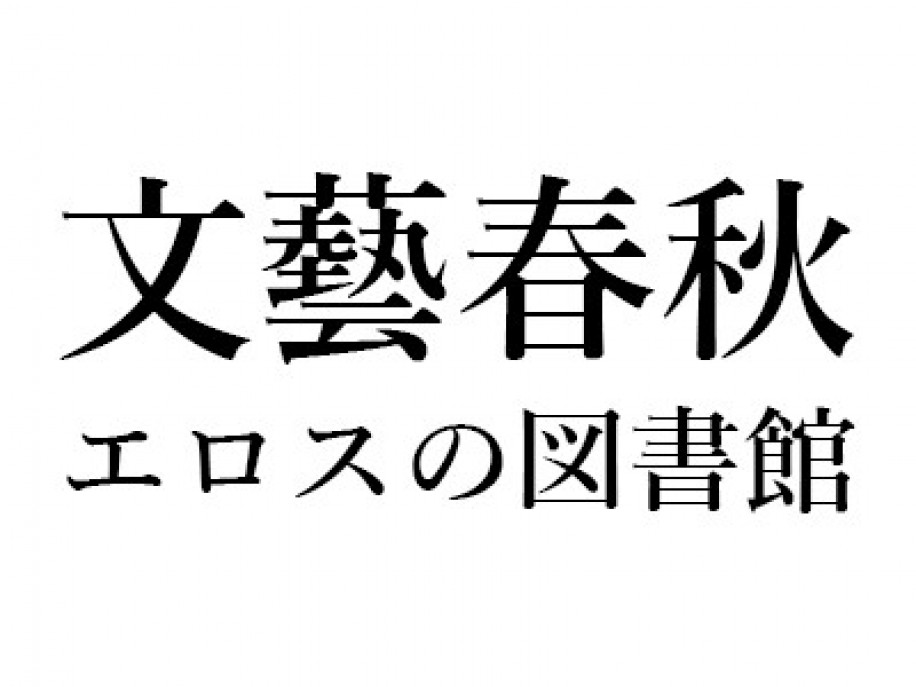書評
『性欲の研究: エロティック・アジア』(平凡社)
人間と文明に対する根本的な視座
あたりまえのことだが、性欲の研究は人間にとって根本的に大切なことである。なぜなら、性欲がなければ人間は生じない。遠い話からはじめる。京都帝国大学文科大学・初代学長は狩野亨吉(こうきち)であった。大哲学者。この国の学識の最高峰。夏目漱石が終生敬愛し、漱石の弔辞は彼が読んでいる。裕仁親王(のちの昭和天皇)の教育掛も狩野をおいて他にないとされ、文部大臣浜尾新(あらた)が説得したが、固辞。そのとき、狩野は学長を辞めて古書商となり、春画をあつめ、おのが性器のスケッチをとって、性欲の研究に没頭しているところだった。この京都帝大文科の初代学長以来の伝統があるのか、どうかは知らない。しかし、人間社会の探究において性欲を排除しない学問の王道を歩む研究者の集まりは、いま京都に「関西性欲研究会」として存在する。本書はその研究成果である。編者の井上章一氏は、性欲という透視装置で時代をながめ、人間と文明の本音にせまろうとしている。いま尖閣で日中関係はぎくしゃくしている。だが、編者はこういってのける。反日デモで中国人がこんなプラカードを掲げていた「釣魚島はわれわれのもの。蒼井そらはみんなのもの」。もちろん、釣魚島は沖縄県石垣市尖閣諸島魚釣島のこと。蒼井そらは日本の人気アダルトビデオ女優である。中国の男たちは「日本はきらいだが、彼女は好きだという」。日米安保闘争の頃、日本でも反米感情が高揚した。しかし、アメリカ帝国主義を批判する人もマリリン・モンローには、ときめいていた。「そこへ目をむければ、一般的な歴史とはちがう、まったくべつの歴史像もうかびあがってくるのではないか」。ユーモアにくるんで、ずばりと本質が突かれている。ともに性欲をもった人間という生物レベルにまで、ぐっと視座をひけば、今日的問題でもあるナショナリズムの激化も、そこから自由にながめられるにちがいない。
井上氏と鹿島茂氏の対談はエスプリに満ちているし、また井上氏と劉(りゅう)建輝氏の対談も興味深い。ソープランドとラブホテル。この国の二大性風俗は、どうやら上海から日本へ、東アジアのなかで伝播(でんぱ)しながら発達したらしい。昭和戦前期までの上海は国際貿易港として独身男性が多く、なかでもフランス租界は売春をみとめていた。その上海から日本に持ち込まれたというのだ。ストリップについては井上氏が日本のすぐそばにある西洋都市ハルビンに注目し、ロシアからの影響を指摘している。
インドから東南アジア、中国、そして日本は、エロティックな文化でも連なっている。ただ、連なっているが相違もある。三橋順子氏が、トランスジェンダーの面から、これを考察している。中国に昭和戦前期までいた相公(シャンコン)――男色を売る女と見まがうような美少年について文献を網羅して詳細に分析。インドのヒジュラ、中国の相公、日本の陰間(かげま)という三カ国の男娼(だんしょう)の比較を試みている。つまりヒジュラはジェンダーの女性化(女装)かつ去勢。相公は女装だが去勢はない。陰間はジェンダーの女性化も去勢もない。男娼の装いと身体において、インド→中国→日本と手を加える程度が低くなっているらしい。本書では、性愛技法や美容整形への認識でも、日中韓には隔たりがあることも論じられている。
ここで行われているのは人間を直視しようとするまじめで誠実な学問である。性欲を考えに入れない歴史文化研究は土台のない建築に等しい。本書はその土台を与える希有(けう)な書だ。
ALL REVIEWSをフォローする