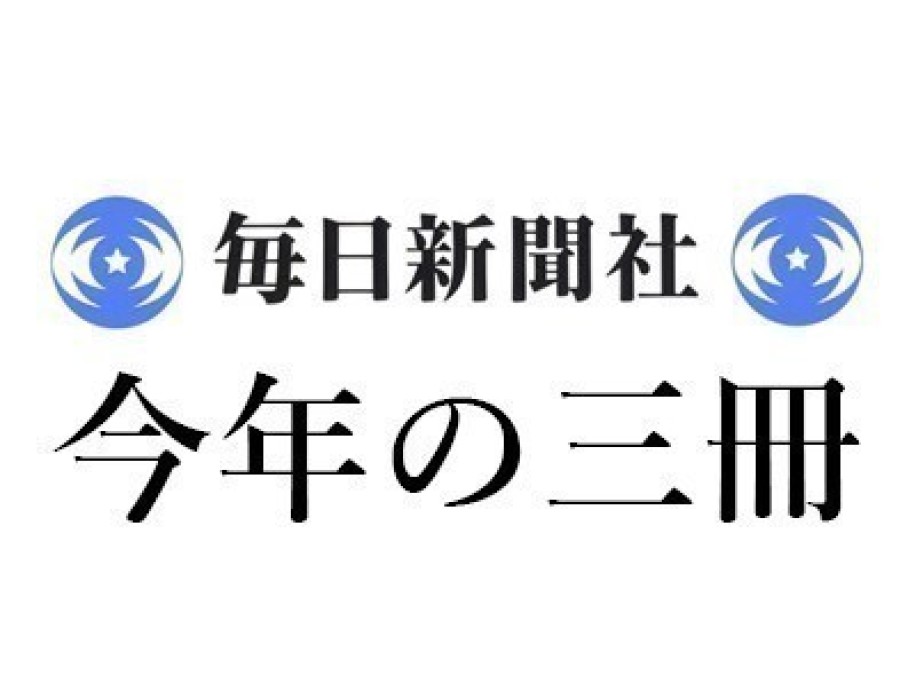書評
『移民受入の国際社会学―選別メカニズムの比較分析―』(名古屋大学出版会)
経済競争がもたらす概念の多層化
ここ数年、「移民」、「難民」という言葉が、世界政治を動かすキーワードとなっている。本書は、世界における移民・難民問題の現状に関する正確な知識を得るために、非常に有用な研究書である。「選別的移民政策」という概念を切り口に、古典的移民国であるアメリカ、オーストラリア、最近になって受入国に転じたEU諸国、そして、「後発受入国」である日韓の政策が比較されている。グローバルな人の動きは、1990年代から徐々に増大してきた。それにはいくつかの要因があった。冷戦の終焉(しゅうえん)により、大きな政治的障壁が取り除かれたこと。世界的な経済自由化により、移動のコストが大幅に下がり、より広範な人が移動することが可能になったこと。携帯電話、GPSなどの技術の普及により、自分の存在位置に関する認識が変化したこと。インターネット、特にSNSの発展に伴い、外の世界に関する情報の経路と情報量が急増したこと。アジア・アフリカ世界の急速な近代化と、それと並行していくつかの内戦の激化、人の移動に関する犯罪組織がらみの仲介業者の爆発的増大、などである。
これらは人を送り出す側の事情であったが、受け入れる側にもいくつかの事情が共通してあった。かなりの先進国で少子高齢化が進んだにもかかわらず、産業構造が急速に変化し、IT産業など一部産業で、高度な技能を持った人材が不足した。他方、グローバルな経済競争の中で、より優秀な人材を低コストで調達する圧力に各国経済がさらされた。その結果、2000年代以降、多くの先進国に、労働力を選別的に受け入れて、自国の競争力向上に役立てようという動きが現れた。
例えばイギリスのブレア政権が、「選択的開放」を実現するための「管理された国際移動」を掲げ、フランスのサルコジ政権は、それまでの新規入国停止、定住移民のフランス社会への定着推進という「統合コンセンサス」を変更し、「国民経済の需要」と「社会の統合能力」に応じた「選択された移民」の受け入れを提唱した。オーストラリア、カナダなどが実施していた「ポイント」制度を、自国流にアレンジして取り入れる国が増えた。
同じころ北欧諸国でも、「国民福祉国家」から「国民競争国家」へと、国家観の転換が起こり、国家が必要とする高度技能を持つ人材獲得戦略としての移民政策が立ち現れてくる。ドイツではシュレーダー政権下、04年の移民制御法成立を皮切りに、高度・技能人材への門戸開放が段階的に進んだ。このうち大きかったのは、ドイツの大学を卒業したEU域外出身者に、求職のために1年間の滞在許可制度を作ったことであった。これはその後ドイツの高度・技能人材の重要な供給源となった。また、EUのブルーカード(学歴・技能・収入の高い移民を受け入れる制度)導入と並行して、学歴制限、年収制限の緩和などを行い、受け入れる労働者の幅と数を拡大してきた。また、そもそもEUという地域統合の枠組みが高度技能移民の供給メカニズムとしても機能した。
これら諸国に共通しているのは、「移民」概念が、多層化、弾力化していることだ。かつて「移民」とは、母国を捨てて、新しい国の国民となることを選ぶ人々であった。当然母国で食い詰めた、貧しい人々が新天地を求めて移動していた。受け入れる側は、やってくるものをそれぞれの事情でフィルターにかける、という「供給主導型」の移動であった。
しかし今や、「移民政策」とくくられるものの中には、数年単位で経済界が必要としている人材を供給するための様々な入国管理政策が含まれている。そして国家は、国境を守る「番人」から、労働市場が必要とする労働力をいかに効率的に供給するかを考える、人材のプロモーターと化してきている。その選別方法には、よく知られる「ポイント」制度を皮切りに、受け入れ雇用主の確保を条件とする「需要主導型」まで様々な手法が存在する。まさにこれが、本書が移民政策の「選別的政策化」と呼んでいるものである。
これらの欧米事例に比べると、日韓の事例は、やや焦点がぼやけている。それでも韓国の方は、1990年代の民主化の進展とともに移民政策も変化し続け、最近では「選別」しつつ、定住を促進する政策に変わってきている。これに対して日本は、高度技能人材以外は、受け入れないという建前を崩していないが、技能実習生、留学生の就労、介護人材の一定の受け入れなど、現実には人手不足の解消に、外国人労働者が入り込んでいる。しかし本書はその実態に十分に切り込めなかった。
今や日本は、不足している「消費者」を「観光客」というカテゴリーで、大量に輸入し始めている。労働力も部分的に自国民以外に頼らざるを得ない。移民賛成か反対か、ではない。人はいずれにせよ入ってくる。どのような人をどのような形で入れ、どのような資格で、どれくらい滞在させるのか。鎖国をするのでなければ、選別政策を考えるしかない。
[書き手]岩間陽子(いわま・ようこ)
政策研究大学院大学教授、専門は国際政治。
ALL REVIEWSをフォローする