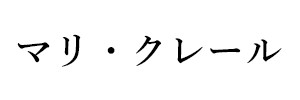書評
『精神医学は対人関係論である』(みすず書房)
この本を読んで確実にどんな読者も得をすることがある。それはいままで分裂病についてもっていた読者の概念に確実に何かを加えられるからだ。加えられた知見が妥当かどうか、有効かどうかは、そのあとで問題にすればよい。不可解な、雲をつかむような分裂病の概念が、いままでよりもはっきりした像を結ぶようになる。それをまずはじめにアレンジして列挙してみる。わたしはそれだけでもこの本から感銘をうけたといっていい。
(1)分裂病の過程(症状、患者の言動、考え方のパターン、紡ぎだすおおくは常同的な物語など)というのは、正常ならば二歳半から後は、意識のなかにはっきり入れておくことをやめてしまうはずの考え方や挙動のパターンを、他人に伝達しようとする試みにあたっている。
(2)強烈な不安や不気味さが生の愉しい状態に不意に立ち入ってこないように「自己組織」のなかに防禦の機構がつくられるが、この防禦が強迫的代理行為によって遂行され、この行為が、不充分な不適切な対人関係の過程になっているとき、それは分裂病である。
(3)分裂病過程は、治癒せずに昂進するばあいは、ふたつの方向をとる。ひとつは人格内の非難や罪悪感の要素を、周囲の人に貼りつける妄想性の順応不全。もうひとつは分裂病過程の不安、恐怖に、人格を解体させることで対応しようとする破瓜型の荒廃。
一見何でもないような知見にみえるが、分裂病についてこれだけのことを言いきったのはこの本の著者サリヴァンがはじめてだし、とくにこんな言い方がされているのはこの本がはじめてなのだ。何がサリヴァンの根本の認識になって、これだけはっきり分裂病について断言できているか、根拠は二つあるとおもう。ひとつは分裂病のどんな常軌をそれた思考や挙動といえども、天(あめ)が下(した)には新しいものなしという認識をサリヴァンが透徹してもっていることだ。つまり精神の病者のどんな振舞いも言動も、かつて人類が未開、原始のある時期か、あるいは個人史の乳幼児期以前あるいは以後にやったことのある言動や振舞いの不意あるいは不測のあらわれでないものはないと見做されていることだ。もうひとつは人間のどんな異常で異様な振舞いや言動も、本人にとって乳幼児のときまでに重要であった対人関係の片割れ(対手)である人物から与えられた強烈で、しかも本人には見当もつかない(つまり「自分でないもの」)不安を基調にした恐怖にみちた衝撃、不気味さ、畏怖、驚愕などと関わりをもつものだということだ。いいかえれば本人には何が原因なのか、どこに緒口があるのか見当もつかない不安の根源になっている構造体があって、それを防禦して「自己」というシステムを解体させないで維持するには、不意うちの由来のわからない不安を和らげたり最小にしたりするために、ある系列の代理行為をするほかないようになる。その代理行為が他人にはしばしば得体の知れない異様な振舞いや言動に見えたりすることになる。
この程度のことは分裂病について誰かがどこかで言っているようにおもえるかも知れないが、じっさいはそんなことはない。この本の著者サリヴァンがはじめて言及したことなのだ。しかもサリヴァンが臨床経験を理論化した優れた精神医学者である所以は、この本でもとてもよくあらわれている。天が下に新しき精神の振舞いや言動はないという認識を徹底化してゆくと、異常な精神の振舞いや言動の記述や解釈は、どうしても単純化され、因果論的につじつまを合わせることに、ひとりでになってしまい、決定論や宿命論の貌をもってくる。これを避ける道はただひとつしかない。豊富で優れた臨床経験とその経験からみちびかれた非因果的な洞察が、解釈を豊饒にし肉付けと陰影を与えることだ。サリヴァンはそれが充分にできていて、高い次元で統合されている。これがサリヴァンの分裂病の理解の仕方につよい説得力を与えている。
じつはこの本の構成は、分裂病の言動や振舞いは、かつて個人史の二歳半までに潜在化されてしまうはずの行動のパターンが顕在化の過程としてあらわれたものであり、妄想性の振舞いもまた個人史のどこかで潜在化されたり、忘却されたりした過程が、不意に出現してきたりしたもので、その契機になったものは「自分でないもの」で、しかも自分に強い不安、畏怖、驚愕を与え、その由来が自分にはわからない要因が作用しているというサリヴァンの基本的な理念を裏づけるために、サリヴァン自身が乳幼児期から小児期、児童期(学童期)、前青春期、青春初期、青春後期、という区分をもうけて、発達心理学的にそれぞれの時期の特徴をたんねんにつかまえようとする記述からはじまり、その記述のために大部分の頁をついやしている。各時期の区分の仕方は発達心理学者(たとえばエリクソン)に従っているが、各時期の特質の把み方はどれもサリヴァンの疾病概念とむすびつくように独特なつかまえ方がなされている。
著者がいちばん重きをおき、大事な基本概念にしているのは「不安」だといえる。これは人間のいちばん早い時期にきわめて不快な体験としてあらわれるもので、この体験に耐えることが、人間として生きることだといってもいいくらいのものだと解釈されている。ではこのひどい「不安」は誰から与えられるかといえば、乳幼児のとき、まだ単独では生きることも育つこともできない折に対人関係を結んだ重要人物―母親または母親役の感情の乱れ、「不安」から転移される。自分が与りしらず、意識もしないのに、原初的な不安や原初的な恐怖はこの母親役から衝撃のように与えられ、この体験は後年に分裂病の障害現象になって再び出現する。この原初的な「不安」は「不気味感」、「畏怖感」、「圧倒恐怖」、「戦慄恐怖」、「嫌悪恐怖」といったさまざまな陰影をもってあらわれてくる。サリヴァンによればこれらの恐怖や不気味さの雰囲気を何とかして回避したい、最小にしたいために人間がとる行いが、生の技術といっていいもので、治療した方がいいとされているものは、そんな悪いものではないと見做すのが妥当だ。つまり症状を治そうとするよりも「不安」にたいして脆弱をあらわす箇所を探ることの方が大切なことなのだ。
サリヴァンは独特の概念でこの原初的「不安」やさまざまなそのあらわれである恐怖の体験に枠組と境界を与える。ひとつは「絶対の愉楽」で、不安がまったくない安らぎの状態、その対極にあるのが「絶対的緊張」で、驚愕恐怖に近い状態で、わたしたちの心の状態はこの両極の中間にある。早速この概念をつかってみると、乳幼児に欲求のため緊張がうまれると、その対人的な重要人物である母親にはこの乳幼児の緊張をやわらげるための「やさしさ」の緊張があらわれる。これを元型的には「やさしさ」の定義としてもいいくらいだ。また逆に母親役のなかに「不安」による緊張があると、乳幼児のなかに「不安」が誘発される。これは鎮静されなければ恐怖をうみだすし、欲求もまた抑圧される。
乳幼児はこの「不安」と欲求の抑圧の状態を母親役から繰返し与えられると、それに対抗し、「不安」な覚醒状態を回避するために、無感情や無感動の状態を身につけるようになる。またひとりでに睡眠状態へ移ること(泣き寝入り)によって耐えるようになる。わたしにはサリヴァンの豊富な臨床体験が生きいきと想起されて、かれの疾病概念へ接近するのをたすけているという感じが、こんなところにとてもよくあらわれているとおもえる。つまり何気なくみえて、とても重要な洞察が語られているとおもえる。乳幼児の無感動や無感情が症状として形成されれば生存を維持してゆくための対人関係で、覚醒時の大部分を無感情で送ることになり懸念がうみだされる。
サリヴァンの母親役と乳幼児との根本的なそして原始的な対人関係の概念は、もう一段だけ高度なところに踏みこむ。この対人関係は確かに生ま身の母親役とその乳幼児の関係から生みだされ対人関係の原型になったり、乳幼児の根本的な「不安」をうみだしたりするのだが、母親にとって乳幼児という存在は擬人存在まで拡大されるし、乳幼児にとっても母親の内部で育ってゆく体験の組織体のところまで拡大され、生ま身の乳幼児とは関わりない因子も含むようになる。ここには覚醒・睡眠・期待や希望・不安と安らぎなどのすべての陰影を映した対人的な関係が生れてくる。わたしたちはここまできて、母親役が乳幼児に与える全スリコミの像が、サリヴァンによって「不安」と安らぎをめぐる原初的な対人関係という概念に要約されているという印象をうける。
サリヴァンの乳幼児の対人関係でなお重要だとおもわれるのは、肛門、糞便、会陰部、外性器に触れてから手を口へもってゆくことにたいする習俗、文化、教育体制、病的清潔感などに由来する母親役のつよい不安と禁止欲求が、乳幼児に与える強力な不安のようなものがある。また児童期における親友の出現の意義、前青春期の対人関係としての「二人組」の関係の意味、この関係がうまくつくれなかったために、自分以外の同性との協同の場面で、たえず緊張を強いられ、夜間の睡眠がとれなくなる精神の障害など、サリヴァン以外のものから記述されれば、社会(対人)心理学になってしまう概念が、精神医学の領分に深くふみとどまっている。それはどうしてかといえば、サリヴァンによって、個人の発達史のなかで、その個人にまったく属さないにもかかわらず、その個人が強い「不安」や恐怖を与えられ、場合によっては睡眠中の悪夢となって繰返しその個人を襲い、しかも覚醒したあとにも悪夢のつづきのなかに在って、そこを脱出できないような振舞いや言動を呈することがあり、これを人々が分裂病と見做しているとしても、この過程が、「自分でないもの」という不安要因の自然成長史としてたどることができることが、臨床体験とその理論化の過程で強固にサリヴァンによって確信されているからだとおもえる。
そこでサリヴァンがこの本で披瀝している重要な概念は二つに要約されるとおもう。ひとつは乳幼児期の母親(役)の乳幼児にたいする対人関係としての意義と振舞いを、赤ん坊部屋や子供部屋の内部の関係から家族外へ、戸外へ、そして生きいきとした社会関係へと解き放ったことだ。生きいきと動く乳幼児と、潜在化された過程で精神障害の要因にまでつながっていく母親(役)の像。もうひとつはフロイトでは乳幼児のリビドーの編成につながっている関係と見做される母親(役)との原初的な関係を、対人関係・親友の登場、二人組をつくる関係などに分割することで、青春期と晩年期をふたつの頂点とする精神障害の在り方のすべてと連結するような理念におきなおしていることだ。
【この書評が収録されている書籍】
(1)分裂病の過程(症状、患者の言動、考え方のパターン、紡ぎだすおおくは常同的な物語など)というのは、正常ならば二歳半から後は、意識のなかにはっきり入れておくことをやめてしまうはずの考え方や挙動のパターンを、他人に伝達しようとする試みにあたっている。
(2)強烈な不安や不気味さが生の愉しい状態に不意に立ち入ってこないように「自己組織」のなかに防禦の機構がつくられるが、この防禦が強迫的代理行為によって遂行され、この行為が、不充分な不適切な対人関係の過程になっているとき、それは分裂病である。
(3)分裂病過程は、治癒せずに昂進するばあいは、ふたつの方向をとる。ひとつは人格内の非難や罪悪感の要素を、周囲の人に貼りつける妄想性の順応不全。もうひとつは分裂病過程の不安、恐怖に、人格を解体させることで対応しようとする破瓜型の荒廃。
一見何でもないような知見にみえるが、分裂病についてこれだけのことを言いきったのはこの本の著者サリヴァンがはじめてだし、とくにこんな言い方がされているのはこの本がはじめてなのだ。何がサリヴァンの根本の認識になって、これだけはっきり分裂病について断言できているか、根拠は二つあるとおもう。ひとつは分裂病のどんな常軌をそれた思考や挙動といえども、天(あめ)が下(した)には新しいものなしという認識をサリヴァンが透徹してもっていることだ。つまり精神の病者のどんな振舞いも言動も、かつて人類が未開、原始のある時期か、あるいは個人史の乳幼児期以前あるいは以後にやったことのある言動や振舞いの不意あるいは不測のあらわれでないものはないと見做されていることだ。もうひとつは人間のどんな異常で異様な振舞いや言動も、本人にとって乳幼児のときまでに重要であった対人関係の片割れ(対手)である人物から与えられた強烈で、しかも本人には見当もつかない(つまり「自分でないもの」)不安を基調にした恐怖にみちた衝撃、不気味さ、畏怖、驚愕などと関わりをもつものだということだ。いいかえれば本人には何が原因なのか、どこに緒口があるのか見当もつかない不安の根源になっている構造体があって、それを防禦して「自己」というシステムを解体させないで維持するには、不意うちの由来のわからない不安を和らげたり最小にしたりするために、ある系列の代理行為をするほかないようになる。その代理行為が他人にはしばしば得体の知れない異様な振舞いや言動に見えたりすることになる。
この程度のことは分裂病について誰かがどこかで言っているようにおもえるかも知れないが、じっさいはそんなことはない。この本の著者サリヴァンがはじめて言及したことなのだ。しかもサリヴァンが臨床経験を理論化した優れた精神医学者である所以は、この本でもとてもよくあらわれている。天が下に新しき精神の振舞いや言動はないという認識を徹底化してゆくと、異常な精神の振舞いや言動の記述や解釈は、どうしても単純化され、因果論的につじつまを合わせることに、ひとりでになってしまい、決定論や宿命論の貌をもってくる。これを避ける道はただひとつしかない。豊富で優れた臨床経験とその経験からみちびかれた非因果的な洞察が、解釈を豊饒にし肉付けと陰影を与えることだ。サリヴァンはそれが充分にできていて、高い次元で統合されている。これがサリヴァンの分裂病の理解の仕方につよい説得力を与えている。
じつはこの本の構成は、分裂病の言動や振舞いは、かつて個人史の二歳半までに潜在化されてしまうはずの行動のパターンが顕在化の過程としてあらわれたものであり、妄想性の振舞いもまた個人史のどこかで潜在化されたり、忘却されたりした過程が、不意に出現してきたりしたもので、その契機になったものは「自分でないもの」で、しかも自分に強い不安、畏怖、驚愕を与え、その由来が自分にはわからない要因が作用しているというサリヴァンの基本的な理念を裏づけるために、サリヴァン自身が乳幼児期から小児期、児童期(学童期)、前青春期、青春初期、青春後期、という区分をもうけて、発達心理学的にそれぞれの時期の特徴をたんねんにつかまえようとする記述からはじまり、その記述のために大部分の頁をついやしている。各時期の区分の仕方は発達心理学者(たとえばエリクソン)に従っているが、各時期の特質の把み方はどれもサリヴァンの疾病概念とむすびつくように独特なつかまえ方がなされている。
著者がいちばん重きをおき、大事な基本概念にしているのは「不安」だといえる。これは人間のいちばん早い時期にきわめて不快な体験としてあらわれるもので、この体験に耐えることが、人間として生きることだといってもいいくらいのものだと解釈されている。ではこのひどい「不安」は誰から与えられるかといえば、乳幼児のとき、まだ単独では生きることも育つこともできない折に対人関係を結んだ重要人物―母親または母親役の感情の乱れ、「不安」から転移される。自分が与りしらず、意識もしないのに、原初的な不安や原初的な恐怖はこの母親役から衝撃のように与えられ、この体験は後年に分裂病の障害現象になって再び出現する。この原初的な「不安」は「不気味感」、「畏怖感」、「圧倒恐怖」、「戦慄恐怖」、「嫌悪恐怖」といったさまざまな陰影をもってあらわれてくる。サリヴァンによればこれらの恐怖や不気味さの雰囲気を何とかして回避したい、最小にしたいために人間がとる行いが、生の技術といっていいもので、治療した方がいいとされているものは、そんな悪いものではないと見做すのが妥当だ。つまり症状を治そうとするよりも「不安」にたいして脆弱をあらわす箇所を探ることの方が大切なことなのだ。
サリヴァンは独特の概念でこの原初的「不安」やさまざまなそのあらわれである恐怖の体験に枠組と境界を与える。ひとつは「絶対の愉楽」で、不安がまったくない安らぎの状態、その対極にあるのが「絶対的緊張」で、驚愕恐怖に近い状態で、わたしたちの心の状態はこの両極の中間にある。早速この概念をつかってみると、乳幼児に欲求のため緊張がうまれると、その対人的な重要人物である母親にはこの乳幼児の緊張をやわらげるための「やさしさ」の緊張があらわれる。これを元型的には「やさしさ」の定義としてもいいくらいだ。また逆に母親役のなかに「不安」による緊張があると、乳幼児のなかに「不安」が誘発される。これは鎮静されなければ恐怖をうみだすし、欲求もまた抑圧される。
乳幼児はこの「不安」と欲求の抑圧の状態を母親役から繰返し与えられると、それに対抗し、「不安」な覚醒状態を回避するために、無感情や無感動の状態を身につけるようになる。またひとりでに睡眠状態へ移ること(泣き寝入り)によって耐えるようになる。わたしにはサリヴァンの豊富な臨床体験が生きいきと想起されて、かれの疾病概念へ接近するのをたすけているという感じが、こんなところにとてもよくあらわれているとおもえる。つまり何気なくみえて、とても重要な洞察が語られているとおもえる。乳幼児の無感動や無感情が症状として形成されれば生存を維持してゆくための対人関係で、覚醒時の大部分を無感情で送ることになり懸念がうみだされる。
サリヴァンの母親役と乳幼児との根本的なそして原始的な対人関係の概念は、もう一段だけ高度なところに踏みこむ。この対人関係は確かに生ま身の母親役とその乳幼児の関係から生みだされ対人関係の原型になったり、乳幼児の根本的な「不安」をうみだしたりするのだが、母親にとって乳幼児という存在は擬人存在まで拡大されるし、乳幼児にとっても母親の内部で育ってゆく体験の組織体のところまで拡大され、生ま身の乳幼児とは関わりない因子も含むようになる。ここには覚醒・睡眠・期待や希望・不安と安らぎなどのすべての陰影を映した対人的な関係が生れてくる。わたしたちはここまできて、母親役が乳幼児に与える全スリコミの像が、サリヴァンによって「不安」と安らぎをめぐる原初的な対人関係という概念に要約されているという印象をうける。
サリヴァンの乳幼児の対人関係でなお重要だとおもわれるのは、肛門、糞便、会陰部、外性器に触れてから手を口へもってゆくことにたいする習俗、文化、教育体制、病的清潔感などに由来する母親役のつよい不安と禁止欲求が、乳幼児に与える強力な不安のようなものがある。また児童期における親友の出現の意義、前青春期の対人関係としての「二人組」の関係の意味、この関係がうまくつくれなかったために、自分以外の同性との協同の場面で、たえず緊張を強いられ、夜間の睡眠がとれなくなる精神の障害など、サリヴァン以外のものから記述されれば、社会(対人)心理学になってしまう概念が、精神医学の領分に深くふみとどまっている。それはどうしてかといえば、サリヴァンによって、個人の発達史のなかで、その個人にまったく属さないにもかかわらず、その個人が強い「不安」や恐怖を与えられ、場合によっては睡眠中の悪夢となって繰返しその個人を襲い、しかも覚醒したあとにも悪夢のつづきのなかに在って、そこを脱出できないような振舞いや言動を呈することがあり、これを人々が分裂病と見做しているとしても、この過程が、「自分でないもの」という不安要因の自然成長史としてたどることができることが、臨床体験とその理論化の過程で強固にサリヴァンによって確信されているからだとおもえる。
そこでサリヴァンがこの本で披瀝している重要な概念は二つに要約されるとおもう。ひとつは乳幼児期の母親(役)の乳幼児にたいする対人関係としての意義と振舞いを、赤ん坊部屋や子供部屋の内部の関係から家族外へ、戸外へ、そして生きいきとした社会関係へと解き放ったことだ。生きいきと動く乳幼児と、潜在化された過程で精神障害の要因にまでつながっていく母親(役)の像。もうひとつはフロイトでは乳幼児のリビドーの編成につながっている関係と見做される母親(役)との原初的な関係を、対人関係・親友の登場、二人組をつくる関係などに分割することで、青春期と晩年期をふたつの頂点とする精神障害の在り方のすべてと連結するような理念におきなおしていることだ。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする