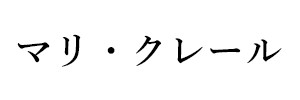書評
『混沌からの秩序』(みすず書房)
まず著者たちの問題の立て方の中心になっている考え方をつかまえておきたい。
眼にみえる物体(たとえば金貨)、そういう物体の質をきめている物質(金や少量の銅その他の金属)、その物質を構成している分子と原子、またその原子を構成している素粒子などの運動や変化や相互変換などを、はっきりと定式化して記述し、それを実験や観察とつき合わせて確かめる分野を力学(古典力学、量子力学、宇宙論)と呼ぶとする。
これにたいして物体の動き、たくさんの物質のあいだに起る相互化学的な変化、またひとつの物質の相変化(たとえば水が氷になったり、水蒸気になったりすること)などに伴う熱エネルギーの出入(発熱、吸熱)を定式化し、法則化し、実験や観察の結果とつきあわせて精密に追究してゆく分野を、熱力学と呼ぶことにする。著者の考え方ではこのふたつの分野はまったく異なったふたつの体系と理念に属していて、両者の関連をつけたり、融合したりするのは難しい。そこで力学と熱力学は別々に発達してきた。もちろん熱もエネルギーの一種だ。また物質もエネルギーの固まりだから、エネルギーに換算してしまうことができる。また熱の出入を伴う物質の変化は、熱力学の第二法則ではエントロピーが増大する方向に進行するから、この次元でいえばエントロピーの変化と、化学反応の起り易さの目安である自由エネルギーとを関係づけることもできる。けれど著者たちの根本的立場は、力学と熱力学とが物質の運動、内部変化、相互変化を記述する二つの異質の学問の分野とみなすところからはじまる。力学のはじまりは万有引力(重力)の作用を記述することであるが、熱力学のはじまりは熱エネルギーの作用と出入を記述することで、このばあい力と熱とは対抗馬のような関係にある。
著者たちは、この本の本題に入ってゆくまえに、もうひとつ根本的な前提を立てている。それは熱力学の第二法則と呼ばれているものに関している。物質が自身で、あるいは他の物質とのあいだで、変化を起すときは、エントロピーが増大する方向に進み、決して逆に進むことはない。だから関与している物質の系にとってエントロピーが極大になったところで安定化する。この変化の過程を不可逆過程と呼ぶ。もうひとつは可逆過程がある。ひとつの物質、また異なった物質のあいだにたとえば化学反応が起るとき、ある点で平衡状態に達する。そこでは正の方向(エントロピー増大)に進行する変化と、逆方向に進行する変化とが釣合ってどちらへも行けるし、またどちらへも行けない状態になっていると考えてよい。
十九世紀に熱力学が研究されてきた経路からいえば、後者の可逆過程の平衡状態の方が単純なモデル化が成立つために、この平衡状態の熱力学が主要なテーマになって発達してきた。そして不可逆過程の方は、変則的で、複雑なため定式化できないものとして、脇におしやられてきた。
著者たちの新しい考え方では、現在この状況は完全に変ってきた。なぜかというと、平衡状態から遠く離れた条件の下で、無秩序(熱的なカオス状態)から全く新しい秩序への転移が起ることが、発見されてきたからだ。この本の著者たちはこの新しい状態を、散逸構造と名づけて、この散逸の過程で起る現象がとても重要なもので、そのことを解き明かしたいために、この本を書いたことになる。
著者たちの挙げている例をたどりながらもう少し、この本のモチーフの奥の方へすすんでみる。著者たちは、簡単な孤立した(外部からの影響や相互作用のない)平衡系からはじめて、平衡から線型に遠くなった系、さらに平衡からアト・ランダムに、乱雑に散逸して遠ざかった系へ、さらに平衡から遠ざかって対流から乱流のカオスへと進んでゆく系について、段階を踏みながら、最後に生命現象のメカニズムを解き明かしてゆく。
著者たちの比喩を使って説明してみる。いま「赤」い分子と「青」い分子があるとする。このふたつの分子をひとつの容器を密閉して左右からそれぞれ容器中に放出してゆくと、はじめは容器の片方ずつにそれぞれ「赤」い分子と「青」い分子が濃くなった状態が出現し、それが次第に両分子の衝突、混合が起ってやがて均質に混合した状態にたどりついて、容器全体は「紫」に見えるようになる。ところがいま平衡状態から遠くするために「赤」または「青」の分子の濃度(分子数)を極度に多くしたり、一方の分子を加熱して温度差を極度に大きくしたり、両分子の圧力差を極度に増加させたりすると、ある境界の閾値を超えたところで、突然まったく予期されない新しい現象が起ることがある。これもまた比喩でいってみれば、この新しい現象というのは、たとえば容器の上部の半分には「赤」い分子が濃く集まり、下部には「青」い分子が濃く集まり、容器の左側には「赤」と「青」の分子一個ずつがペアになって濃く集まり、容器の右側には「赤」の分子一個と「青」の分子二個とが三角対になって濃く集まりというように、均質にならずにまったく予想を超えた状態が出現して、これらが、上部、下部、左側、右側というように規則正しく周期的に転移するといった現象が起りうることが新しく発見された。熱力学の第二法則によれば、普通この系は「赤」の分子と「青」の分子が何れにしろ均質化されたところで、状態は終って平衡か最終状態が出現するはずなのだが、まったく予期しない状態が平衡から遠く離れたところで出現することが知られてきたのだ。著者たちによれば、一九六〇年にベルーソフ=ジャポチンスキーは、セリウム、マンガン、フェロインなどの触媒の存在で、臭化カリウム(KI)を使って有機マロン酸を酸化させる反応で、化学的不安定性の閾値を超えたところで、新たな、予期しなかった現象が起ることを見つけ出した。こういう例は、ブリュッセルで研究されたモデル反応「ブリュッセレータ」、その他「オレゴネータ」、「パロアルトネータ」などで知られている。
もうひとつ著者たちが挙げている生体内で起る分子生物学的な例を取りあげてみる。人間(その他)の生体のなかでは文字通り平衡状態から遠くはなれた条件下で、触媒の存在のもとで、さまざまな新たな予期できないような自己組織化(構造化)の反応過程が起っている。このばあい生体のなかで生物代謝反応にあずかっている触媒の機能は、三種類の過程がある。(1)は自己触媒(Xの存在がX自身を生体内で合成する作用を促進させる作用)、(2)は自己阻害(Xの存在が、X自身の合成反応を妨害して反応速度をおくらせる作用)、(3)は相互触媒(二つの異った反応経路の二つの生成物が、お互いにそれぞれの生成物を生体内で造るばあいの合成反応を促進する作用)。この三種の触媒(生体内では酵素と呼ばれているものが、この役割をする)反応によって生体の内部では細胞成分の合成が行われている。この生体反応のメカニズムは単純であるが、分子(タンパク質、核酸、リボ核酸など)の構造は複雑で特異的な高分子である。これはさきの例にあげた無機化学の反応とちがっている。著者たちの見事な言いまわし方を引用すれば「生体系は『過去をもっている』。生体を構成している分子は進化の所産である。それらの分子は、きわめて特異な組織化過程を作りあげる自己触媒機構に参画するように淘汰されてきた」ということになる。
あらためて、この著者たちの言いまわしを、ここで解説すればこうなる。人間の体内のような生体のなかでは、生物の長い進化(アメーバから人間まで)の過程と年月のあいだに淘汰されずに生き残った成分分子だけが、生き残ることに耐えてきた触媒合成反応を持続して、細胞を造ったり廃棄したり、その他の化学反応を起しつづけている。そしてその結果新陳代謝が行われ、また人間の身体という複雑な自己維持された形態と機能をもった自己組織をつくっているのだ。そしてこの生体内で起っている触媒の存在下の合成反応と、その結果の絶えまない持続は、いままでこの本で述べられてきた、平衡から遠くはなれた不可逆反応が、ある閾値を超えたところで生み出す新たな自己組織化という現象を意味している。人間(一般に生物)の体内で行われている合成反応についての見事な理論づけの記述は、この本のなかでいちばん優れた個所だといえる。これだけのことを知るためだけでも、この本は読んで損しない感じがする。
わたしが感心したもうひとつの例について言及してみる。
細胞性粘菌類のアメーバ(タマホコリカビ)は、環境の栄養状態が悪くなると、はじめばらばらだった細胞の集団が、結合しあった数万個の細胞からできた集塊を作りはじめる。この変形体はつぎに分化をはじめ、そのあいだ形を変えつづけ、「柄」を形成し、また栄養培地に触れるとアメーバの新しいコロニーをつくる。栄養を消費しつくすと、また他の環境に侵入するために移動する。なぜこういう動きを粘菌のアメーバは獲得するのか。それは細胞が集合してゆく過程で「変位波」が起り集合運動が始まるのだとわかってきた。「誘引の中心」には周期性のAMPが高い濃度差をもって存在しており、この条件に細胞が感応した結果、移動が起る。そして循環性のAMPは、「誘引の中心」にいるアメーバによって周期的に生産されることもわかった。この過程を整理すると、平衡から遠くはなれた不可逆な乱雑な系にだけ起る、典型的な新たな反応現象の始まりだということがわかる。つまり周囲の栄養が貧しくなり、消費しつくされてくると、代謝の体制が不安定になり、アメーバはAMPを放出する「誘引の中心」をつくりだし、これは飢餓状態になると、どのアメーバも周期性のAMPを放出する「誘引の中心」になりうるから、系のはじめに生まれた不安定性のゆらぎは、ますます乱雑になり、増幅され、培地を組織化するという、まったく予期しなかった新しい現象を作り出してゆく。
ところでもうすこし細部にわけ入ってゆくと、とても重要な結果が生じてくる。それはいままでまったく別々に形成されてきた力学と熱力学とが、接触し、からみ合い、ひとつのものとしてある新しい細胞現象のなかに統合される場面が、想定できるということだ。著者たちによれば、ベナール細胞の例で、この系が平衡状態にあるときは、この細胞反応には重力の影響は無視できるが、いったん平衡から遠くはなれた状態でゆらぎがはじまると、この細胞はたった数ミリメートルの厚さしかないのに、重力の役割が本質的な影響を与え、分岐点のところで対称性の破れが生じ、系の細胞反応は、まったく新しい状態に移ってしまう。たとえば核酸DNAは右巻きのラセン構造をもっていることが知られている。対称性からいえば左巻きの構造が半分あっていいはずなのに、この生命を司るタンパクは右巻きである。そしてこれを説明できるかどうかは生命の特性を説明できるかどうかと同じことになる。偶然に右巻きからはじまった生命は、そのあとつぎつぎ右巻きを生んでいったとかんがえるか、あるいは左巻き構造もあったのだが、淘汰のながい過程で右が勝って左を消滅させてしまった、そうもかんがえられる。こういう説明にたいし、この本の著者たちの立場は、平衡から遠くはなれた条件のもとで、無視できなくなった重力の影響にたいし右巻きのDNAだけが重力を感知し、それに適用する選択をなしえたので生きのびたのだという説明になる。この説明を正当化するような新しい反応の例を著者たちは発見した。そしてこれが生命現象を司る細胞の構造のなかにある不斉性(非対称性)にたいする著者たちの見解だ。これを見事しめくくった著者たちの言葉で、あらためて言いあらわせばつぎのようになる。「今日の知見によれば、生物圏は全体としてもその個別成分としても、それが生きていようが死んでいようが、平衡から遠く離れた状態にある。この文脈から、生命は自然の秩序から遠く離れて、実際に起った自己組織化過程の最高の形態のようにおもえる」
【この書評が収録されている書籍】
眼にみえる物体(たとえば金貨)、そういう物体の質をきめている物質(金や少量の銅その他の金属)、その物質を構成している分子と原子、またその原子を構成している素粒子などの運動や変化や相互変換などを、はっきりと定式化して記述し、それを実験や観察とつき合わせて確かめる分野を力学(古典力学、量子力学、宇宙論)と呼ぶとする。
これにたいして物体の動き、たくさんの物質のあいだに起る相互化学的な変化、またひとつの物質の相変化(たとえば水が氷になったり、水蒸気になったりすること)などに伴う熱エネルギーの出入(発熱、吸熱)を定式化し、法則化し、実験や観察の結果とつきあわせて精密に追究してゆく分野を、熱力学と呼ぶことにする。著者の考え方ではこのふたつの分野はまったく異なったふたつの体系と理念に属していて、両者の関連をつけたり、融合したりするのは難しい。そこで力学と熱力学は別々に発達してきた。もちろん熱もエネルギーの一種だ。また物質もエネルギーの固まりだから、エネルギーに換算してしまうことができる。また熱の出入を伴う物質の変化は、熱力学の第二法則ではエントロピーが増大する方向に進行するから、この次元でいえばエントロピーの変化と、化学反応の起り易さの目安である自由エネルギーとを関係づけることもできる。けれど著者たちの根本的立場は、力学と熱力学とが物質の運動、内部変化、相互変化を記述する二つの異質の学問の分野とみなすところからはじまる。力学のはじまりは万有引力(重力)の作用を記述することであるが、熱力学のはじまりは熱エネルギーの作用と出入を記述することで、このばあい力と熱とは対抗馬のような関係にある。
著者たちは、この本の本題に入ってゆくまえに、もうひとつ根本的な前提を立てている。それは熱力学の第二法則と呼ばれているものに関している。物質が自身で、あるいは他の物質とのあいだで、変化を起すときは、エントロピーが増大する方向に進み、決して逆に進むことはない。だから関与している物質の系にとってエントロピーが極大になったところで安定化する。この変化の過程を不可逆過程と呼ぶ。もうひとつは可逆過程がある。ひとつの物質、また異なった物質のあいだにたとえば化学反応が起るとき、ある点で平衡状態に達する。そこでは正の方向(エントロピー増大)に進行する変化と、逆方向に進行する変化とが釣合ってどちらへも行けるし、またどちらへも行けない状態になっていると考えてよい。
十九世紀に熱力学が研究されてきた経路からいえば、後者の可逆過程の平衡状態の方が単純なモデル化が成立つために、この平衡状態の熱力学が主要なテーマになって発達してきた。そして不可逆過程の方は、変則的で、複雑なため定式化できないものとして、脇におしやられてきた。
著者たちの新しい考え方では、現在この状況は完全に変ってきた。なぜかというと、平衡状態から遠く離れた条件の下で、無秩序(熱的なカオス状態)から全く新しい秩序への転移が起ることが、発見されてきたからだ。この本の著者たちはこの新しい状態を、散逸構造と名づけて、この散逸の過程で起る現象がとても重要なもので、そのことを解き明かしたいために、この本を書いたことになる。
著者たちの挙げている例をたどりながらもう少し、この本のモチーフの奥の方へすすんでみる。著者たちは、簡単な孤立した(外部からの影響や相互作用のない)平衡系からはじめて、平衡から線型に遠くなった系、さらに平衡からアト・ランダムに、乱雑に散逸して遠ざかった系へ、さらに平衡から遠ざかって対流から乱流のカオスへと進んでゆく系について、段階を踏みながら、最後に生命現象のメカニズムを解き明かしてゆく。
著者たちの比喩を使って説明してみる。いま「赤」い分子と「青」い分子があるとする。このふたつの分子をひとつの容器を密閉して左右からそれぞれ容器中に放出してゆくと、はじめは容器の片方ずつにそれぞれ「赤」い分子と「青」い分子が濃くなった状態が出現し、それが次第に両分子の衝突、混合が起ってやがて均質に混合した状態にたどりついて、容器全体は「紫」に見えるようになる。ところがいま平衡状態から遠くするために「赤」または「青」の分子の濃度(分子数)を極度に多くしたり、一方の分子を加熱して温度差を極度に大きくしたり、両分子の圧力差を極度に増加させたりすると、ある境界の閾値を超えたところで、突然まったく予期されない新しい現象が起ることがある。これもまた比喩でいってみれば、この新しい現象というのは、たとえば容器の上部の半分には「赤」い分子が濃く集まり、下部には「青」い分子が濃く集まり、容器の左側には「赤」と「青」の分子一個ずつがペアになって濃く集まり、容器の右側には「赤」の分子一個と「青」の分子二個とが三角対になって濃く集まりというように、均質にならずにまったく予想を超えた状態が出現して、これらが、上部、下部、左側、右側というように規則正しく周期的に転移するといった現象が起りうることが新しく発見された。熱力学の第二法則によれば、普通この系は「赤」の分子と「青」の分子が何れにしろ均質化されたところで、状態は終って平衡か最終状態が出現するはずなのだが、まったく予期しない状態が平衡から遠く離れたところで出現することが知られてきたのだ。著者たちによれば、一九六〇年にベルーソフ=ジャポチンスキーは、セリウム、マンガン、フェロインなどの触媒の存在で、臭化カリウム(KI)を使って有機マロン酸を酸化させる反応で、化学的不安定性の閾値を超えたところで、新たな、予期しなかった現象が起ることを見つけ出した。こういう例は、ブリュッセルで研究されたモデル反応「ブリュッセレータ」、その他「オレゴネータ」、「パロアルトネータ」などで知られている。
もうひとつ著者たちが挙げている生体内で起る分子生物学的な例を取りあげてみる。人間(その他)の生体のなかでは文字通り平衡状態から遠くはなれた条件下で、触媒の存在のもとで、さまざまな新たな予期できないような自己組織化(構造化)の反応過程が起っている。このばあい生体のなかで生物代謝反応にあずかっている触媒の機能は、三種類の過程がある。(1)は自己触媒(Xの存在がX自身を生体内で合成する作用を促進させる作用)、(2)は自己阻害(Xの存在が、X自身の合成反応を妨害して反応速度をおくらせる作用)、(3)は相互触媒(二つの異った反応経路の二つの生成物が、お互いにそれぞれの生成物を生体内で造るばあいの合成反応を促進する作用)。この三種の触媒(生体内では酵素と呼ばれているものが、この役割をする)反応によって生体の内部では細胞成分の合成が行われている。この生体反応のメカニズムは単純であるが、分子(タンパク質、核酸、リボ核酸など)の構造は複雑で特異的な高分子である。これはさきの例にあげた無機化学の反応とちがっている。著者たちの見事な言いまわし方を引用すれば「生体系は『過去をもっている』。生体を構成している分子は進化の所産である。それらの分子は、きわめて特異な組織化過程を作りあげる自己触媒機構に参画するように淘汰されてきた」ということになる。
あらためて、この著者たちの言いまわしを、ここで解説すればこうなる。人間の体内のような生体のなかでは、生物の長い進化(アメーバから人間まで)の過程と年月のあいだに淘汰されずに生き残った成分分子だけが、生き残ることに耐えてきた触媒合成反応を持続して、細胞を造ったり廃棄したり、その他の化学反応を起しつづけている。そしてその結果新陳代謝が行われ、また人間の身体という複雑な自己維持された形態と機能をもった自己組織をつくっているのだ。そしてこの生体内で起っている触媒の存在下の合成反応と、その結果の絶えまない持続は、いままでこの本で述べられてきた、平衡から遠くはなれた不可逆反応が、ある閾値を超えたところで生み出す新たな自己組織化という現象を意味している。人間(一般に生物)の体内で行われている合成反応についての見事な理論づけの記述は、この本のなかでいちばん優れた個所だといえる。これだけのことを知るためだけでも、この本は読んで損しない感じがする。
わたしが感心したもうひとつの例について言及してみる。
細胞性粘菌類のアメーバ(タマホコリカビ)は、環境の栄養状態が悪くなると、はじめばらばらだった細胞の集団が、結合しあった数万個の細胞からできた集塊を作りはじめる。この変形体はつぎに分化をはじめ、そのあいだ形を変えつづけ、「柄」を形成し、また栄養培地に触れるとアメーバの新しいコロニーをつくる。栄養を消費しつくすと、また他の環境に侵入するために移動する。なぜこういう動きを粘菌のアメーバは獲得するのか。それは細胞が集合してゆく過程で「変位波」が起り集合運動が始まるのだとわかってきた。「誘引の中心」には周期性のAMPが高い濃度差をもって存在しており、この条件に細胞が感応した結果、移動が起る。そして循環性のAMPは、「誘引の中心」にいるアメーバによって周期的に生産されることもわかった。この過程を整理すると、平衡から遠くはなれた不可逆な乱雑な系にだけ起る、典型的な新たな反応現象の始まりだということがわかる。つまり周囲の栄養が貧しくなり、消費しつくされてくると、代謝の体制が不安定になり、アメーバはAMPを放出する「誘引の中心」をつくりだし、これは飢餓状態になると、どのアメーバも周期性のAMPを放出する「誘引の中心」になりうるから、系のはじめに生まれた不安定性のゆらぎは、ますます乱雑になり、増幅され、培地を組織化するという、まったく予期しなかった新しい現象を作り出してゆく。
ところでもうすこし細部にわけ入ってゆくと、とても重要な結果が生じてくる。それはいままでまったく別々に形成されてきた力学と熱力学とが、接触し、からみ合い、ひとつのものとしてある新しい細胞現象のなかに統合される場面が、想定できるということだ。著者たちによれば、ベナール細胞の例で、この系が平衡状態にあるときは、この細胞反応には重力の影響は無視できるが、いったん平衡から遠くはなれた状態でゆらぎがはじまると、この細胞はたった数ミリメートルの厚さしかないのに、重力の役割が本質的な影響を与え、分岐点のところで対称性の破れが生じ、系の細胞反応は、まったく新しい状態に移ってしまう。たとえば核酸DNAは右巻きのラセン構造をもっていることが知られている。対称性からいえば左巻きの構造が半分あっていいはずなのに、この生命を司るタンパクは右巻きである。そしてこれを説明できるかどうかは生命の特性を説明できるかどうかと同じことになる。偶然に右巻きからはじまった生命は、そのあとつぎつぎ右巻きを生んでいったとかんがえるか、あるいは左巻き構造もあったのだが、淘汰のながい過程で右が勝って左を消滅させてしまった、そうもかんがえられる。こういう説明にたいし、この本の著者たちの立場は、平衡から遠くはなれた条件のもとで、無視できなくなった重力の影響にたいし右巻きのDNAだけが重力を感知し、それに適用する選択をなしえたので生きのびたのだという説明になる。この説明を正当化するような新しい反応の例を著者たちは発見した。そしてこれが生命現象を司る細胞の構造のなかにある不斉性(非対称性)にたいする著者たちの見解だ。これを見事しめくくった著者たちの言葉で、あらためて言いあらわせばつぎのようになる。「今日の知見によれば、生物圏は全体としてもその個別成分としても、それが生きていようが死んでいようが、平衡から遠く離れた状態にある。この文脈から、生命は自然の秩序から遠く離れて、実際に起った自己組織化過程の最高の形態のようにおもえる」
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする