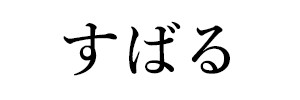書評
『セザンヌ 画家のメチエ』(青土社)
言葉の《tache》、思考の《plan》
セザンヌの絵をめぐる言葉に触れるのが億劫になったのは、たぶん洲之内徹の評言のせいだろうと思う。それがどの時期であるかは明記されていないものの、文脈から言って晩年の作品を指すのはまちがいないセザンヌの画面の「塗り残し」について、「気まぐれ美術館」の館長はこう述べていたのだ。「いろいろと理屈をつけてむつかしく考えられているけれども、ほんとうは、セザンヌが、そこをどうしたらいいかわからなくて、塗らないままで残しておいたのではないか」。文字どおり理屈抜きにそう述べたあと、彼はさらにこうつづけていた。「セザンヌが凡庸な画家だったら、いい加減に辻褄を合わせて、苦もなくそこを塗り潰してしまったろう」と。画家本人でないかぎり、辻褄を合わせないことの意味を追体感するのは不可能である。しかし辻褄を合わせないことが、画家のたゆまぬ努力の果てに訪れた、怖ろしいまでに辻褄のあう、いわば絵画に対して、自然に対して「開かれた謎」であるという事情を徹底的に考察することは可能かも知れない。前田英樹の『セザンヌ 画家のメチエ』は、洲之内徹のいくらか無責任な発言の真実を、「理屈」ではない「理路」の、それもただいたずらに整然としているだけではない思考の「色斑」tache の集積によって立証し、対象と「平行」する言語で考え抜くことの美しさを示した強固な散文の成果である。
絵具としてはマチエールではなく、「あらゆる質量的混合の外」にある「色」でなければならず、しかもその「色」は、自然のなかの「色」と異なる仕方で存在していなければならない。色斑が「表現するもの」と「表現されるもの」を同時に体現する二重の「プラン」となり、それらの「面」の組成が絵画の「深さ」を表現する。「線」ではなく、「色」が深さを実現するのだ――。そんなふうにかい摘んでしまえば抽象的にすぎる議論が、適切な伝記的事実の参照と過不足のない図版の選択、さらに各章のつなぎめで粘り強く変奏、反復されるモチーフによって、しだいに奥行きを生んでいく。頭脳的なものの一切と対立するセザンヌ的な「感覚の論理」に、ほかならぬ頭脳をもって正面からぶつかり、そこに殉じようとする矛盾が、書き手のみならず読み手にも破格の緊張を強いる。「これ以上、付け加える言葉もない」というあとがきの一句は、嘘偽りない真実だろう。少なくとも本書には、いささかの塗り残しもない。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする