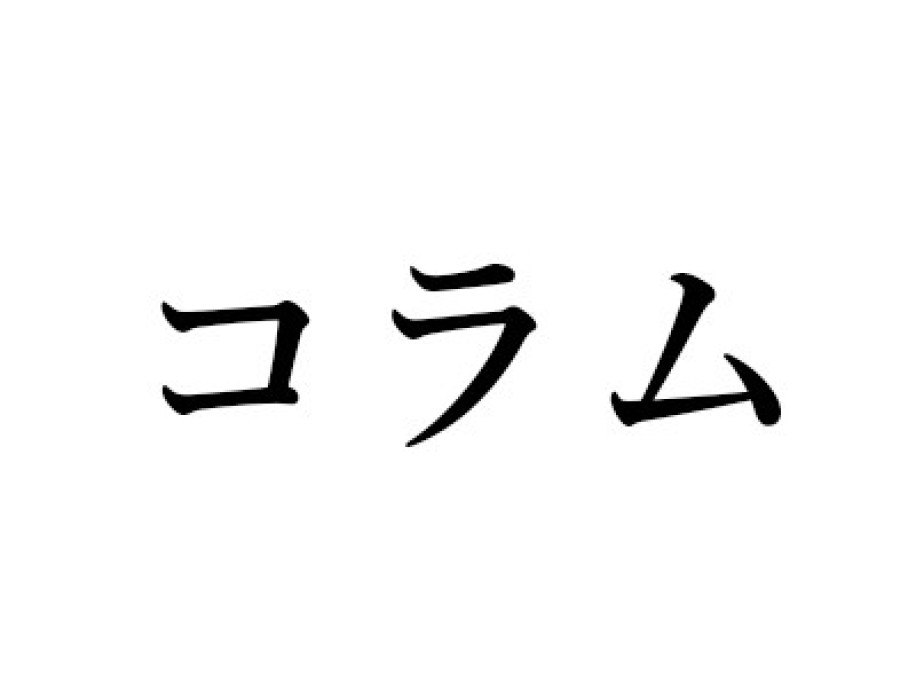書評
『ぼくのコドモ時間』(筑摩書房)
ほのかに熱い思いを呼びさます淡々描写
「コドモ時間」というのは、ボクの造語ですが、こんなコトバをわざわざ思いついたのにはワケがある。コドモのころのことを思い出していると、どうもあのころの一日は、いまよりずっと長かったような気がします。大人(おとな)とコドモでは一日の長さがほんとに違(ちが)うんではないか?
という書き出しで始まる南伸坊の最新作『ぼくのコドモ時間』(福音館書店・現ちくま文庫)を読んで、ボクもほんとにちがうんではないか、と思った(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は1991年)。
この本は昭和二十年代に東京の下町でこども時代を過ごした伸坊氏の思い出話だが、この手の話にありがちな落とし穴をたくみに逃れているのがいい。いちおう世間で認められるようになった大人のする子供時代の回想というのはかならず何がしかの自慢と教訓を含んでいるが、そうしたくささがきれいさっぱり消えているし、また、冒険とか友情とか熱血とかガキ大将などの言葉に託されるようないかにもの少年時代も登場せず、まるで夏休みの宿題の朝顔の観察絵日記のように子供の頃のごくありふれた行動と心の動きが淡々と描かれている。
たとえば家の近くの坂道の街灯を大人より先に点灯した時のよろこび。
そのためには、日没(にちぼつ)ちょっと前には、街灯の下にスタンバイしていないといけない。ただそこにいるのは、なんとなく〈我ながら不自然〉と思うから、街灯下でスタンバる時は、グラブとなんきゅうを持っていって道の反対側の鈴木さんちの石塀(いしべい)にそれをぶつけて、キャッチボールとピッチングの練習をしているというスタイルにしたんでした。
近所のサンキュー食堂がバーに改造された時のこと、
食堂の前は砂利置場になっていて、ボクらはその空き地で、三角ベースをよくしていましたが、まだ明るい三時か四時ころに、黒いドレスを着た、でもまだお化粧(けしょう)前のおねえさんが、お店の掃除(そうじ)をしたりするので、“バーのなかみ”がちょっと見えたのです。外は明るくても、窓のない『トリスバー39』の店内は、いつも夜になっています。ちょうど青空に四角い夜の穴があいているような、それは不思議な景色なんでした。……ねえさんは、モップで床をふいています。頭にはパーマネントにする、サメの口のような金具をいっぱいつけてます。
そのほか、男の子なら誰でも記憶のある道端で拾った物を集める話(なお、女の子にはこうした収集癖はないという路上観察学の学説がある)をはじめ、「音楽が苦手だった」「ヘンなオジサン」「原田くんのずる休み」「ガラスの割れた日」「掃除当番」、とテーマの一部を並べれば、本の方向は分かると思う。
こうしたありふれたテーマについて淡々と正確に書かれているから、読む人は“ああ自分も子供の頃は……”と、ほのかに熱い思いを呼び醒(さ)まされるのである。もしファーブルが少年記を書いていれば似た質のものになっていたかもしれない。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする