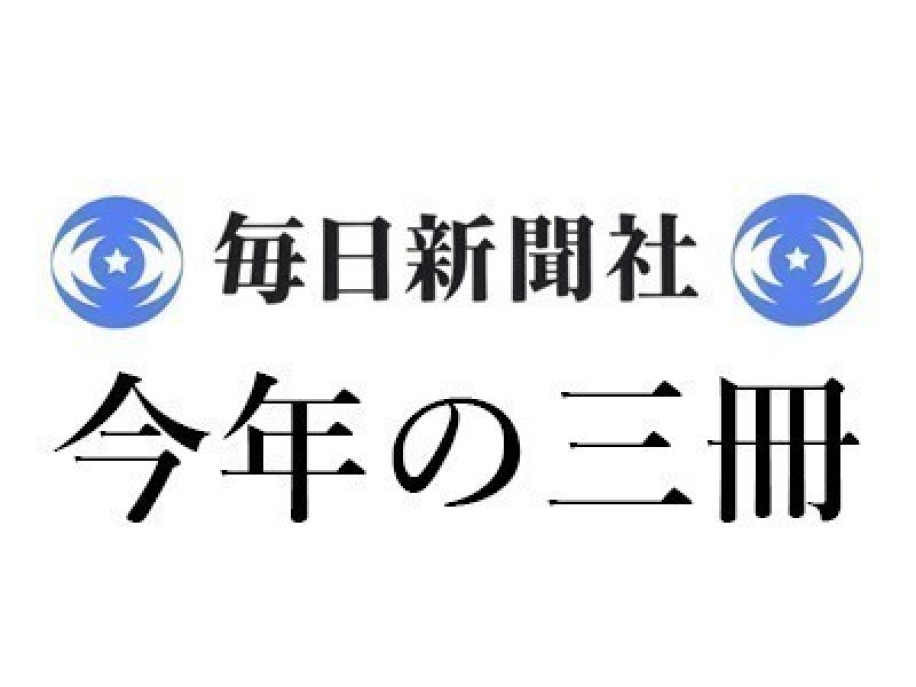書評
『恐怖時代』(中央公論新社)
ウニだのイクラだのキャビアだの、へんな、しつこい味のするものが好きである。もったいぶった値段がついているのも、正しい。ああいうものはほんの少量をごたいそうにまさに舌なめずりする感じで食べるべきもので、食べ過ぎると気持悪くなるものだ——ということを、私はこの夏の北海道旅行で二日間ほど狂喜してウニ丼を食べ続けて思い知ったのだった。
谷崎潤一郎は私にとってウニ丼みたいな存在だ。実家に『谷崎潤一郎全集』(全三十巻。昭和三十三年の中央公論社版。クロス貼りの装丁は棟方志功だが、全然土くさくなく瀟洒(しょうしゃ)な感じのものである)があって、実家にいたときから今に至るまで、もう何十年も(三十年くらいだろうか)かけてちびちびと読んで楽しんでいるばかりで、一気にガーッとまとめて読破するということはしていない。たった一巻でも通して読むと、何となくグッタリしてしまうのだもの。何か、あの濃厚な世界にこちらの活力を吸い取られたような気分になってしまうのだもの。それはウニ丼を食べ過ぎたときのゲンナリ感と、かなり似ている。
先日、昔読んで印象に残っていた『恐怖時代』という戯曲を読み直してみたが……いやー、やっぱり凄いわ。しつこいわ。
ヒロインはお銀の方という、芸者から春藤家の殿に目をかけられて愛妾(あいしょう)になった女で、いうまでもなく悪女です。これに梅野という、器量はたいしたことがないが悪智恵にたけた年増の女中がついている。
お銀の方は殿の寵愛を受ける身でありながら、古いなじみの家老・春藤靫負(ゆげい)とも通じている。これがまずまずの色男だが「奸譎(かんけつ)なる佞臣(ねいしん)」で、共謀して春藤家を乗っ取ろうとたくらんでいる。お銀の方は、これも古くからのなじみだった春藤家の医者の細井玄澤を色じかけでだまし、毒薬を手に入れ、臆病者のお茶坊主・珍齋をつかって、奥方を毒殺しようとする。
これに梅野の年下の愛人で磯貝伊織之介というのが絡むのだが、これがまた「前髪姿の、国貞流のうら若い妖艶な美男子で、女のやうな優しい口の利き方をする癖のあるのが、何となく油断のならない、狡猾らしい感じを与へる。袴も着物も派手でなまめかしくて、女性的の優雅と奸譎と、男性的の智慮と豪胆(ごうたん)とが巧みに織り交ぜられた人間である事を想像させる」というキャラクターである。
ようするにお茶坊主の珍齋(と、その娘のお由良)以外はみんな、底の知れない、色欲に迷ったワルである。お銀の方が、周囲の人間を(腹心の梅野までも)二重三重にだましていて、次々と殺してゆく——その目まぐるしさには呆気にとられてしまう。ひとことで言うと「派手」。
次々と殺される人物たちの死にざまも凄い。「ザツ、ザツと二度ばかり恐ろしく多量な血潮がはねかゝつて、花火のやうにバツとひろがつて流れ落ちる」というありさまだったり、「後ろから脳天の骨を横に殺がれる。髪の毛と頭葢の生皮が剝ぎ落されて、真赤な、むごたらしい坊主頭になる」という、ほとんど筒井康隆というかマンガ的状況だったり。やっぱり、ひとことで言うと「派手」である。
こういう描写を見ると、谷崎潤一郎は歌舞伎が好きでたまらなかった人なんだなあ、とつくづく思う。そもそも、この物語自体が鶴屋南北の悪女ものの芝居と地続きだが、この死にざまの派手さやショー的な大胆さも歌舞伎のセンスそのままだと思う。
たとえば、歌舞伎の『暫(しばらく)』では、主人公が大太刀を抜いて、仕丁(じちょう)たちの首を一度にサーッと切り落とす場面がある。小道具の首(血を示す赤い布のついた簡単素朴なつくりの首)が連なって切り落とされるところは、まるで生々しさはなくて、「むごたらしい」だの「かわいそう」だのというより、何と言うか、笑っちゃうくらい「派手」で、「景気がいい」という感じがする。谷崎潤一郎にはそういう歌舞伎の心があって、血だの死だのを、厳粛なものとしてではなく一種、華美なものとして描き出している。
後半に登場する殿様の狂い方も「派手」だ。死体をそのままにしているのでは面白くない、「喉頸を、真直ぐ畳まで突き通してしまへ」などと言って楽しんでいるのだもの。
そういう人並はずれて濃い何かを持った人物たちが、次々とだまし合い、死んでゆく。最後には一番の悪党のお銀の方と伊織之介まで、いささかの迷いもなく、刺し違えて死んでゆく。その「生」の消費ぶりは、啞然とするほど「派手」である。
悪女と見えたお銀の方も最後は惚れた男と心中するのだから、実は純情いちずの女だったと言えなくもないが、谷崎潤一郎はそういう「女の哀れ」をほのめかすことには全然力点を置いていないようだ。あくまでも強欲な女——その欲望のあくどさと確かさが、凡人にはまぶしく思える——として描いているところが好もしい。
この『恐怖時代』は、浅丘ルリ子主演で上演された。コッテリとした美貌の浅丘ルリ子=お銀の方というのは適役だった。歌舞伎でも玉三郎=お銀の方で上演されている。
【この書評が収録されている書籍】
谷崎潤一郎は私にとってウニ丼みたいな存在だ。実家に『谷崎潤一郎全集』(全三十巻。昭和三十三年の中央公論社版。クロス貼りの装丁は棟方志功だが、全然土くさくなく瀟洒(しょうしゃ)な感じのものである)があって、実家にいたときから今に至るまで、もう何十年も(三十年くらいだろうか)かけてちびちびと読んで楽しんでいるばかりで、一気にガーッとまとめて読破するということはしていない。たった一巻でも通して読むと、何となくグッタリしてしまうのだもの。何か、あの濃厚な世界にこちらの活力を吸い取られたような気分になってしまうのだもの。それはウニ丼を食べ過ぎたときのゲンナリ感と、かなり似ている。
先日、昔読んで印象に残っていた『恐怖時代』という戯曲を読み直してみたが……いやー、やっぱり凄いわ。しつこいわ。
ヒロインはお銀の方という、芸者から春藤家の殿に目をかけられて愛妾(あいしょう)になった女で、いうまでもなく悪女です。これに梅野という、器量はたいしたことがないが悪智恵にたけた年増の女中がついている。
お銀の方は殿の寵愛を受ける身でありながら、古いなじみの家老・春藤靫負(ゆげい)とも通じている。これがまずまずの色男だが「奸譎(かんけつ)なる佞臣(ねいしん)」で、共謀して春藤家を乗っ取ろうとたくらんでいる。お銀の方は、これも古くからのなじみだった春藤家の医者の細井玄澤を色じかけでだまし、毒薬を手に入れ、臆病者のお茶坊主・珍齋をつかって、奥方を毒殺しようとする。
これに梅野の年下の愛人で磯貝伊織之介というのが絡むのだが、これがまた「前髪姿の、国貞流のうら若い妖艶な美男子で、女のやうな優しい口の利き方をする癖のあるのが、何となく油断のならない、狡猾らしい感じを与へる。袴も着物も派手でなまめかしくて、女性的の優雅と奸譎と、男性的の智慮と豪胆(ごうたん)とが巧みに織り交ぜられた人間である事を想像させる」というキャラクターである。
ようするにお茶坊主の珍齋(と、その娘のお由良)以外はみんな、底の知れない、色欲に迷ったワルである。お銀の方が、周囲の人間を(腹心の梅野までも)二重三重にだましていて、次々と殺してゆく——その目まぐるしさには呆気にとられてしまう。ひとことで言うと「派手」。
次々と殺される人物たちの死にざまも凄い。「ザツ、ザツと二度ばかり恐ろしく多量な血潮がはねかゝつて、花火のやうにバツとひろがつて流れ落ちる」というありさまだったり、「後ろから脳天の骨を横に殺がれる。髪の毛と頭葢の生皮が剝ぎ落されて、真赤な、むごたらしい坊主頭になる」という、ほとんど筒井康隆というかマンガ的状況だったり。やっぱり、ひとことで言うと「派手」である。
こういう描写を見ると、谷崎潤一郎は歌舞伎が好きでたまらなかった人なんだなあ、とつくづく思う。そもそも、この物語自体が鶴屋南北の悪女ものの芝居と地続きだが、この死にざまの派手さやショー的な大胆さも歌舞伎のセンスそのままだと思う。
たとえば、歌舞伎の『暫(しばらく)』では、主人公が大太刀を抜いて、仕丁(じちょう)たちの首を一度にサーッと切り落とす場面がある。小道具の首(血を示す赤い布のついた簡単素朴なつくりの首)が連なって切り落とされるところは、まるで生々しさはなくて、「むごたらしい」だの「かわいそう」だのというより、何と言うか、笑っちゃうくらい「派手」で、「景気がいい」という感じがする。谷崎潤一郎にはそういう歌舞伎の心があって、血だの死だのを、厳粛なものとしてではなく一種、華美なものとして描き出している。
後半に登場する殿様の狂い方も「派手」だ。死体をそのままにしているのでは面白くない、「喉頸を、真直ぐ畳まで突き通してしまへ」などと言って楽しんでいるのだもの。
そういう人並はずれて濃い何かを持った人物たちが、次々とだまし合い、死んでゆく。最後には一番の悪党のお銀の方と伊織之介まで、いささかの迷いもなく、刺し違えて死んでゆく。その「生」の消費ぶりは、啞然とするほど「派手」である。
悪女と見えたお銀の方も最後は惚れた男と心中するのだから、実は純情いちずの女だったと言えなくもないが、谷崎潤一郎はそういう「女の哀れ」をほのめかすことには全然力点を置いていないようだ。あくまでも強欲な女——その欲望のあくどさと確かさが、凡人にはまぶしく思える——として描いているところが好もしい。
この『恐怖時代』は、浅丘ルリ子主演で上演された。コッテリとした美貌の浅丘ルリ子=お銀の方というのは適役だった。歌舞伎でも玉三郎=お銀の方で上演されている。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア

月刊Asahi(終刊) 1993年11月号
ALL REVIEWSをフォローする