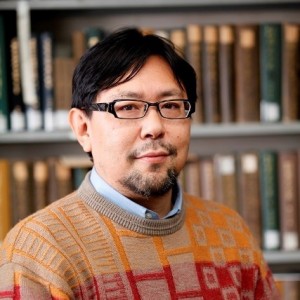書評
『空襲で消えた「戦国」の城と財宝』(平凡社)
失われたものの尊さに改めて思いを馳せる
尾崎士郎に関ケ原の戦いを描いた『篝火(かがりび)』という小説があって、尾崎が大垣城(三成方が本営を置いた)の天守閣を訪れたときに、子ども用の甲冑を見たことから書き始められている。子ども用の甲冑というのは珍しい、と記憶に残っていたので、仕事で大垣に赴いたときにお城に寄り道し、博物館になっている天守閣の学芸員の方に甲冑のことを質問してみた。ところが彼女は、そうしたものは記憶にない、という。『篝火』のことを話すと、ありがたいことに収蔵品の台帳をめくって調べてくださったが、やはりデータはない。あれ? 作品の冒頭は自身の体験として描かれていたが、あれもフィクションだったのかな?
だが、帰りの新幹線の中でやっと気付いた。ぼくが読んだ『篝火』は光文社の文庫で平成2年刊。スマホで調べたら、小説自体は戦前に櫻井書店から出版されている。たしか大垣城天守閣は戦災に遭っているはずだ。また調べると、昭和20年7月29日の空襲で、4重4階の立派な天守閣(国宝)は焼け落ちた。現在の建物は14年後に再建されたもの。とすると尾崎は消失以前の天守閣に足を運んでいるわけで、甲冑も天守閣もろとも焼けたのではないか。
本書は空襲により失われた城と文化財をまとめたものである。貴重な写真が多数収録されていて、まことに興味深い。また空襲被害がまとめられているが、その大多数は昭和20年のものである。19年時点では戦争の敗北は不可避の状態となっていて、それでも政府・軍部が戦いをやめなかったために多くの命が失われたという。文化財も同じだったのだ。本当に、本当に惜しい。戦争を起こしては、絶対にダメだ。もうすぐめぐってくる終戦記念日の前に、ぜひ目を通したい本である。
ALL REVIEWSをフォローする