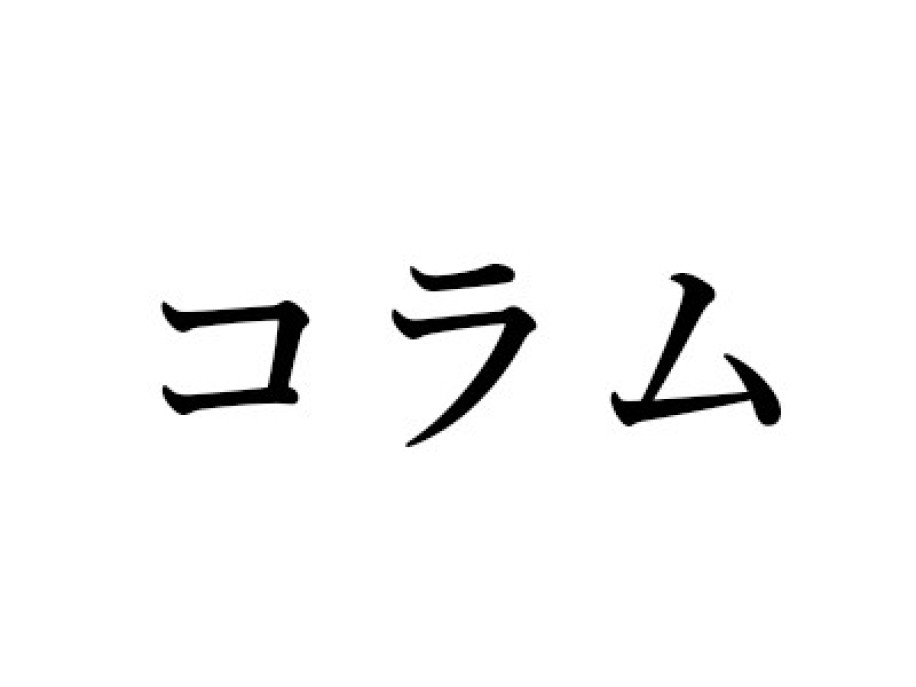書評
『ベストセラーの方程式』(筑摩書房)
本を売る側の意見
書評もふくめて送り手分析は多いけれど、読者論のような受け手分析は少ない。井狩春男『ベストセラーの方程式』(ブロンズ新社)は取次に勤める立場で売れる本の条件を分析した本で、送り手、受け手とその仲介者の関係がなかなかよく見えて面白い。「女性が買うとベストセラーになる」「ベストセラーの値段は千円前後」「新刊が出るたびに著者の最初の本が売れる」「イヌの本よりネコの本の方が売れる」などフーム、なるほどの話はまだまだある。
吉本ばななの小説が売れたとき、読者の十~二十代の女性は吉本隆明を知らなかったから、これは親の七光り本とはいえないが、マスコミ人には隆明氏の読者が多く、記事になりやすかったかもしれないという指摘は、あまり上品な見方ではないがスルドイ。圧巻は第百回芥川賞・直木賞を「商売として賞が設けられている」と仮定して推理して、見事ダブル受賞の四人を当ててしまうくだり。「もちろん選考委員のみなさんは内容で選ばれていることは書くまでもない」というオチが楽しめた。
それから「書評委員は偉い方々がほとんどで若い人が少ない」「大新聞はガチガチのスキのない論文みたいな書評がほとんど」という指摘は書評の末席に連なる者として考えさせられた。
私自身は書評委員会に出るようになって「思ったより時間をかけてフェアに本を選んでいるんだ」という印象だけど、やはり限られたスペースだから「今年の労作」をきちんと「批評」するという構えになりやすく、何百万人もの読者の興味からかけ離れやすいのも確か。面白いと思った本を、もっと気楽に、読みたくなるように取り上げてみたいと鋭意努力中です。
「売ることについて書くと志派の良書出版人に非難を受けそうだが」と著者は控え目に断っているが、必要な本を必要な読者に届けるという一点に立って、地道な少部数の本やミニコミへの理解をふくめ、本へのスタンスははっきりしている。
ところで、「内容の暗い本は装幀くらい明るく」「8ポでビッチリはサービスしたつもりでも読者は喜ばない」といった有益なプロの指摘に「志派の良心的出版社」こそ耳を傾けるべきだろう。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする