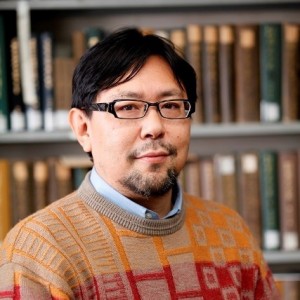書評
『家康謀殺』(KADOKAWA)
作家の想像力と観察力で戦国の世を活写する
信長・秀吉・家康の周囲に着想を得た6本の物語が並ぶ。そのどれもが真正面から時代に取り組む、堂々たる読み物に仕上がっている。奇をてらう行動とか、常識はずれの武勇とか、そういうものは不要。等身大の人間が、一生懸命に生きる。すると時に一個人たる彼は巨大な権力への異議申し立てに成功したり、時代の変革に参加できたりする。人間の精神や心理、社会状況を知り尽くした著者だからこそ、時代を活写できる。2本目の「上意に候」の主人公は豊臣秀次(秀吉の甥(おい))。関白の地位を譲り受け、一応豊臣政権の後継候補となっていた秀次だが、お拾(すて)(のちの秀頼)が生まれてしまった。さあ、どうする? 人は誰しも実の子がかわいい。権力を譲りたい。秀吉は専制君主であり、対応を間違えば破滅が待っている。関白を辞するか否か。秀次は思い悩む。
秀次について、最近ある研究者が独自の解釈を示した。秀吉は秀次に自害させる気はなかった。積極的な史料がないのが証拠だ。豊臣家の血を引く男子は少なく貴重だから、秀吉が秀次を滅ぼすはずがない……。この研究者はそう力説する。私は頭を抱えた。血が近ければ近いほど、後継者にとってその人は危険である。だから古今東西、権力者が後継者のライバルたり得る人物を排除する例は腐るほどある。なぜそんな簡単なことをこの研究者は分からないのか。史料の欠如を考察や経験で補ってこその歴史的考察だろうに。
これに対し、著者はさすがの一言。この最新の研究成果を取り込みながら(実に勉強熱心なのだ)、読者に十分に説得力ある歴史像を描いてみせる。優秀な小説家の想像力と観察力は、視野の狭い歴史研究者を易々(やすやす)と超えていく。のりにのる伊東潤からは、目を離せそうにない。
ALL REVIEWSをフォローする