書評
『周作人随筆』(冨山房)
小学校でも英語教育をすべきではないかという声があり、近頃、論議をよんでいるらしい。実利的に見ればそれも結構と思えるが、教える先生の英語力が大いに問題だ。今のシステムのままでは、いたずらに英語嫌いを増やすだけのような気がする。
小学校の教育カリキュラムにそんなゆとりがあるのなら、私はむしろ漢文教育に力を入れていただきたいと思う。実利的にはたいした意義はないだろうが、文化的には数段意義のあることだと思う。
少なくとも私は戦後教育の中で育ったがために漢文系の素養がまったくないことに、今、苦しんでいる。残念に思っている。漱石にしても鷗外にしても、昔(大ざっぱに言うなら戦前まで)の教養人は当たり前のこととして漢籍に親しんでいたのが、戦後プッツリとその伝統が断たれた。私は白文(はくぶん)を読みこなせない。漢字が並んでいるだけでげんなりだ。高校時代、大学受験とは関係のない選択科目だった「漢文」の時間に居眠りしていたのが悔やまれる。
そういうわけで、私は中国文学にも中国にも全然興味がない。いや中国料理にしか興味がない。
しかし、戦後生まれの同世代=いわゆる「団塊の世代」でも男の人たちはちょっと違うようだ。「最近、『三国志』にのめり込んじゃって……」「実は僕も……」などと言って、千七百年だか何だか昔のお話を夢中になってしゃべっていたりする。不思議。
ある日、『周作人随筆』(松枝茂夫訳、冨山房百科文庫)という本が送られてきた(私は書評の仕事もしているので、時どき出版社から新刊書が送られてくるのだ。最初、パッと見たとき『周作随筆』と読んでしまい、「なぜ私に遠藤周作のエッセーの本が?!」と軽く驚いてしまった……)。
周作人という人のことはまったく知らなかった。中国近代文学では有名な(一番有名かもしれない)魯迅の弟だという。
興味ないなあと思いながら、目次を見て、少しばかり面白そうなタイトルのついたものだけ読んでみることにしたが……あらあらあら、面白いんだわ、これが。福田恆存を思わせる、バランスのいい思索的なエッセー集である。中でもこの人の思想的体質が最もよく出ていると思われるのは「生活の芸術」と題された一編だ。
周作人はこの短いエッセーの中で、快楽の、幸福の、美しい生活(=周作人の言葉では、生活の芸術化)の極意を語っている。
彼はまず、中国人の酒の飲み方から話を始める。中国人は一口ずつちびりちびりと酒の味をよく味わいながら綴るが、これは「中国にわずかに残っている飲酒の芸術」であるが、一般的にはそういう「生活の芸術は、とうの昔に絶えてしまった」。「中国の生活の方式は、今はただ両極端のみだ。禁欲でなければ縦欲(しょうよく)、酒という字を口にすることすら許さないのでなければ酒槽(さかふね)にとっぷり身を浸す。この二者が互いに相反動し、各々ますます増長して、そしてその結果は、ただ前と同じめちゃくちゃだ」と嘆き、「生活の芸術はただ禁欲と縦欲との調和にある」と断言するのだ。
快楽、幸福、美しい生活の極意は、「禁欲と耽溺」、あるいは「節制と自由」、またあるいは「抑圧と放恣(ほうし)」――相反する両者のバランスの中にあると言うのだ。つまり……「中庸」ということだろう。
まったく、その通りじゃないか。私も長年(でもないか)生きてきたけれど、実感的にその通りだと思う。「中庸」ということの貴重さ、困難さ、美しさを痛感するようになった。
周作人によると、「生活の芸術という言葉は、中国固有の字を用いて言えば、つまりいわゆる礼である」。礼=Artだと言うのである。後世では形骸化してしまったが、「礼」とは本来そういうものだったと言うのである。
ふうん、そうだったのか。そういう意味の「礼」だったら、セレモニー嫌いで儀礼嫌いの私にもわかる。すんなり受け入れられる。「礼」といい「中庸」といい、堅苦しく身構えた人の口から発せられると、「ふん、うるさい!」としか思えないが、この周作人のエッセーには、堅苦しく威嚇的なところは全然ない。上っつらの瑣末なことに惑わされず、ズバッと物事の核心をつかんでいる人――つまり(語の厳密な意味においての)明晰な人特有ののびのびした感じがある。静かに、のびのび。
このエッセーで言われていることは、実のところ、とくに目新しいことではないと思う。日本でも人生論(というより処世術か)好きのおやじライターが言いそうなことだと思う。しかし、どこかハッキリと「品格」が遠う。せこい処世テクニックではなくて、もっと大きく、人間という生きものの真実について語っている、という感じが確かにある。
古今東西の文化にかんするうんちくを傾けながら、論を進めるのだが、その引用の仕方がまことに適切で、「この人はライターというよりエディター的才能に恵まれた人なのではないか?」と思われる。
「日本文化を語る書簡」「東京を懐(おも)う」「冬の蝿」と題されたエッセーもたいへん面白い。
周作人は、一九〇六年(明治三十九年)以来、六年間の日本留学生活をおくっている。
「冬の蝿」というエッセーでは当時の新刊として谷崎潤一郎の『摂陽随筆』と、永井荷風の『冬の蝿』を読み、江戸時代の横井也有の名まで引き合いに出しながら、「谷崎・永井両氏の書くものは俳文ではない。だが随筆としてきわめて立派なものであって、現代の俳諧師の遠く及ぶところではない」うんぬんと讃辞をおくっている。
「私が東京に続けて暮したのはわずか六年である。しかし私はあそこを愛好し、第二の故郷の感を抱いている」と言いきる周作人は、日本の、いや東京の生活文化(衣・食・住)の魅力の一番のポイントを「清淡質素」という言葉で表現している。
私も日本の美意識の最もすぐれた部分というか、独創的な部分は、金持階級が生み出したものではない、中流庶民の生み出したものであって、貧乏の芸術化=「簡素の美」の中にあると思っていたので、「わが意を得たり!」とうれしくなってしまう。何十年も昔の、それも中国の人がこの私と同じようなことを感じていた――というのが、うれしい。時空を超えた共感。「活字の力」を思い知る。
エッセー集の最後のほうは、兄・魯迅についての話だ。私は高校時代に『阿Q正伝』を読んだが、すっかり忘れているので、まず魯迅をちゃんと読んでからと思い、今回は魯迅論部分は読まずじまい。ごめんなさい。
【この書評が収録されている書籍】
小学校の教育カリキュラムにそんなゆとりがあるのなら、私はむしろ漢文教育に力を入れていただきたいと思う。実利的にはたいした意義はないだろうが、文化的には数段意義のあることだと思う。
少なくとも私は戦後教育の中で育ったがために漢文系の素養がまったくないことに、今、苦しんでいる。残念に思っている。漱石にしても鷗外にしても、昔(大ざっぱに言うなら戦前まで)の教養人は当たり前のこととして漢籍に親しんでいたのが、戦後プッツリとその伝統が断たれた。私は白文(はくぶん)を読みこなせない。漢字が並んでいるだけでげんなりだ。高校時代、大学受験とは関係のない選択科目だった「漢文」の時間に居眠りしていたのが悔やまれる。
そういうわけで、私は中国文学にも中国にも全然興味がない。いや中国料理にしか興味がない。
しかし、戦後生まれの同世代=いわゆる「団塊の世代」でも男の人たちはちょっと違うようだ。「最近、『三国志』にのめり込んじゃって……」「実は僕も……」などと言って、千七百年だか何だか昔のお話を夢中になってしゃべっていたりする。不思議。
ある日、『周作人随筆』(松枝茂夫訳、冨山房百科文庫)という本が送られてきた(私は書評の仕事もしているので、時どき出版社から新刊書が送られてくるのだ。最初、パッと見たとき『周作随筆』と読んでしまい、「なぜ私に遠藤周作のエッセーの本が?!」と軽く驚いてしまった……)。
周作人という人のことはまったく知らなかった。中国近代文学では有名な(一番有名かもしれない)魯迅の弟だという。
興味ないなあと思いながら、目次を見て、少しばかり面白そうなタイトルのついたものだけ読んでみることにしたが……あらあらあら、面白いんだわ、これが。福田恆存を思わせる、バランスのいい思索的なエッセー集である。中でもこの人の思想的体質が最もよく出ていると思われるのは「生活の芸術」と題された一編だ。
周作人はこの短いエッセーの中で、快楽の、幸福の、美しい生活(=周作人の言葉では、生活の芸術化)の極意を語っている。
彼はまず、中国人の酒の飲み方から話を始める。中国人は一口ずつちびりちびりと酒の味をよく味わいながら綴るが、これは「中国にわずかに残っている飲酒の芸術」であるが、一般的にはそういう「生活の芸術は、とうの昔に絶えてしまった」。「中国の生活の方式は、今はただ両極端のみだ。禁欲でなければ縦欲(しょうよく)、酒という字を口にすることすら許さないのでなければ酒槽(さかふね)にとっぷり身を浸す。この二者が互いに相反動し、各々ますます増長して、そしてその結果は、ただ前と同じめちゃくちゃだ」と嘆き、「生活の芸術はただ禁欲と縦欲との調和にある」と断言するのだ。
快楽、幸福、美しい生活の極意は、「禁欲と耽溺」、あるいは「節制と自由」、またあるいは「抑圧と放恣(ほうし)」――相反する両者のバランスの中にあると言うのだ。つまり……「中庸」ということだろう。
まったく、その通りじゃないか。私も長年(でもないか)生きてきたけれど、実感的にその通りだと思う。「中庸」ということの貴重さ、困難さ、美しさを痛感するようになった。
周作人によると、「生活の芸術という言葉は、中国固有の字を用いて言えば、つまりいわゆる礼である」。礼=Artだと言うのである。後世では形骸化してしまったが、「礼」とは本来そういうものだったと言うのである。
ふうん、そうだったのか。そういう意味の「礼」だったら、セレモニー嫌いで儀礼嫌いの私にもわかる。すんなり受け入れられる。「礼」といい「中庸」といい、堅苦しく身構えた人の口から発せられると、「ふん、うるさい!」としか思えないが、この周作人のエッセーには、堅苦しく威嚇的なところは全然ない。上っつらの瑣末なことに惑わされず、ズバッと物事の核心をつかんでいる人――つまり(語の厳密な意味においての)明晰な人特有ののびのびした感じがある。静かに、のびのび。
このエッセーで言われていることは、実のところ、とくに目新しいことではないと思う。日本でも人生論(というより処世術か)好きのおやじライターが言いそうなことだと思う。しかし、どこかハッキリと「品格」が遠う。せこい処世テクニックではなくて、もっと大きく、人間という生きものの真実について語っている、という感じが確かにある。
古今東西の文化にかんするうんちくを傾けながら、論を進めるのだが、その引用の仕方がまことに適切で、「この人はライターというよりエディター的才能に恵まれた人なのではないか?」と思われる。
「日本文化を語る書簡」「東京を懐(おも)う」「冬の蝿」と題されたエッセーもたいへん面白い。
周作人は、一九〇六年(明治三十九年)以来、六年間の日本留学生活をおくっている。
「冬の蝿」というエッセーでは当時の新刊として谷崎潤一郎の『摂陽随筆』と、永井荷風の『冬の蝿』を読み、江戸時代の横井也有の名まで引き合いに出しながら、「谷崎・永井両氏の書くものは俳文ではない。だが随筆としてきわめて立派なものであって、現代の俳諧師の遠く及ぶところではない」うんぬんと讃辞をおくっている。
「私が東京に続けて暮したのはわずか六年である。しかし私はあそこを愛好し、第二の故郷の感を抱いている」と言いきる周作人は、日本の、いや東京の生活文化(衣・食・住)の魅力の一番のポイントを「清淡質素」という言葉で表現している。
私も日本の美意識の最もすぐれた部分というか、独創的な部分は、金持階級が生み出したものではない、中流庶民の生み出したものであって、貧乏の芸術化=「簡素の美」の中にあると思っていたので、「わが意を得たり!」とうれしくなってしまう。何十年も昔の、それも中国の人がこの私と同じようなことを感じていた――というのが、うれしい。時空を超えた共感。「活字の力」を思い知る。
エッセー集の最後のほうは、兄・魯迅についての話だ。私は高校時代に『阿Q正伝』を読んだが、すっかり忘れているので、まず魯迅をちゃんと読んでからと思い、今回は魯迅論部分は読まずじまい。ごめんなさい。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
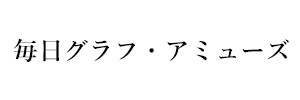
毎日グラフ・アミューズ(終刊) 1995年3月8日号~1997年1月8日号
ALL REVIEWSをフォローする








































