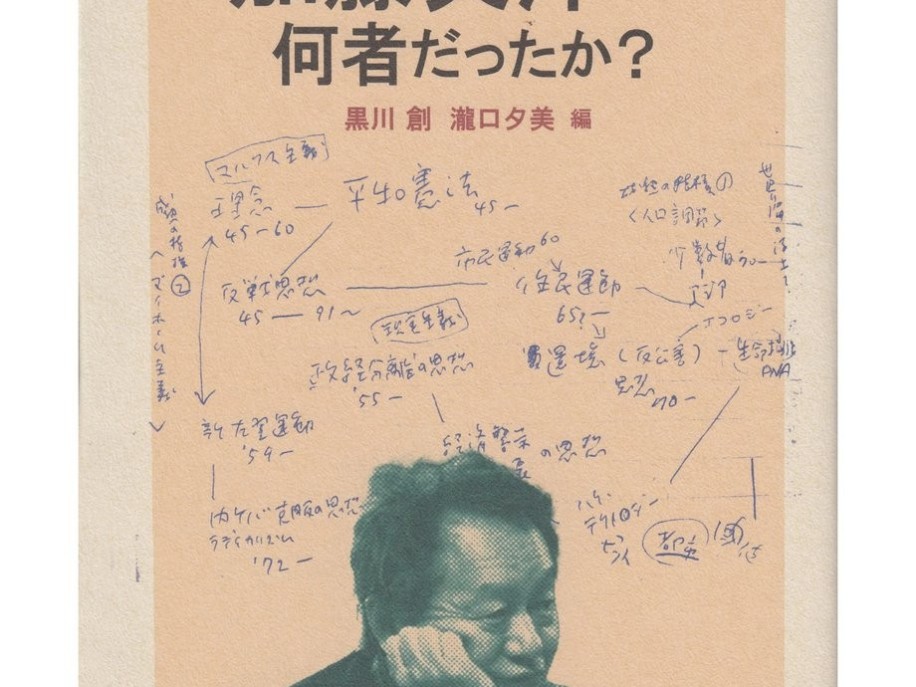書評
『御馳走帖』(中央公論社)
一九九六年も終わろうとしている。私が今年読んだ本の中で質量ともに一番圧倒されたのは、『古川ロッパ昭和日記』(全四巻、晶文社)だった。
古川ロッパはもともと映画評論家、映画雑誌編集者としてスタートした人で、本質的には芸能人というよりもジャーナリストだったと思う。徳川夢声と同様に文学への憧れが強く、生涯、作家への夢を捨てられなかった。谷崎潤一郎に心酔していて、公私にわたって親交があった。
気難しくわがままな性格と肥満ぎみの風貌(ふうぼう)から内田百閒を連想しながら読んでいたら、実際、ロッパは百閒の本を読んでいて、昭和十四年には有楽座の舞台で百閒を演じていたのだった(内田百閒原作 伊藤松雄脚色「百鬼園先生」)。ロッパと百閒、両方に興味のある私としては、タイムスリップできたら、ぜひともこの舞台は見たいものだと思う。
昭和十四年三月三十一日、ロッパは「百鬼園先生」の舞台稽古を見にやってきた百閒と初めて顔を合わせている。その第一印象は、「ヌウッと部屋へ入って来たオットセイの標本みたいなのが“私が内田百閒です”成程変っている」「内田先生づっと見てるので、弱った」。
無愛想に威張った顔をしながら、内心興味津々だったに違いない百閒の様子が目に浮かぶ。当時、百閒四十九歳か。
百閒の食べものエッセー集『御馳走帖』の中公文庫版が、改版されて新しく出ていたので、読んでみた。
食べものエッセーと言っても、いわゆるグルメ志向のものではない。グルメ(美食家)でありグルマン(大食漢)でもあったロッパが書いた『ロッパの悲食記』(ちくま文庫)とはちょっと違う。林檎(りんご)、沢庵(たくあん)、おからなど身近な、ふだんの食べものの話が中心である。うれしいことには「油揚の焼いたの」まで出てくる。
実は私も……。買物の暇がなくて、おかずに困ったときは、この「油揚の焼いたの」でしのぐ。何だか貧乏くさく、ひとにはあんまり言えない感じがしていたが、百閒もお気に入りとはうれしいじゃないか。
そうだ……。ここで急に思い出してしまったが、子どもの頃「たけのこの皮の三角」というのを母が作って、おやつ代わりに食べさせられた記憶がある。たけのこの内側のほうのケバ立ってない皮に、種を取った梅干を入れて、三角に包んだものをしゃぶる。かすかに香りのある皮から梅の酸っぱさがしみ出して、私の好物だったのだけれど……うーん……何だかこれも貧乏くさくて、胸を張って口外はできないタイプのものだった……。
題材になっている食べもの自体はどうってことはないのだが、食べ方のほうがおかしくて、短いエッセーを次から次へと読み進んでしまう。読まされてしまう。どうも百閒という人物の、妙な生理から来る妙な流儀に引きずられて、読まされてしまうようなのだ。
その妙な流儀というのが一番はっきりと語られているのが「饗応」と題されたエッセーだ。
ひとの家を訪ねた百閒は、用談がすんだので帰ろうとすると奥さんがビールをお盆に載せて入って来た。百閒は「しまつたと思つて途方に暮れた」。なぜなら「自分のおなかの中の順序に、外部から干渉されるのが、いや」だから。
ビールのあとに鰻丼(うなどん)が出てくる。百閒は「このお蔭で今晩の食膳が、どんなに不味(まず)くなるかと考へると、先づ以て憂鬱になる」。「むつとした気持で、鰻丼に箸をつけると、因果な事に案外うまかつたりして、一粒も残さず食べてしまつた後では、おなかが苦しくなつて、頭は鬱陶しく、麦酒と一緒にふくれるものだから胸がどきどきし出す。だからこちらの欲せざる時に、外の時なら欲しさうな物を、先方の思ひつきで、勝手に人の前に供せられては、困るのである」。
ひとにごちそうになって、しかもそれをうまいうまいときれいに平らげたうえで、(「因果な事に案外うまかつたりして」という所が私にはすごくおかしい)、困ったものだと怨(うら)んでいるのだ。ずうずうしいようだが、彼の中ではちゃんと理屈の筋道は通っている。通りすぎていたりする。しかし、世間一般の流儀とはいささかズレている。
「林檎」と題されたエッセーもおかしい。停留場前の果物屋で林檎を買おうとしたら、七銭のものから十五銭のものまでいろいろある。そこで百閒は値段によって林檎の味がどう違うか食べ比べてみようと思い、値段ごとに一個ずつ買うことにする。
店員が面倒がってしぶしぶ一個ずつ取ってくれたが、それを集めたら、どれがいくらのものだったかわからなくなってしまった。いちいち値段を店員に確認し、一つ一つの林檎に値段を書き込もうとして、「ちよつと筆を貸してくれませんか」と頼む。
そこに至るまで面倒なことをさせられていた店員は、ついにキレる。「人の店に這入つて来て、変な事をするのは止めて貰いませう」。百閒もキレる。「いきなり、ぷいと店を出てむしやくしやしながら、道を歩いた」。
百閒はしつこい。それだけでは腹の虫が収まらず、「到頭その店の主人に宛てて、名前は解らないけれども、屋号を知つてゐるから、手紙を書いて、不都合をなじつた」。
いつも利用している電車の停留場の前にある果物屋である。「私の方は、そのお蔭で電車の乗り降りの度に、いつ迄も気づまりな思ひをした」。
こういう話がちょろちょろ出てくるので、つい、読まされてしまうのである。私は百閒のちょっと毛色の変わった腹の虫(=生理)というのが好きなのだが、どうも、百閒自身、それをちょっと読んでいるようなところもあるなあ、80パーセントはやむにやまれぬ腹の虫なのだが20パーセントは衒(てら)ったところもあるなあ。そこがまたわがままお坊ちゃんらしくてかわいいんだけどね……と思う。
今回はどうも感想文と言うよりも紹介文のようになってしまった。ついでにもう一つ、紹介。百閒が「若い頃取り止めもない憂悶になやんでゐた当時」の話。「倉庫ぐらゐある大きな消し護謨(ゴム)に嚙みついて、一生懸命に歯を立てる事を考へて気分が悪くなつた事がある」のだそうだ。
ロッパじゃないが、「成程変っている」。
【この書評が収録されている書籍】
古川ロッパはもともと映画評論家、映画雑誌編集者としてスタートした人で、本質的には芸能人というよりもジャーナリストだったと思う。徳川夢声と同様に文学への憧れが強く、生涯、作家への夢を捨てられなかった。谷崎潤一郎に心酔していて、公私にわたって親交があった。
気難しくわがままな性格と肥満ぎみの風貌(ふうぼう)から内田百閒を連想しながら読んでいたら、実際、ロッパは百閒の本を読んでいて、昭和十四年には有楽座の舞台で百閒を演じていたのだった(内田百閒原作 伊藤松雄脚色「百鬼園先生」)。ロッパと百閒、両方に興味のある私としては、タイムスリップできたら、ぜひともこの舞台は見たいものだと思う。
昭和十四年三月三十一日、ロッパは「百鬼園先生」の舞台稽古を見にやってきた百閒と初めて顔を合わせている。その第一印象は、「ヌウッと部屋へ入って来たオットセイの標本みたいなのが“私が内田百閒です”成程変っている」「内田先生づっと見てるので、弱った」。
無愛想に威張った顔をしながら、内心興味津々だったに違いない百閒の様子が目に浮かぶ。当時、百閒四十九歳か。
百閒の食べものエッセー集『御馳走帖』の中公文庫版が、改版されて新しく出ていたので、読んでみた。
食べものエッセーと言っても、いわゆるグルメ志向のものではない。グルメ(美食家)でありグルマン(大食漢)でもあったロッパが書いた『ロッパの悲食記』(ちくま文庫)とはちょっと違う。林檎(りんご)、沢庵(たくあん)、おからなど身近な、ふだんの食べものの話が中心である。うれしいことには「油揚の焼いたの」まで出てくる。
じゆん、じゆん、じゆんと焼けて、まだ煙の出てゐるのをお皿に移して、すぐに醬油をかけると、ばりばりと跳ねる。その味を、名前も顔も忘れた友達に教はつて、今でも私の御馳走の一つである。(「油揚」)
実は私も……。買物の暇がなくて、おかずに困ったときは、この「油揚の焼いたの」でしのぐ。何だか貧乏くさく、ひとにはあんまり言えない感じがしていたが、百閒もお気に入りとはうれしいじゃないか。
そうだ……。ここで急に思い出してしまったが、子どもの頃「たけのこの皮の三角」というのを母が作って、おやつ代わりに食べさせられた記憶がある。たけのこの内側のほうのケバ立ってない皮に、種を取った梅干を入れて、三角に包んだものをしゃぶる。かすかに香りのある皮から梅の酸っぱさがしみ出して、私の好物だったのだけれど……うーん……何だかこれも貧乏くさくて、胸を張って口外はできないタイプのものだった……。
題材になっている食べもの自体はどうってことはないのだが、食べ方のほうがおかしくて、短いエッセーを次から次へと読み進んでしまう。読まされてしまう。どうも百閒という人物の、妙な生理から来る妙な流儀に引きずられて、読まされてしまうようなのだ。
その妙な流儀というのが一番はっきりと語られているのが「饗応」と題されたエッセーだ。
ひとの家を訪ねた百閒は、用談がすんだので帰ろうとすると奥さんがビールをお盆に載せて入って来た。百閒は「しまつたと思つて途方に暮れた」。なぜなら「自分のおなかの中の順序に、外部から干渉されるのが、いや」だから。
ビールのあとに鰻丼(うなどん)が出てくる。百閒は「このお蔭で今晩の食膳が、どんなに不味(まず)くなるかと考へると、先づ以て憂鬱になる」。「むつとした気持で、鰻丼に箸をつけると、因果な事に案外うまかつたりして、一粒も残さず食べてしまつた後では、おなかが苦しくなつて、頭は鬱陶しく、麦酒と一緒にふくれるものだから胸がどきどきし出す。だからこちらの欲せざる時に、外の時なら欲しさうな物を、先方の思ひつきで、勝手に人の前に供せられては、困るのである」。
ひとにごちそうになって、しかもそれをうまいうまいときれいに平らげたうえで、(「因果な事に案外うまかつたりして」という所が私にはすごくおかしい)、困ったものだと怨(うら)んでいるのだ。ずうずうしいようだが、彼の中ではちゃんと理屈の筋道は通っている。通りすぎていたりする。しかし、世間一般の流儀とはいささかズレている。
「林檎」と題されたエッセーもおかしい。停留場前の果物屋で林檎を買おうとしたら、七銭のものから十五銭のものまでいろいろある。そこで百閒は値段によって林檎の味がどう違うか食べ比べてみようと思い、値段ごとに一個ずつ買うことにする。
店員が面倒がってしぶしぶ一個ずつ取ってくれたが、それを集めたら、どれがいくらのものだったかわからなくなってしまった。いちいち値段を店員に確認し、一つ一つの林檎に値段を書き込もうとして、「ちよつと筆を貸してくれませんか」と頼む。
そこに至るまで面倒なことをさせられていた店員は、ついにキレる。「人の店に這入つて来て、変な事をするのは止めて貰いませう」。百閒もキレる。「いきなり、ぷいと店を出てむしやくしやしながら、道を歩いた」。
百閒はしつこい。それだけでは腹の虫が収まらず、「到頭その店の主人に宛てて、名前は解らないけれども、屋号を知つてゐるから、手紙を書いて、不都合をなじつた」。
いつも利用している電車の停留場の前にある果物屋である。「私の方は、そのお蔭で電車の乗り降りの度に、いつ迄も気づまりな思ひをした」。
こういう話がちょろちょろ出てくるので、つい、読まされてしまうのである。私は百閒のちょっと毛色の変わった腹の虫(=生理)というのが好きなのだが、どうも、百閒自身、それをちょっと読んでいるようなところもあるなあ、80パーセントはやむにやまれぬ腹の虫なのだが20パーセントは衒(てら)ったところもあるなあ。そこがまたわがままお坊ちゃんらしくてかわいいんだけどね……と思う。
今回はどうも感想文と言うよりも紹介文のようになってしまった。ついでにもう一つ、紹介。百閒が「若い頃取り止めもない憂悶になやんでゐた当時」の話。「倉庫ぐらゐある大きな消し護謨(ゴム)に嚙みついて、一生懸命に歯を立てる事を考へて気分が悪くなつた事がある」のだそうだ。
ロッパじゃないが、「成程変っている」。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
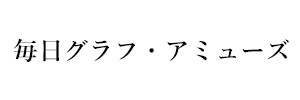
毎日グラフ・アミューズ(終刊) 1997年1月8日号
ALL REVIEWSをフォローする