書評
『寺田寅彦随筆集』(岩波書店)
前項は岩波文庫版の『柿の種』のことを書いたが、私、どうも寺田寅彦が好きなようだ。エッセーが面白い。何となくおかしくて、しかも頭がよくなるような気がして好きなのだ。
岩波文庫から『寺田寅彦随筆集』(全四巻)が出ていて、その第三巻には数編の映画エッセーが収録されている。昭和五年から七年頃に書かれたものである。映画がサイレントからトーキーに移り変わって間もない頃だ。その頃はまだ活動写真=映画というのはインテリがまともに論じる対象ではないと思われていた時代だと思うが、寺田寅彦は映画(とくに洋画)に興味を抱き、『東京帝国大学新聞』や『中央公論』といったところに、堂々たる映画芸術論を書いているのだ。
私も映画が好きで、映画評論の本もほんの少しだけ読んだが……いやー、寺田寅彦の映画芸術論は、六十年以上昔に書かれたものとは思えないほど刺激的だ。
何と言っても、寺田寅彦の長年の趣味である俳諧と映画とを重ね合わせて、映画を分析しているところがユニークだ。
映画通の間ではロシアのエイゼンシュテインのモンタージュ理論が有名だが、寺田寅彦はこれを日本の俳諧連句と同じことだと言うのである。『芭蕉七部集』を読めば、エイゼンシュテインが主張し、世界中の監督たちが影響を受けた「モンタージュ」という映画術のことがよくわかるはずだと言うのである。
そして寺田寅彦は、ロシア映画の『大地』を見て、こう言う。「映画『大地』はドラマでもなく、エピックでもなく、またリュリックでもない。これに比較さるべき唯一の芸術形式は東洋日本の特産たる俳諧連句である」。たとえば『大地』の美しいラストシーン――ほこりっぽい、塩辛い汗と涙の葬列の場面が続いたあとで、沛然(はいぜん)として降り注ぐ果樹園の雨のラストシーン――は、ちょうど連句の揚げ句(しめくくりの句)のようなものだと言うのである。
映画『大地』は連句である、という主張を補強するために、寺田寅彦は、自作の連句でもって『大地』を説明してみせる。
こんな連続をもってこの一巻の“歌仙式フィルム”は始まるのである。それからたとえば、
とでもいったような場面などがいろいろあって、そうして終わりには、
なるほどなあ、と思う。私はエイゼンシュテインのモンタージュ理論も連句もよく知らないが、そうだよね、映画の妙味って一場面一場面の面白さとともに、それが転換推移するときの連続感と不連続感(イメージの飛躍やコントラストの妙)にもあるんだよねと思う。モンタージュ理論や連句のエッセンスがわかったような気分になる。
寺田寅彦の映画の見方は、とても男性的な感じがする。映画をこのように構造的に把握したがり、またこのように構造的に語りたがるところが、私にはいかにも男の人らしく感じられるのだ。
恥ずかしながら私も映画エッセーを書いているが、こういう構造分析的なものは全然書けない。スターの誰それがよかったとか、そのお話のどこそこが面白かったとか、そういう、いわゆる「印象批評」しか書けない。寺田寅彦流の分析的映画評論は永遠に自分の手に入らぬ憧れである。
といったハッとするような指摘が次から次へと出てくるが、とくに注目すべきは次のくだりだ。
小津安二郎が大部屋でくすぶっていた笠智衆を抜擢したときのセリフ――「表情はなしだ、能面で行け」を思い出す。
寺田寅彦の映画エッセーの面白さは、連句とか文楽とか日本文化にかんする深い洞察の中から、(当時の)舶来新文化である映画の本質をつかまえようとしているところである。だから、才気たっぷりではあっても「才気走った」という薄っぺらな感じがしないのだと思う。福田恆存の言う通り「日本人は“和魂洋才”などと言ったからダメなのだ。和魂で洋魂をとらえなければいけなかったのだ」。
ああ、紙数が足りない。寺田寅彦のエッセーを読んでいると、いつもその「生涯一科学少年」的な純真さにクスクス笑わされる。
たとえば、『アフリカは語る』というドキュメント映画を見て、湖畔のフラミンゴの大群の中に一カ所だけ空地があるのは湖底がそこだけ深いに違いないと推理して「もしそうだとすれば鳥の群れの写真から湖底の等深線の一つがわかるはずである」と書いたりするところ。もちろん本気(マジ)で。私にはそういうところが、男の子ぽくてかわいいのだ。
【この書評が収録されている書籍】
岩波文庫から『寺田寅彦随筆集』(全四巻)が出ていて、その第三巻には数編の映画エッセーが収録されている。昭和五年から七年頃に書かれたものである。映画がサイレントからトーキーに移り変わって間もない頃だ。その頃はまだ活動写真=映画というのはインテリがまともに論じる対象ではないと思われていた時代だと思うが、寺田寅彦は映画(とくに洋画)に興味を抱き、『東京帝国大学新聞』や『中央公論』といったところに、堂々たる映画芸術論を書いているのだ。
私も映画が好きで、映画評論の本もほんの少しだけ読んだが……いやー、寺田寅彦の映画芸術論は、六十年以上昔に書かれたものとは思えないほど刺激的だ。
何と言っても、寺田寅彦の長年の趣味である俳諧と映画とを重ね合わせて、映画を分析しているところがユニークだ。
映画通の間ではロシアのエイゼンシュテインのモンタージュ理論が有名だが、寺田寅彦はこれを日本の俳諧連句と同じことだと言うのである。『芭蕉七部集』を読めば、エイゼンシュテインが主張し、世界中の監督たちが影響を受けた「モンタージュ」という映画術のことがよくわかるはずだと言うのである。
(『芭蕉七部集』を読めば)舶来のモンタージュ術と本質的に同型で、しかもこれに比べて比較にならぬほど立派なものが何百年前の日本の民衆の間に平気で行なわれていたことを発見して驚くであろう。
ウンター・デン・リンデンを歩いている女と、タウェンチーン街を歩いている男と、ホワイトハウスの玄関をはぎ合わせたりするような事はそもそも宵の口のことであって、もっともっと美しい深い内容的のモンタージュはいかなる連句のいかなる所にも見いだされるであろう。(「映画雑感Ⅰ」)
そして寺田寅彦は、ロシア映画の『大地』を見て、こう言う。「映画『大地』はドラマでもなく、エピックでもなく、またリュリックでもない。これに比較さるべき唯一の芸術形式は東洋日本の特産たる俳諧連句である」。たとえば『大地』の美しいラストシーン――ほこりっぽい、塩辛い汗と涙の葬列の場面が続いたあとで、沛然(はいぜん)として降り注ぐ果樹園の雨のラストシーン――は、ちょうど連句の揚げ句(しめくくりの句)のようなものだと言うのである。
映画『大地』は連句である、という主張を補強するために、寺田寅彦は、自作の連句でもって『大地』を説明してみせる。
草を吹く風の果てなり雲の峰
娘十八向日葵(ひまわり)の宿
死んで行く人の片頬(かたほ)に残る笑(えみ)
秋の実りは豊かなりけり
こんな連続をもってこの一巻の“歌仙式フィルム”は始まるのである。それからたとえば、
踊りつつ月の坂道ややふけて
はたと断えたる露の玉の緒
とでもいったような場面などがいろいろあって、そうして終わりには、
葬礼のほこりにむせて萩尾花
母なる土に帰る秋雨
なるほどなあ、と思う。私はエイゼンシュテインのモンタージュ理論も連句もよく知らないが、そうだよね、映画の妙味って一場面一場面の面白さとともに、それが転換推移するときの連続感と不連続感(イメージの飛躍やコントラストの妙)にもあるんだよねと思う。モンタージュ理論や連句のエッセンスがわかったような気分になる。
寺田寅彦の映画の見方は、とても男性的な感じがする。映画をこのように構造的に把握したがり、またこのように構造的に語りたがるところが、私にはいかにも男の人らしく感じられるのだ。
恥ずかしながら私も映画エッセーを書いているが、こういう構造分析的なものは全然書けない。スターの誰それがよかったとか、そのお話のどこそこが面白かったとか、そういう、いわゆる「印象批評」しか書けない。寺田寅彦流の分析的映画評論は永遠に自分の手に入らぬ憧れである。
(すぐれた映画監督は)概念の代わりに“印象”を、説明の代わりに“詩”を、そうして、三面記事の代わりに“俳諧”を提出したであろう。
このいわゆる俳味というのはロイドやキートンになくてチャプリンのどこかにある東洋哲学的のにおいである。(以上「映画雑感Ⅰ」)
といったハッとするような指摘が次から次へと出てくるが、とくに注目すべきは次のくだりだ。
大写しの顔や手は、決して“芝居”をしてはいけないことになっている。それをするといやみで見ていられなくなるのである。
巧妙な映画監督は、大写しのなんともない自然な一つの顔を、いわゆるモンタージュによって泣いている顔にも見せ、また笑っているようにも見せる。これはその顔が自然の顔でなんら概念的な感情を表現していないからこそ可能になるわけである。同じことは能面の顔についても人形芝居の人形の顔についてもいわれる、これらの顔は泣いているともつかず怒っているともまた笑っているともつかぬ顔である。しかしまたそれだから、大いに泣き、大いに怒りまた笑った顔となりうる潜在能をもった顔である。(以上「生ける人形」)
小津安二郎が大部屋でくすぶっていた笠智衆を抜擢したときのセリフ――「表情はなしだ、能面で行け」を思い出す。
寺田寅彦の映画エッセーの面白さは、連句とか文楽とか日本文化にかんする深い洞察の中から、(当時の)舶来新文化である映画の本質をつかまえようとしているところである。だから、才気たっぷりではあっても「才気走った」という薄っぺらな感じがしないのだと思う。福田恆存の言う通り「日本人は“和魂洋才”などと言ったからダメなのだ。和魂で洋魂をとらえなければいけなかったのだ」。
ああ、紙数が足りない。寺田寅彦のエッセーを読んでいると、いつもその「生涯一科学少年」的な純真さにクスクス笑わされる。
たとえば、『アフリカは語る』というドキュメント映画を見て、湖畔のフラミンゴの大群の中に一カ所だけ空地があるのは湖底がそこだけ深いに違いないと推理して「もしそうだとすれば鳥の群れの写真から湖底の等深線の一つがわかるはずである」と書いたりするところ。もちろん本気(マジ)で。私にはそういうところが、男の子ぽくてかわいいのだ。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
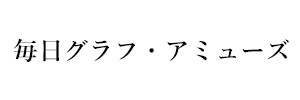
毎日グラフ・アミューズ(終刊) 1995年3月8日号〜1997年1月8日号
ALL REVIEWSをフォローする





































