書評
『柿の種』(岩波書店)
岩波文庫から新しく『柿の種』が出たので、さっそく買って読んでみた。
面白い。文庫版であっても、品のいい愉しい装丁で、本文中の草花状のマークも洒落ているこの本が、小さな宝物のようにいとおしく、とうとく見えてくる。
大正九年から亡くなる直前の昭和十年までの間に書かれた、ごくごく短い随筆百七十六編を集めたものである。著者は、自序で「きわめて気楽に気ままに書き流したものである」「身辺の些事に関するたわいもないフィロソフィーレンや、われながら幼稚な、あるいはいやみな感傷などが主なる基調をなしている」――と書いているが、とんでもない、すばらしい短文集だ。わかりやすく、しかも、深い。平明かつ深遠。これこそ随筆の真髄ではないだろうか。
百七十六編の最初の一編から、強く惹き込まれる。
「日常生活の世界と詩歌の世界の境界は、ただ一枚のガラス板で仕切られている」という書き出しで(不粋な言葉になってしまうが)実生活と文学との関係について語られている。
そのガラス板には小さな狭い穴があいていて、始終その二つの世界を出入りしていると、その穴は大きくなっていくのだが、ある人たちはその穴の存在さえ知らない。ガラス板があまりにも曇っていて、反対側の世界が見えないのだと寺田寅彦は言う。
「穴を見つけても通れない人もある。それは、あまりからだが肥り過ぎているために……」と続くのが、おかしい。まったくその通りだ。世間的な打算や分別や強欲などで頭の中に厚着している人間は、永遠に文学=曇ったガラス板の向こう側の世界とは無縁である。しかし、私に言わせれば……そういうふうに頭の中が厚着の人に限って、えてして三文小説好きだったり、達者に書いてみせたりするのは皮肉なことである。
この短文の最後の一行にも、唸る。
「まれに、きわめてまれに、天の焰(ほのお)を取って来てこの境界のガラス板をすっかり溶かしてしまう人がある」。なるほど、天才とはそういうことなのかと、視覚的イメージでわかってくる。
冒頭のこの一編などは珍しく抽象的な言葉に終始しているが、他の多くは、ごく具体的で日常的な事柄を中心に筆をすすめていく。たとえば、こんな調子だ。
具体的な手ざわりのある事柄から、ある法則性を発見し、そこからヒョイと、まったく別の世界の事柄を連想し、類推し、抽象化していく。この「ヒョイ」というところが、寺田寅彦の随筆の刺激的なところだ。頭の中の配線が、うまく、面白くできている人という感じがする。おかげで読んでいる私のほうも少し頭がよくなった感じがする。
しかも、その「ヒョイ」に、頭の曲芸的なこれ見よがしのあざとさがなくて、あくまでもつつましく、さりげないのが好もしい(時に――ほんの二、三編、芥川龍之介のアフォリズムめいたものもあるけれど、それはあんまり面白くない)。
眼は閉じられるのに耳のほうは閉じられないようにできているのはなぜだろうとか、鳥や魚のように眼が頭の両側についていたら、この世界はどんなふうに見えるのだろうとか……私の子ども時代にはやった『なぜだろうなぜかしら』という本(子ども向き科学書)を思い出させるような、「永遠の科学少年」のような短文もある。
蟻が自分の身長の数百倍もあるコスモスの枝の尖端で働いているのを見て「どうして蟻がこの高い高い茎の頂上につぼみのできたことをかぎつけるかが不思議である」と書き、また、椿の花がどれも仰向けに落ちているのを不思議に思ったが、知り合いの植物学者に「花が樹にくっついている間は植物学の問題になるが、樹をはなれた瞬間から以後の事柄は問題にならぬ」と言われ、「学問というものはどうも窮屈なものである」と嘆き、また、ガラス板に鋼鉄の球をぶつけて割れ目を作り、その割れ目の形状を顕微鏡で調べるという研究に熱中していて、「今まで、まだやっと二、三百枚のガラス板しかこわしていないが、少なくも二、三千枚ぐらいはこわしてみなければなるまいと思っている」と書く物理学者・寺田寅彦が、私は好きだ。
「宇宙の秘密が知りたくなった、と思うと、いつのまにか自分の手は一塊の土くれをつかんでいた。そうして、ふたつの眼がじいっとそれを見つめていた」と寺田寅彦は書いているが、私も宇宙の秘密――この大地と人間の秘密が知りたい。その知りたいわかりたい握りしめたい……との思いにつき動かされて、生きているのだと思う。そのことをハッキリと心に確認できる瞬間は、喜びだ。「生きている」という実感がある。けれど、おうおうにして忘れて、この本の中にも出て来る言葉――自動人形(アウトマーテン)のようになって日を送ってしまう。
寺田寅彦の随筆を読んでいると、「情報」と「知識」とは別のものだ、ということがハッキリとわかる。「情報」は「技術」とは結びついても、そのままでは「知識」にはならない。「宇宙の秘密」にたいする豊かな感受性によって練りあげられなければ「知識」にはならないと私は思う。「おたく」と「知識人」は、決定的に違う。
この岩波文庫では巻末に池内了さんのすぐれた解説がついている。そこでも語られていることだが、上野松坂屋の食堂で見かけた家族の対話や、皮膚病を患った男と少女の対話などに触れた短文には、寺田寅彦の、まったくsensitiveな、心の芯の部分をかいまみる思いがする。
一編一編は短いので、通勤電車の中で、また散歩や旅行のときなどに、少しずつ、少しずつ、かみしめながら読んでいただきたい。頭がよくなり、心が柔かくなる一冊です。
【この書評が収録されている書籍】
面白い。文庫版であっても、品のいい愉しい装丁で、本文中の草花状のマークも洒落ているこの本が、小さな宝物のようにいとおしく、とうとく見えてくる。
大正九年から亡くなる直前の昭和十年までの間に書かれた、ごくごく短い随筆百七十六編を集めたものである。著者は、自序で「きわめて気楽に気ままに書き流したものである」「身辺の些事に関するたわいもないフィロソフィーレンや、われながら幼稚な、あるいはいやみな感傷などが主なる基調をなしている」――と書いているが、とんでもない、すばらしい短文集だ。わかりやすく、しかも、深い。平明かつ深遠。これこそ随筆の真髄ではないだろうか。
百七十六編の最初の一編から、強く惹き込まれる。
「日常生活の世界と詩歌の世界の境界は、ただ一枚のガラス板で仕切られている」という書き出しで(不粋な言葉になってしまうが)実生活と文学との関係について語られている。
そのガラス板には小さな狭い穴があいていて、始終その二つの世界を出入りしていると、その穴は大きくなっていくのだが、ある人たちはその穴の存在さえ知らない。ガラス板があまりにも曇っていて、反対側の世界が見えないのだと寺田寅彦は言う。
「穴を見つけても通れない人もある。それは、あまりからだが肥り過ぎているために……」と続くのが、おかしい。まったくその通りだ。世間的な打算や分別や強欲などで頭の中に厚着している人間は、永遠に文学=曇ったガラス板の向こう側の世界とは無縁である。しかし、私に言わせれば……そういうふうに頭の中が厚着の人に限って、えてして三文小説好きだったり、達者に書いてみせたりするのは皮肉なことである。
この短文の最後の一行にも、唸る。
「まれに、きわめてまれに、天の焰(ほのお)を取って来てこの境界のガラス板をすっかり溶かしてしまう人がある」。なるほど、天才とはそういうことなのかと、視覚的イメージでわかってくる。
冒頭のこの一編などは珍しく抽象的な言葉に終始しているが、他の多くは、ごく具体的で日常的な事柄を中心に筆をすすめていく。たとえば、こんな調子だ。
脚を切断してしまった人が、時々、なくなっている足の先のかゆみや痛みを感じることがあるそうである。総入れ歯をした人が、どうかすると、その歯がずきずきうずくように感じることもあるそうである。こういう話を聞きながら、私はふと、出家遁世(とんせい)の人の心を想いみた。生命のある限り、世を捨てるということは、とてもできそうに思われない。
具体的な手ざわりのある事柄から、ある法則性を発見し、そこからヒョイと、まったく別の世界の事柄を連想し、類推し、抽象化していく。この「ヒョイ」というところが、寺田寅彦の随筆の刺激的なところだ。頭の中の配線が、うまく、面白くできている人という感じがする。おかげで読んでいる私のほうも少し頭がよくなった感じがする。
しかも、その「ヒョイ」に、頭の曲芸的なこれ見よがしのあざとさがなくて、あくまでもつつましく、さりげないのが好もしい(時に――ほんの二、三編、芥川龍之介のアフォリズムめいたものもあるけれど、それはあんまり面白くない)。
眼は閉じられるのに耳のほうは閉じられないようにできているのはなぜだろうとか、鳥や魚のように眼が頭の両側についていたら、この世界はどんなふうに見えるのだろうとか……私の子ども時代にはやった『なぜだろうなぜかしら』という本(子ども向き科学書)を思い出させるような、「永遠の科学少年」のような短文もある。
蟻が自分の身長の数百倍もあるコスモスの枝の尖端で働いているのを見て「どうして蟻がこの高い高い茎の頂上につぼみのできたことをかぎつけるかが不思議である」と書き、また、椿の花がどれも仰向けに落ちているのを不思議に思ったが、知り合いの植物学者に「花が樹にくっついている間は植物学の問題になるが、樹をはなれた瞬間から以後の事柄は問題にならぬ」と言われ、「学問というものはどうも窮屈なものである」と嘆き、また、ガラス板に鋼鉄の球をぶつけて割れ目を作り、その割れ目の形状を顕微鏡で調べるという研究に熱中していて、「今まで、まだやっと二、三百枚のガラス板しかこわしていないが、少なくも二、三千枚ぐらいはこわしてみなければなるまいと思っている」と書く物理学者・寺田寅彦が、私は好きだ。
「宇宙の秘密が知りたくなった、と思うと、いつのまにか自分の手は一塊の土くれをつかんでいた。そうして、ふたつの眼がじいっとそれを見つめていた」と寺田寅彦は書いているが、私も宇宙の秘密――この大地と人間の秘密が知りたい。その知りたいわかりたい握りしめたい……との思いにつき動かされて、生きているのだと思う。そのことをハッキリと心に確認できる瞬間は、喜びだ。「生きている」という実感がある。けれど、おうおうにして忘れて、この本の中にも出て来る言葉――自動人形(アウトマーテン)のようになって日を送ってしまう。
寺田寅彦の随筆を読んでいると、「情報」と「知識」とは別のものだ、ということがハッキリとわかる。「情報」は「技術」とは結びついても、そのままでは「知識」にはならない。「宇宙の秘密」にたいする豊かな感受性によって練りあげられなければ「知識」にはならないと私は思う。「おたく」と「知識人」は、決定的に違う。
この岩波文庫では巻末に池内了さんのすぐれた解説がついている。そこでも語られていることだが、上野松坂屋の食堂で見かけた家族の対話や、皮膚病を患った男と少女の対話などに触れた短文には、寺田寅彦の、まったくsensitiveな、心の芯の部分をかいまみる思いがする。
一編一編は短いので、通勤電車の中で、また散歩や旅行のときなどに、少しずつ、少しずつ、かみしめながら読んでいただきたい。頭がよくなり、心が柔かくなる一冊です。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
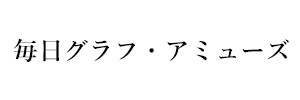
毎日グラフ・アミューズ(終刊) 1995年3月8日号〜1997年1月8日号
ALL REVIEWSをフォローする




































