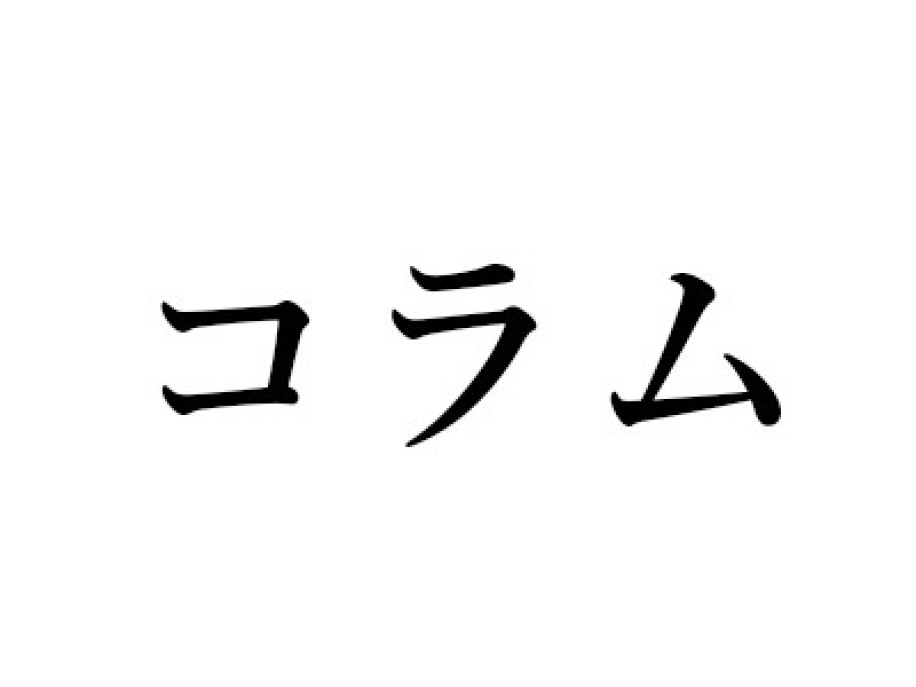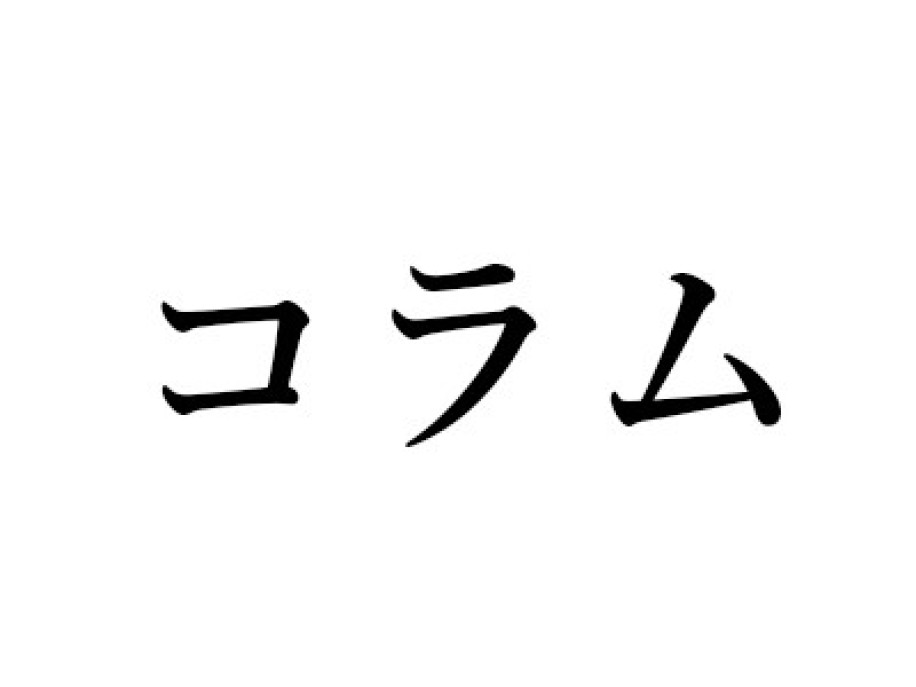書評
『ヰタ・セクスアリス』(新潮社)
本棚の整理をしていたら、筑摩書房の『現代文学大系4・森鷗外集』が出てきた。大学時代に古書店で買ったものだ。
パラパラめくってみると、ところどころ鉛筆のマークがあり、読んだ形跡が確かにある。にもかかわらず、どれも内容に関してあんまりおぼえていないので、自分でも呆れる。漱石はストレートに好きだが、どうも、鷗外はそれほどでもなかったようだ。『妄想』や『あそび』に繰り返し描き出された「ディレッタントの心」にはずいぶん共感したつもりではあるけれど。
有名な『ヰタ・セクスアリス』にも鉛筆のマークの跡があるので驚く。私はまったくおぼえていないのだ。よく見ると、マークは前半だけだ。途中で退屈してしまったのだろう。
昔は何の不思議も感じなかったが、あの自己抑制的な鷗外が、いちおうフィクションの体裁を取っているとはいえ自分の性遍歴をつづってみた――というのが妙である。「高尚なる人物は仮面を被つてゐる。仮面を尊敬せねばならない」(『仮面』)と書いた人のようではない。何か特別の意図があってしたことなんじゃないだろうか。
という興味を抱いて、読んでみた。やっぱり鷗外は真面目な人だ。冒頭数ページを費やして、なぜ「自分の性欲的生活の歴史」を書くことにしたかが、しっかりと説明されている。ひとことで言うと、それはどうやら、当時流行の自然主義文学にたいする強い違和感と、そのいっぽうで湧き起こってくる冷静なる興味――この二つにつき動かされてのことらしい。
自然主義文学が何につけても性欲的描写をともない、また、批評がそれを人生を写し得たものとして認めるという状況を見て、鷗外は大いに違和感をおぼえる。「人生は果してそんなものであらうか」「自分が人間一般の心理的状態を外れて性欲に冷澹(れいたん)であるのではないか」と首をひねる。
そのいっぽうで、人間が恋愛や芸術においてそんなに性欲に支配されているのだとしたら、「こいつは奇警だ。併し奇警ついでに何故此説をも少し押し広めて、人生のあらゆる出来事は皆性欲の発揮であると立てないのだらう」と考える。宗教などはその最たるものではないか、とも疑う。そして「一体性欲といふものが人の生涯にどんな順序で発現して来て、人の生涯にどれ丈(だけ)関係してゐるかといふことを徴すべき文献は甚だ少いやうだ」とも思いつく。
そういうわけで、鷗外は「自分の性欲的生活の歴史」を振り返ってみた。はたして自分はどの程度に性欲に支配されてきたか。あるいは支配されてこなかったか――と。自分自身を使った一種の臨床レポートを書いてみる気になったのだ。
主人公の名前は金井湛(しづか)で、哲学教授ということになっている。金井の回想は六歳の頃の思い出から始まる。近くに住む後家のおばさんと知らない娘がポルノグラフィを読んでいたのに出くわし、からかわれる。「僕は二人の見てゐた絵の何物なるかを判断する智識を有せなかつた。併し二人の言語挙動を非道く異様に、しかも不愉快に感じた。そして何故か知らないが、此出来事をお母様に問ふことを憚(はばか)つた」
性的な事柄にかんして、子どもが「何かわからないが、へんなもの、おおっぴらにできないもの」と感じ取る、その感受性は思いのほか鋭敏なものだ。自分の子ども時代を振り返ってみても、その感じはよくわかる。
七歳の頃、十歳の頃、十一歳の頃……と、いくつかの記憶の断片が語られていき、その事柄の内容よりもそれを描写する鷗外の文章のほうに興味を惹かれる。過不足なく明晰な文章だ。ごく下劣な老人やあやしげな二枚目や売春婦なども登場し、その人びとのかもし出す気配はよくわかるのだが、何かよく磨かれたガラス越しに見えている感じだ。
私が驚いたのはこの金井が大学進学前の二年間、ドイツ語学校に入り、寄宿舎で暮らしていたときの話だ(この部分が長い)。急に下世話になるが、その寄宿舎内での同性愛の横行ぶりに私はビックリしたのだった。
その寄宿舎内では最年少の金井は、年長者につけ狙われる。金井は実家に帰ったとき短刀を一本かくし持って来て、ある年長者が夜這い(?)をかけて来たときは、その短刀を握り、屋根に逃げかくれた――というほどだ。
「その頃の生徒仲間には軟派と硬派とがあつた」そうで、軟派は女を追い回すほう、硬派は男を追い回すほう――というニュアンスである。軟派・硬派という言葉の、そういう意味の使い方もあったわけだ……。
森鷗外はなんと十三歳(当時は年齢を十五歳と偽っていた)で東京医学校予科(=東大医学部)に入学した。しかも年長者たちにまったくひけを取らぬ優秀な学生だった。この『ヰタ・セクスアリス』を読むと、そんな天才児ゆえの苦労が、十分にうかがわれる。
「自分の醜男子(ぶおとこ)なることを知つて、所詮(しょせん)女には好かれないだらうと思つた。此頃から後は、此考が永遠に僕の意識の底に潜伏してゐて、僕に十分の得意といふことを感ぜさせない。そこへ年齢の不足といふことが加勢して、何事をするにも、友達に暴力で圧せられるので、僕は陽に屈服して陰に反抗するといふ態度になつた」
同室の年長者である鰐口や古賀という男の描写も面白い。金井は、時に性欲の獣を野放しにする古賀とそれからもう一人のうぶな友人と「三角同盟」を結んで、他の奔放な生徒たちを批判する。
なんてバランスよく明晰なひとなんだろう。そこに感心もするし、もっといびつに狂っているほうが面白いのにとも、ちょっと思う。
回想記は大学を卒業し、留学したところで終わる。金井は「自分は少年の時から、余りに自分を知り抜いてゐたので、その悟性が情熱を萌芽のうちに枯らしてしまつたのである」と書いたあと、たちまち考え直して、こう書き続ける。
ちょっとうっちゃりをくったような気分になる。私は鷗外のことが、やっぱり根本的にわかっていないんだなと思う。鷗外の孤独な「熱」をわかる人は少ないかもしれない。
【この書評が収録されている書籍】
パラパラめくってみると、ところどころ鉛筆のマークがあり、読んだ形跡が確かにある。にもかかわらず、どれも内容に関してあんまりおぼえていないので、自分でも呆れる。漱石はストレートに好きだが、どうも、鷗外はそれほどでもなかったようだ。『妄想』や『あそび』に繰り返し描き出された「ディレッタントの心」にはずいぶん共感したつもりではあるけれど。
有名な『ヰタ・セクスアリス』にも鉛筆のマークの跡があるので驚く。私はまったくおぼえていないのだ。よく見ると、マークは前半だけだ。途中で退屈してしまったのだろう。
昔は何の不思議も感じなかったが、あの自己抑制的な鷗外が、いちおうフィクションの体裁を取っているとはいえ自分の性遍歴をつづってみた――というのが妙である。「高尚なる人物は仮面を被つてゐる。仮面を尊敬せねばならない」(『仮面』)と書いた人のようではない。何か特別の意図があってしたことなんじゃないだろうか。
という興味を抱いて、読んでみた。やっぱり鷗外は真面目な人だ。冒頭数ページを費やして、なぜ「自分の性欲的生活の歴史」を書くことにしたかが、しっかりと説明されている。ひとことで言うと、それはどうやら、当時流行の自然主義文学にたいする強い違和感と、そのいっぽうで湧き起こってくる冷静なる興味――この二つにつき動かされてのことらしい。
自然主義文学が何につけても性欲的描写をともない、また、批評がそれを人生を写し得たものとして認めるという状況を見て、鷗外は大いに違和感をおぼえる。「人生は果してそんなものであらうか」「自分が人間一般の心理的状態を外れて性欲に冷澹(れいたん)であるのではないか」と首をひねる。
そのいっぽうで、人間が恋愛や芸術においてそんなに性欲に支配されているのだとしたら、「こいつは奇警だ。併し奇警ついでに何故此説をも少し押し広めて、人生のあらゆる出来事は皆性欲の発揮であると立てないのだらう」と考える。宗教などはその最たるものではないか、とも疑う。そして「一体性欲といふものが人の生涯にどんな順序で発現して来て、人の生涯にどれ丈(だけ)関係してゐるかといふことを徴すべき文献は甚だ少いやうだ」とも思いつく。
そういうわけで、鷗外は「自分の性欲的生活の歴史」を振り返ってみた。はたして自分はどの程度に性欲に支配されてきたか。あるいは支配されてこなかったか――と。自分自身を使った一種の臨床レポートを書いてみる気になったのだ。
主人公の名前は金井湛(しづか)で、哲学教授ということになっている。金井の回想は六歳の頃の思い出から始まる。近くに住む後家のおばさんと知らない娘がポルノグラフィを読んでいたのに出くわし、からかわれる。「僕は二人の見てゐた絵の何物なるかを判断する智識を有せなかつた。併し二人の言語挙動を非道く異様に、しかも不愉快に感じた。そして何故か知らないが、此出来事をお母様に問ふことを憚(はばか)つた」
性的な事柄にかんして、子どもが「何かわからないが、へんなもの、おおっぴらにできないもの」と感じ取る、その感受性は思いのほか鋭敏なものだ。自分の子ども時代を振り返ってみても、その感じはよくわかる。
七歳の頃、十歳の頃、十一歳の頃……と、いくつかの記憶の断片が語られていき、その事柄の内容よりもそれを描写する鷗外の文章のほうに興味を惹かれる。過不足なく明晰な文章だ。ごく下劣な老人やあやしげな二枚目や売春婦なども登場し、その人びとのかもし出す気配はよくわかるのだが、何かよく磨かれたガラス越しに見えている感じだ。
私が驚いたのはこの金井が大学進学前の二年間、ドイツ語学校に入り、寄宿舎で暮らしていたときの話だ(この部分が長い)。急に下世話になるが、その寄宿舎内での同性愛の横行ぶりに私はビックリしたのだった。
その寄宿舎内では最年少の金井は、年長者につけ狙われる。金井は実家に帰ったとき短刀を一本かくし持って来て、ある年長者が夜這い(?)をかけて来たときは、その短刀を握り、屋根に逃げかくれた――というほどだ。
「その頃の生徒仲間には軟派と硬派とがあつた」そうで、軟派は女を追い回すほう、硬派は男を追い回すほう――というニュアンスである。軟派・硬派という言葉の、そういう意味の使い方もあったわけだ……。
森鷗外はなんと十三歳(当時は年齢を十五歳と偽っていた)で東京医学校予科(=東大医学部)に入学した。しかも年長者たちにまったくひけを取らぬ優秀な学生だった。この『ヰタ・セクスアリス』を読むと、そんな天才児ゆえの苦労が、十分にうかがわれる。
「自分の醜男子(ぶおとこ)なることを知つて、所詮(しょせん)女には好かれないだらうと思つた。此頃から後は、此考が永遠に僕の意識の底に潜伏してゐて、僕に十分の得意といふことを感ぜさせない。そこへ年齢の不足といふことが加勢して、何事をするにも、友達に暴力で圧せられるので、僕は陽に屈服して陰に反抗するといふ態度になつた」
同室の年長者である鰐口や古賀という男の描写も面白い。金井は、時に性欲の獣を野放しにする古賀とそれからもう一人のうぶな友人と「三角同盟」を結んで、他の奔放な生徒たちを批判する。
僕の性欲的生活が繰延(くりのべ)になつたのは、全く此三角同盟のお陰である。後になつて考へて見れば、若し此同盟に古賀がゐなかつたら、此同盟は陰気な、貧血性な物になつたのかも知れない。
なんてバランスよく明晰なひとなんだろう。そこに感心もするし、もっといびつに狂っているほうが面白いのにとも、ちょっと思う。
回想記は大学を卒業し、留学したところで終わる。金井は「自分は少年の時から、余りに自分を知り抜いてゐたので、その悟性が情熱を萌芽のうちに枯らしてしまつたのである」と書いたあと、たちまち考え直して、こう書き続ける。
併し自分の悟性が情熱を枯らしたやうなのは、表面だけの事である。永遠の氷に掩はれてゐる地極の底にも、火山を突き上げる猛火は燃えてゐる。
ちょっとうっちゃりをくったような気分になる。私は鷗外のことが、やっぱり根本的にわかっていないんだなと思う。鷗外の孤独な「熱」をわかる人は少ないかもしれない。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
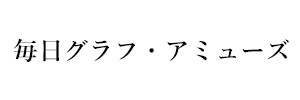
毎日グラフ・アミューズ(終刊) 1995年3月8日号~1997年1月8日号
ALL REVIEWSをフォローする