書評
『赤ちゃんができたらこんな本が読みたい』(草思社)
右手に子ども、左手に本
一九八一年に最初の赤ん坊が生まれて、一九八四年に地域雑誌「谷根千」を始めるまでの三年ばかり、一番本を読んだ気がする。専業主婦で暇はあったし、社会と接点を持てず欲求不満だった。初めての子どもを育てる不安と興奮で、私は図書館の育児の本をゴソッと“棚借り”した。杉山由美子さんは私より年上だけど、二人の女の子さんはうちより数歳年下。三十代半ばで子を産んで仕事も続けてきた。『赤ちゃんができたらこんな本が読みたい』(草思社)はその“本中毒”母の育児と読書の同時進行ドキュメント。三百冊を超す本を手ぎわよく紹介しながら、でもその本のいちばんいい所をムンズとつかんでいる。
うーむ、子そだて数年の違いで、ずい分面白い本が出ているもんだ。私は松田道雄『育児の百科』世代である。杉山さんは山田真『はじめてであう小児科の本』だそうだ。どちらも名著。何百回めくるに足る本だが、山田さんの本にはこの程度で病院にいくことはない、とホッとさせられ、ひるがえって「病気ってそんなに悪いもんなの?」と問われるそうだ。
そして『良いおっぱい 悪いおっぱい』の伊藤比呂美ブームのただなかを杉山さんは通過するが、私にはもう同時代感覚はなかった。「胎児はうんこと同じ」。ナニそれ、加藤登紀子がずい分前に言ってたよ、なんて横目で見てました。
杉山さんはかなりそそっかしい。『ニキーチン夫妻と七人の子ども』に感動し、赤ちゃんの握力はこんなにすごいのよ、と引っぱったら脱臼しちゃって救急車を呼んだり。相良敦子『ママ、ひとりでするのを手伝ってね!』にかぶれて、娘に包丁を与えたら指を切ってしまった。「モンテッソーリがどうのこうのって包丁を使わせるのもいいけど、やるからにはこういうことが起きたらどうするか、対処法まで考えておいてほしいね」と夫からはキツーいひとこと。
そういう失敗談が楽しい。
『丸元淑生のシステム料理学』にもかぶれたそうだ。「いきなりそば粉のパンケーキを焼き(これはおいしくなかった)、ステーキを油をひかずに焼き(これはいいと思った)、豆を煮て(生煮えが多かった)、あさりを食べ、ちりめんじゃこを買った」。このとおり、ちゃんと実用書も検証しながら紹介している。
仕事人間は子どもの相手をするのが下手。つい「本、持っといで」と読みきかせに走るのは私も同じで身につまされた。だけどそうして出会った絵本は母親の生活を豊かにする。『いやだいやだのスピンキー』はウケた。『いつもちこくのおとこのこ』はバカ受け。正直な子どもの反応が紹介のモノサシになっている(ついでにいうと、わが家では寝る前の漱石『吾輩は猫である』がバッカ受け)。
杉山さんはアメリカものに強い。絵本に育児書だけじゃこの時期さみしいじゃない。A・クィンドレン『グッド・ガール、バッド・ガール』。P・セルー『眠れぬ親たちのためのベッドタイム・ストーリー』、A・タイラー『夢見た旅』、N・エフロン『ハートバーン』、A・タン『ジョイ・ラック・クラブ』、……これみんな私は未読、赤丸印。「アメリカには、子持ち女性の意見が堂々と大新聞に連載され、広く共感を呼ぶという風土があるのだ」。日本では女・子ども物は書評も出ませんよ。男は読みゃしませんよ。
子育ては楽しいけれど、膨大な時間を食う。「ほんとうに、あの原稿いつ書いたんだっけ?とすっかり忘れているくらいに茫々と時間が過ぎて、夜中に疲労困憊している自分に気がつく」。実にそうなのです。それでも右手に子ども、左手に本はやめられない。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
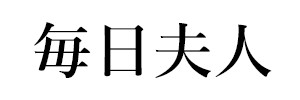
毎日夫人(終刊) 1993年~1996年
ALL REVIEWSをフォローする





































