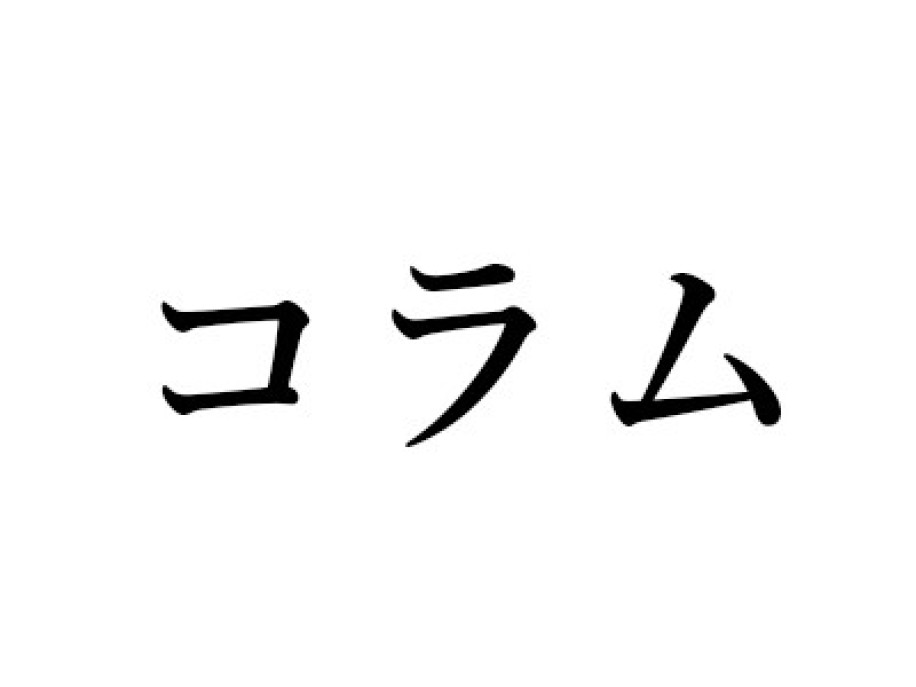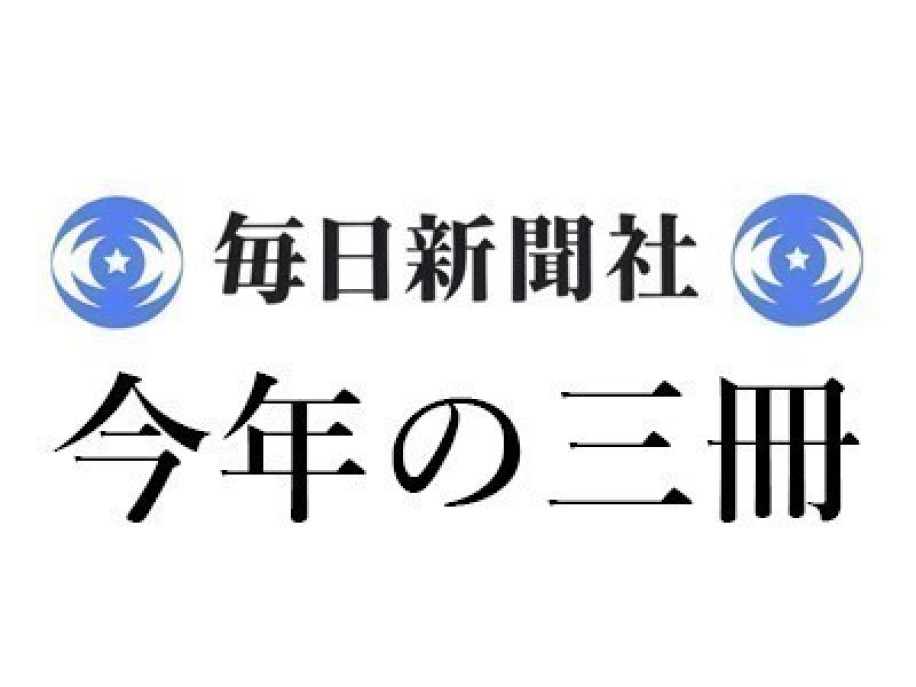書評
『夢の場所・夢の建築―原記憶のフィールドワーク』(工作舎)
二五年間の夢に現れた「場」を分析
フロイト、ユングなどなど、夢についての研究はたくさんあるが、旅館は……夢に最も受け入れられやすい建築。
なんて意表をつく説が書かれた本はちょっとない。
瀧口修造、中勘助、島尾敏雄、横尾忠則といった夢見の名人たちの採夢録を調べると、旅館・料亭の建物が印象深く登場し、きまってそれはとりとめもなく広く、どうなっているのか全体像が分からないまま、階段を上り、また下り、廊下を通って広間に出たかと思うと、土間になり、大きい部屋、小さい部屋、いずれも用途のはっきりしないところを、さまよい歩いてゆく。
たしかに、明確に区画された個室と廊下からなるホテルにくらべ、日本の旅館のあいまいで迷路的な空間は、夢そのものの性格とよく合っている。
旅館、学校をはじめとする建物や住宅、地域や町といった自分たちが暮らす「場」が、夢の中でいったいどんなになっているのかについて、日本はむろん夢研究の進んだヨーロッパでも、これまでほとんど語られていない。この方面にとば口を開く本ということになる。
著者は、二十五年前、人間と空間の関係の深層を知りたいと思い立ち、河合隼雄の影響を受け、見た夢の記録をとるようになり、およそ千百件を得た。
記録をとりはじめてしばらくして気づいたのは、成長期に私が過ごした家や町に関連する夢が非常に多いことだった。しかも、これはかなり普遍的らしいことが、諸文献や他人の話からも推測できた。
にもかかわらず、家や町といった場を通しての夢分析が遅れたのは、場は、夢の筋や人に比べ、本人がよほど意識的に記録しないとただちに忘れてしまうからだという。そのとおりで、たいていの人は昨日見た夢の話をする時、登場人物と筋については話すが、背景の様子を描写したりはしない。人・筋は場に優先する。
夢の特徴は、はかなさ消えやすさだが、中でもとりわけはかなく消えやすい場。そんなものにはたしてどんな意味があるんだろうか。
二十五年の採夢の中で、著者は面白い現象に気づく。優位に立つ人・筋とはかない場の二つを安定性という点からチェックするとどうも力関係は逆転するらしい。人・筋は、印象深いけれど、けっこう気まぐれで、見るたびにどんどん変わる。ところが、そのドラマの背景になる町や家や地形の様子はいちじるしく安定している。
そしてその安定した場にも優劣があるらしい、と気づくあたりから著者の分析は、夢分析ならではの佳境に入り、立ちこめる霧の中を懐中電燈をたよりに奥へと分け入ってゆく。ヘビが出るかジャが出るか。
「『夢の場』においては、成長期に住んだ家や町、環境が大きな比重を占める。一方、最近住み着いた環境は割合に見ることが少ない」。なるほど、夢の中では古い場の方が優位なのは想像にかたくない。では、転勤や改築によって新しい環境に放り込まれた時、その夜、夢の中にはどんな場が現われるか。
新しい場が現われる。ただし、新しい家の全体が現われるのではなくて、きわめて選択的に、古い家と類似したところばかりが出てくる。それもそうとう強引で、他人が見ると、本人でも醒めた後からチェックすると、ほとんど別物なのに、夢の中では、階段と居間の位置関係とかのごく一部の類似もしくはどの家でも当たり前の類似をとらえ、全体がとても似ているように感ずる。
自分の家や環境、とくに成長期のそれは、誰にとっても意味深い場所で、無意識の中でその人の一生を通じて新しく出会う場所に働きかけ続けるのだと考えられる。
こうした古い場の働きかけにより、新しい場は意識の奥で飼いならされ、人はそれを受け入れ、安心して住むようになる。誰でも経験するように新しい家に入居した時、眠って起きると、なんだか昨日と今日が無事つながったような珍しい気分になって安心するが、どうも夢の中で、古い場と新しい場の溶接工事がせっせと行われたおかげらしい。
昨日の私と今日の私が同一であるという自己のアイデンティティを支えているのは意識の方だが、夢を含む無意識の方は、場についての新たな経験情報を組み込みながら過去の経験を結合して安定性を支え、われわれの日々の前進に備えているのではなかろうか。
無意識下における場の連結感が、人間の自己同一感を保証している、と言うのである。
夢の中のはかなく消えやすい場は、夢の奥の夢、無意識の奥の無意識の住人だった。そのぶん意識の世界でははかなく消えやすい。著者も自ら言うようにずいぶん大胆で魅力的な仮説である。
杉浦康平のブックデザインも必見。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする