書評
『蹴りたい背中』(河出書房新社)
青臭い。なのに、独善的じゃない。描かれているのは高校生の世界。なのに、ハイティーンだけでなく、それこそリストラ世代の胸にも届く言葉に溢れている。綿矢りさの長篇第二作目にあたる『蹴りたい背中』は、“一七歳の女子高生が書いた”という話題だけが先行しがちだったデビュー作『インストール』よりはるかに普遍性の高い、この若い作家の明るい末来を予告するファンファーレのごとき晴れやかな小説なのだ。
主人公は高校一年生のハツ。友達は中学生時代から一緒の絹代ただ一人なのだけれど、その彼女も新しい友人グループを作ってしまい、ハツはクラスで浮いた存在になっている。ある日、もう一人のクラスの余り者、にな川に家に来ないかと誘われる。にな川はハツが中学生の頃偶然に出会ったモデルのオリチャンの大ファンで、彼女の情報を集めていたのだった。
「どうしてそんなに薄まりたがるんだろう。同じ溶液に浸(つ)かってぐったり安心して、他人と飽和することは、そんなに心地よいもんなんだろうか」。独りきりで過ごす休み時間や昼寝タイムの居心地の悪さをつらいと感じても、ハツはだからといって無理に仲間を作りたいとも思わない。練習をさぼることばかり考えている陸上部の、仲良しクラブのようにぬるい雰囲気にも馴染むことができない。
でも、中学時代にはそうしたグループの一員だったこともあるハツは「人のいる笑い声ばかりの向こう岸も、またそれはそれで息苦しい」のを知っている。笑いたくなくても笑って、他の人に調子を合わせなくてはならない暗黙の掟(おきて)の窮屈さを知っている。だから、よくいえばニュートラル、悪くいえばどっちつかずの状態にあるハツ。それゆえに、自分より一層他者と交わらず、オリチャンという幻想の中に閉じこもっているにな川が気になって仕方なくなってしまうのだ。
でも、それは“好き”という感情とは違う。オリチャンのラジオ番組を、「この方が耳元で囁(ささや)かれてる感じがするから」と、片耳イヤホンで聞くにな川の「この、もの哀しく丸まった、無防備な背中を蹴りたい。痛がるにな川を見たい」という欲望に耐えきれず、凄まじい力で蹴り倒すハツ。一緒にオリチャンの初コンサートに行き、地震が起こればいい、地震が起きたら自分がオリチャンを助けるんだという妄想を口走りながらも、しかし、絶対に地震など起こらないことも分かっているにな川が絶望的な表情を見せれば「にな川がさびしい。彼を可哀相と思う気持ちと同じ速度で、反対側のもう一つの激情に引っぱられていく。にな川の傷ついた顔を見たい。もっとかわいそうになれ」と思ってしまうハツ。
勉強ができるわけじゃない。ルックスがいいわけじゃない。何か特技があるわけでもない。だから、独りとはいっても、それは孤高の存在なんてカッコイイものではなくて、クラスのお荷物的存在としての独り。ハツはそんな自分の情けない立場をよく知っている。ところが、にな川ときたら、自分以上にクラスメートから異物扱いを受けているのに、意にも介さない。オリチャンさえいれば満足なのだ。オリチャンのグッズに囲まれていれば幸福なのだ。そんなにな川に対する共感と苛立ちと、ほんのわずかな羨望と――。
一歩間違えば陰惨な、しかも哀しいくらい低レベルないじめに向かってしまいそうなそうした心象を、綿矢さんは簡単に決着させることなく、丁寧に、でもくどくはない、どちらかといえば軽いユーモラスな筆致で描いていく。そして、ハツとにな川の関係性を開いたまま、物語を閉じる。一九歳にしか書けない、けれどフツーの一九歳には決して書くことができない。これは新しい才能の開花を告げる慶賀の一冊なのだ。
【この書評が収録されている書籍】
主人公は高校一年生のハツ。友達は中学生時代から一緒の絹代ただ一人なのだけれど、その彼女も新しい友人グループを作ってしまい、ハツはクラスで浮いた存在になっている。ある日、もう一人のクラスの余り者、にな川に家に来ないかと誘われる。にな川はハツが中学生の頃偶然に出会ったモデルのオリチャンの大ファンで、彼女の情報を集めていたのだった。
「どうしてそんなに薄まりたがるんだろう。同じ溶液に浸(つ)かってぐったり安心して、他人と飽和することは、そんなに心地よいもんなんだろうか」。独りきりで過ごす休み時間や昼寝タイムの居心地の悪さをつらいと感じても、ハツはだからといって無理に仲間を作りたいとも思わない。練習をさぼることばかり考えている陸上部の、仲良しクラブのようにぬるい雰囲気にも馴染むことができない。
でも、中学時代にはそうしたグループの一員だったこともあるハツは「人のいる笑い声ばかりの向こう岸も、またそれはそれで息苦しい」のを知っている。笑いたくなくても笑って、他の人に調子を合わせなくてはならない暗黙の掟(おきて)の窮屈さを知っている。だから、よくいえばニュートラル、悪くいえばどっちつかずの状態にあるハツ。それゆえに、自分より一層他者と交わらず、オリチャンという幻想の中に閉じこもっているにな川が気になって仕方なくなってしまうのだ。
でも、それは“好き”という感情とは違う。オリチャンのラジオ番組を、「この方が耳元で囁(ささや)かれてる感じがするから」と、片耳イヤホンで聞くにな川の「この、もの哀しく丸まった、無防備な背中を蹴りたい。痛がるにな川を見たい」という欲望に耐えきれず、凄まじい力で蹴り倒すハツ。一緒にオリチャンの初コンサートに行き、地震が起こればいい、地震が起きたら自分がオリチャンを助けるんだという妄想を口走りながらも、しかし、絶対に地震など起こらないことも分かっているにな川が絶望的な表情を見せれば「にな川がさびしい。彼を可哀相と思う気持ちと同じ速度で、反対側のもう一つの激情に引っぱられていく。にな川の傷ついた顔を見たい。もっとかわいそうになれ」と思ってしまうハツ。
勉強ができるわけじゃない。ルックスがいいわけじゃない。何か特技があるわけでもない。だから、独りとはいっても、それは孤高の存在なんてカッコイイものではなくて、クラスのお荷物的存在としての独り。ハツはそんな自分の情けない立場をよく知っている。ところが、にな川ときたら、自分以上にクラスメートから異物扱いを受けているのに、意にも介さない。オリチャンさえいれば満足なのだ。オリチャンのグッズに囲まれていれば幸福なのだ。そんなにな川に対する共感と苛立ちと、ほんのわずかな羨望と――。
一歩間違えば陰惨な、しかも哀しいくらい低レベルないじめに向かってしまいそうなそうした心象を、綿矢さんは簡単に決着させることなく、丁寧に、でもくどくはない、どちらかといえば軽いユーモラスな筆致で描いていく。そして、ハツとにな川の関係性を開いたまま、物語を閉じる。一九歳にしか書けない、けれどフツーの一九歳には決して書くことができない。これは新しい才能の開花を告げる慶賀の一冊なのだ。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
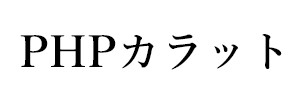
PHPカラット(終刊) 2004年1月号
ALL REVIEWSをフォローする





































