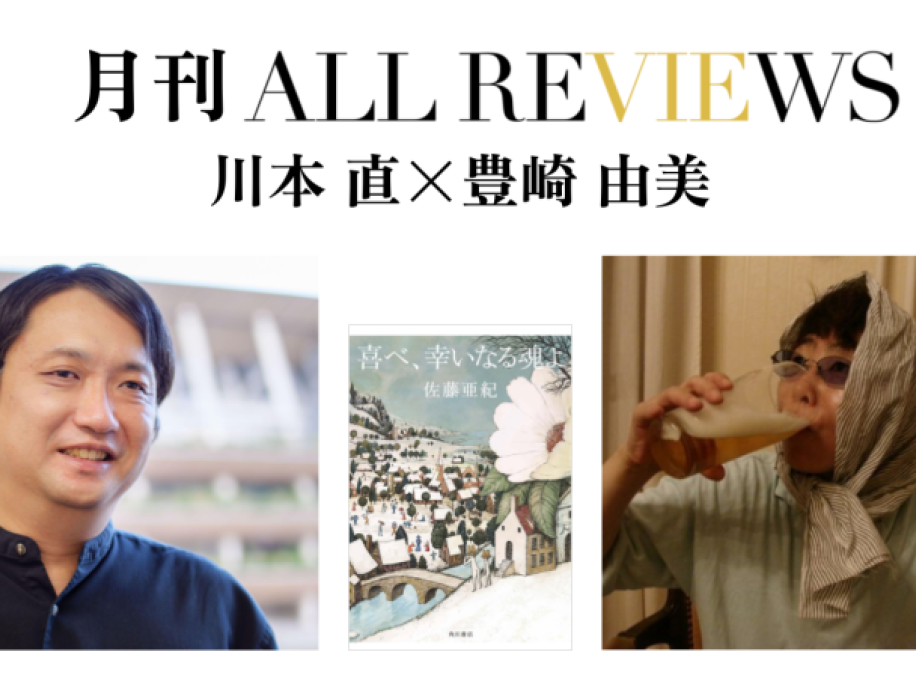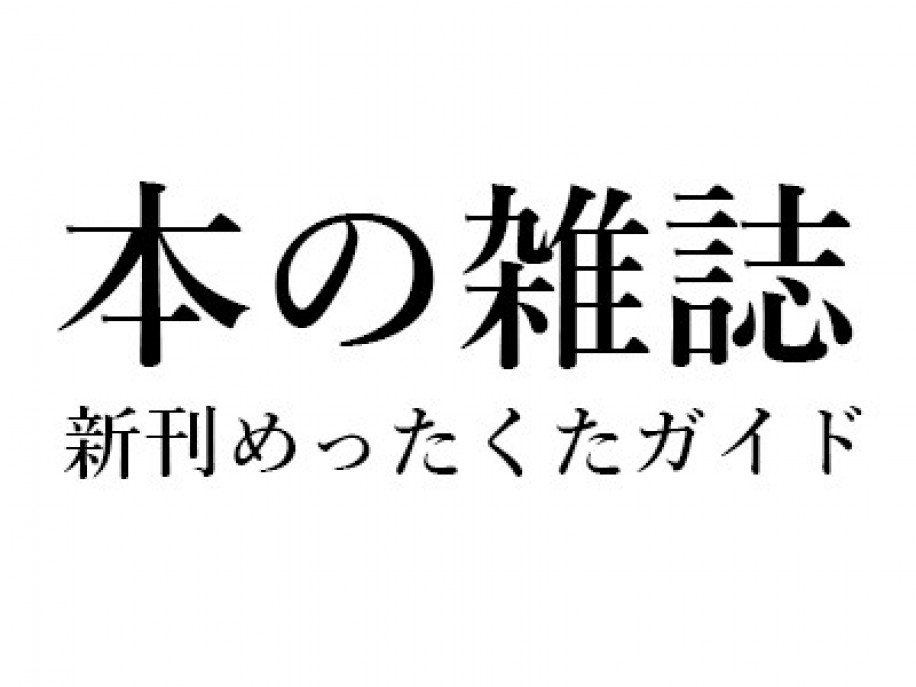書評
『天使』(文藝春秋)
佐藤亜紀が『バルタザールの遍歴』という恐るべき傑作をもってデビューした時の昂揚は今もよく覚えている。同世代の、真に瞠目すべき作家が現れた、その悦び。以降、全ての小説を書店に並んだその日に購入したのは、わたしの本読み人生における自慢であり、誇りなんである。
スピードと効率を金科玉条とするドロモロジー(速度体制)によって、追い立てられ、狩られ、絶滅するしかなかった旧世界の高貴な人々と高潔な精神。佐藤氏は、そのかくも美しく哀しい落日の光景を、深い教養と批評眼、抑制の効いた端正なタッチで描く。そして、それら馥郁(ふくいく)たる香りを湛えたコニャックのような作品は、『世界がもし100人の村だったら』というビールですらない発泡酒のごとき本がバカ売れする現代ニッポンでは、悲しむべきかな、人口に膾炙(かいしゃ)することがない。生まれるべき時代と場所を間違えた作家なのだ。が、それは作家の責任にあらず。ジャンクフードに馴れきった味覚音痴が多いせいなのだ。
というわけで、最新作『天使』の紹介を(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は2003年)。主人公は天賦の“感覚”を持つ青年ジェルジュで、舞台は第一次世界大戦下のヨーロッパ。オーストリアの諜報活動を指揮する顧問官に拾われ、その配下となるべく教育を施されるジェルジュの成長と、感覚を自在に操ることで相手の考えを読んだり、動かしたりできる異能者たちのサイキック・ウォーズを描いた、これは冒険活劇小説にして、スパイ小説にして、ビルドゥングスロマンにして、ピカレスクロマンにして、貴種流離譚(きしゅりゅうりたん)にして、斜陽小説にして、SF小説でもあるという読みどころ満載の作品だ。時に自分自身をも傷つけずにはおかないほど鋭敏な感覚を持った“選ばれし者”の深い孤独と、それゆえ、しっくり合った外套のように身についてしまったニヒリズム。憂愁(ゆうしゅう)すらはねつけるジェルジュの硬質な人物造型がまずは魅惑的だ。彼にまつわる出生の秘密、天使のような羽を持つ貴婦人との秘められた情事、誕生する新たな生命――どうしたって続編を期待せずにはいられなくなる巧妙なストーリー展開にも心躍らされる。
そして、最大の読みどころが超能力者同士の感覚を武器にした戦いの描写。「空気の中で何かが膨れ上がり、窓の硝子が震えて、止った。メザーリが虚無の仮装を脱ぎ捨てたのだ。完全に統御された力が、波紋ひとつ広げることなく辺りに満ちた。死の翼が開くのを見るようだった」。
物語の最後に用意された宿敵メザーリとの死闘。息を呑むほどの迫力と緊迫感に溢れた静かな、しかし、読んでいるこちらにまで苦痛が伝わるほどリアルな描写になっている。感覚という目には見えないものを、必要最小限の表現で十全に描き切る。筆才が活字となって目に突き刺さる快感に打ち震えるシーンなのだ。そろそろ、時代と場所のほうが佐藤亜紀という器に合わせてしかるべきだろう。才能の遇し方を知る程度の礼儀は持ち合わせたいものだ。
【この書評が収録されている書籍】
スピードと効率を金科玉条とするドロモロジー(速度体制)によって、追い立てられ、狩られ、絶滅するしかなかった旧世界の高貴な人々と高潔な精神。佐藤氏は、そのかくも美しく哀しい落日の光景を、深い教養と批評眼、抑制の効いた端正なタッチで描く。そして、それら馥郁(ふくいく)たる香りを湛えたコニャックのような作品は、『世界がもし100人の村だったら』というビールですらない発泡酒のごとき本がバカ売れする現代ニッポンでは、悲しむべきかな、人口に膾炙(かいしゃ)することがない。生まれるべき時代と場所を間違えた作家なのだ。が、それは作家の責任にあらず。ジャンクフードに馴れきった味覚音痴が多いせいなのだ。
というわけで、最新作『天使』の紹介を(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は2003年)。主人公は天賦の“感覚”を持つ青年ジェルジュで、舞台は第一次世界大戦下のヨーロッパ。オーストリアの諜報活動を指揮する顧問官に拾われ、その配下となるべく教育を施されるジェルジュの成長と、感覚を自在に操ることで相手の考えを読んだり、動かしたりできる異能者たちのサイキック・ウォーズを描いた、これは冒険活劇小説にして、スパイ小説にして、ビルドゥングスロマンにして、ピカレスクロマンにして、貴種流離譚(きしゅりゅうりたん)にして、斜陽小説にして、SF小説でもあるという読みどころ満載の作品だ。時に自分自身をも傷つけずにはおかないほど鋭敏な感覚を持った“選ばれし者”の深い孤独と、それゆえ、しっくり合った外套のように身についてしまったニヒリズム。憂愁(ゆうしゅう)すらはねつけるジェルジュの硬質な人物造型がまずは魅惑的だ。彼にまつわる出生の秘密、天使のような羽を持つ貴婦人との秘められた情事、誕生する新たな生命――どうしたって続編を期待せずにはいられなくなる巧妙なストーリー展開にも心躍らされる。
そして、最大の読みどころが超能力者同士の感覚を武器にした戦いの描写。「空気の中で何かが膨れ上がり、窓の硝子が震えて、止った。メザーリが虚無の仮装を脱ぎ捨てたのだ。完全に統御された力が、波紋ひとつ広げることなく辺りに満ちた。死の翼が開くのを見るようだった」。
物語の最後に用意された宿敵メザーリとの死闘。息を呑むほどの迫力と緊迫感に溢れた静かな、しかし、読んでいるこちらにまで苦痛が伝わるほどリアルな描写になっている。感覚という目には見えないものを、必要最小限の表現で十全に描き切る。筆才が活字となって目に突き刺さる快感に打ち震えるシーンなのだ。そろそろ、時代と場所のほうが佐藤亜紀という器に合わせてしかるべきだろう。才能の遇し方を知る程度の礼儀は持ち合わせたいものだ。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
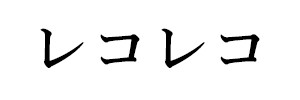
レコレコ(終刊) 2003年1-2月号
ALL REVIEWSをフォローする