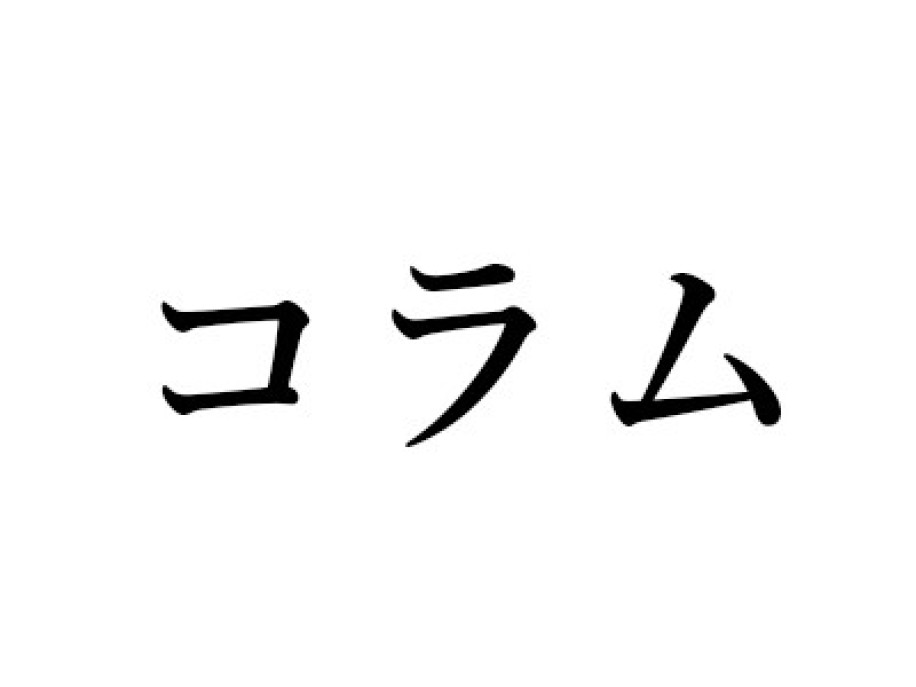書評
『龍宮』(文藝春秋)
くっきりはっきり輪郭つけたがる人ってつまらないなあと思う。「男だから」「女だから」「年寄りだから」「金持ちだから」「チビだから」「A型だから」「乙女座だから」――だからナニッ、思わず舌打ちしてしまいそうになる。そんな風に自分や相手を枠の中に閉じこめて、何が楽しいんだろう、どう安心できるのだろう、どんな展望があるのだろう。
そういう四方を壁に囲まれたように堅苦しい世界の外側にいる作家の代表が、川上弘美なのだと思う。男と女、親と子、あの世とこの世、年寄りと若者、何処(どこ)かと此処(ここ)、いつかと今、あなたとわたし等々。多くの人がよく考えもせずに安易に一線を引いてしまいがちな境界を、川上さんは柔らかな笑みを浮かべながら、ひょいっと飛び越えていってしまう。いや、飛び越えるというよりは溶かしてしまうと云ったほうが正確だろうか。しなやかな心と、呪術のごとき力を備えた文体によって。
たとえば表題作。これは、一四歳の頃から霊言を口にするようになり、以来、あちらとこちらの世界の境をさまよってきたイトの不思議な生涯を、曾孫の「私」が代わりに語った物語だ。ところがっ! 実はといえば、そんなさもわかったような要約を拒むのが、この作品の素晴らしさの所以(ゆえん)なのである。物語の大枠だけを取り出した途端、たちまちはじけ散ってしまう面白さの粋。こぼれ落ちていってしまう独特の雰囲気。それはなぜかといえば、川上さんの文章そのものが、まるでイトの霊言のような力を秘めているからだ。太古の昔から口承によって語りつぎ歌いつがれてきた伝承文学のように、直接伝えることで相手に言霊(ことだま)が乗りうつっていく、そういうタイプの小説なのである。
考えてみれば、わたしのような書評家は、当たり前のように粗筋紹介という形で作品の輪郭を明確にしたがるけれど、本当に凄い小説はそんなことでは決して魅力を露(あらわ)にしない。要約なんて壁で到底囲いこめるもんじゃない。つまり――。人間の世界に馴染めずプラプラしている大酒のみでスケベエな蛸(たこ)(「北斎」)、台所に棲みついた小さな神様が見える万引き癖のある不倫主婦(「荒神」)、気力をなくした人間を鉤爪(かぎづめ)に引っかけて拾ってくる異形のサラリーマン(「鼴鼠(もぐら)」)、四〇〇歳の先祖に恋する老女(「島崎」)、男から男に譲り渡された末、今は世田谷で主婦をやっている海から上がってきた女(「海馬」)なんて要約では、その本性を少しも明らかにしてくれない作家なのだ、川上弘美は。
本書には、この世の者ならぬ存在が当たり前のように生きたり死んだりする、この世ならぬ世界が広がっている。どの物語もごく短いのに、奥行きはとても深い。読みながら奈落に引き込まれていくような目眩(めまい)を覚えてしまうほどに。そうして、やがてページを繰っていくうちに、この世の者ならぬ存在やこの世ならぬ世界が、あたかも以前からずっとそこに在ったかのごとく思われてくるのだ。「女だから」云々と、つまらない境界を気にさせられることが多い自分の窮屈な居場所から、ほんの少しだけ解放されて、昼寝から目覚めた猫みたいに「うぅ~ん」と大きく伸びをしてみたくなるのだ。
要約という壁の中に囲いこまれず、「~だから」というある種の言い訳や諦めを伴った境界線からも自由で、どこからかやって来る物語を言霊のこもった文章で紡ぎ出す。それこそが、小説家という現世の本筋からはみ出した場所で遊ぶ者の本領だろう。でも、その本領を発揮できる才能は少ない。つまり、川上弘美は稀少な語部(かたりべ)なのだ。現実と地続きで読みやすい『センセイの鞄』はとてもいい小説だけど、異界をこちらの世界と溶け合わせる路線の作品の魅力もまた格別。八つの物語を収めた『龍宮』は、それを味わうことのできる絶好の一冊なのだ。
【この書評が収録されている書籍】
そういう四方を壁に囲まれたように堅苦しい世界の外側にいる作家の代表が、川上弘美なのだと思う。男と女、親と子、あの世とこの世、年寄りと若者、何処(どこ)かと此処(ここ)、いつかと今、あなたとわたし等々。多くの人がよく考えもせずに安易に一線を引いてしまいがちな境界を、川上さんは柔らかな笑みを浮かべながら、ひょいっと飛び越えていってしまう。いや、飛び越えるというよりは溶かしてしまうと云ったほうが正確だろうか。しなやかな心と、呪術のごとき力を備えた文体によって。
たとえば表題作。これは、一四歳の頃から霊言を口にするようになり、以来、あちらとこちらの世界の境をさまよってきたイトの不思議な生涯を、曾孫の「私」が代わりに語った物語だ。ところがっ! 実はといえば、そんなさもわかったような要約を拒むのが、この作品の素晴らしさの所以(ゆえん)なのである。物語の大枠だけを取り出した途端、たちまちはじけ散ってしまう面白さの粋。こぼれ落ちていってしまう独特の雰囲気。それはなぜかといえば、川上さんの文章そのものが、まるでイトの霊言のような力を秘めているからだ。太古の昔から口承によって語りつぎ歌いつがれてきた伝承文学のように、直接伝えることで相手に言霊(ことだま)が乗りうつっていく、そういうタイプの小説なのである。
考えてみれば、わたしのような書評家は、当たり前のように粗筋紹介という形で作品の輪郭を明確にしたがるけれど、本当に凄い小説はそんなことでは決して魅力を露(あらわ)にしない。要約なんて壁で到底囲いこめるもんじゃない。つまり――。人間の世界に馴染めずプラプラしている大酒のみでスケベエな蛸(たこ)(「北斎」)、台所に棲みついた小さな神様が見える万引き癖のある不倫主婦(「荒神」)、気力をなくした人間を鉤爪(かぎづめ)に引っかけて拾ってくる異形のサラリーマン(「鼴鼠(もぐら)」)、四〇〇歳の先祖に恋する老女(「島崎」)、男から男に譲り渡された末、今は世田谷で主婦をやっている海から上がってきた女(「海馬」)なんて要約では、その本性を少しも明らかにしてくれない作家なのだ、川上弘美は。
本書には、この世の者ならぬ存在が当たり前のように生きたり死んだりする、この世ならぬ世界が広がっている。どの物語もごく短いのに、奥行きはとても深い。読みながら奈落に引き込まれていくような目眩(めまい)を覚えてしまうほどに。そうして、やがてページを繰っていくうちに、この世の者ならぬ存在やこの世ならぬ世界が、あたかも以前からずっとそこに在ったかのごとく思われてくるのだ。「女だから」云々と、つまらない境界を気にさせられることが多い自分の窮屈な居場所から、ほんの少しだけ解放されて、昼寝から目覚めた猫みたいに「うぅ~ん」と大きく伸びをしてみたくなるのだ。
要約という壁の中に囲いこまれず、「~だから」というある種の言い訳や諦めを伴った境界線からも自由で、どこからかやって来る物語を言霊のこもった文章で紡ぎ出す。それこそが、小説家という現世の本筋からはみ出した場所で遊ぶ者の本領だろう。でも、その本領を発揮できる才能は少ない。つまり、川上弘美は稀少な語部(かたりべ)なのだ。現実と地続きで読みやすい『センセイの鞄』はとてもいい小説だけど、異界をこちらの世界と溶け合わせる路線の作品の魅力もまた格別。八つの物語を収めた『龍宮』は、それを味わうことのできる絶好の一冊なのだ。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
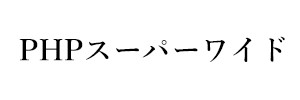
PHPスーパーワイド(終刊) 2002年11月号
ALL REVIEWSをフォローする