書評
『若かった日々』(新潮社)
子どもの頃、よく考えませんでしたか? 「なんで、自分は自分なんだろう」とか、「なんで、わたしは今ここにいるんだろう」とか。ところが大抵の人は成長するにつれ、そういうことを考えなくなっちゃう。多分、知識や常識が刷り込まれて目が曇るからなんです。まっさらな気持ちで世界や自分と対峙できなくなる上に、忙しくて考えてる暇もなくなって……。そうして、わたしたちは子どもの頃に見ていた〈不揃いで、ぼやけていて、キラキラと光って、不思議と美しい世界〉を失って、ハイビジョン映像みたいにクリアなんだけど、まるで誰かに見せられているかのように嘘臭い世界の住人になっていくのかもしれません。
でも、いざ“来し方”を振り返ってみようとしても、ほんの少し向こうすら靄(もや)がかかってじれったい。子どもの頃、どんなことが怖くて、どんなことに笑ったのか、若かった頃、どんなことに怯えて、どんなことを夢みたのか。今いる自分がどうやって形作られて、ここまでどうやってたどりついたのか。断片的なシーンや感情がぽつんぽつんと浮かぶだけで、一向につながっていかない! 愕然とするわたしに手渡された一冊が、レベッカ・ブラウンの『若かった日々』だったのです。
生まれつきの極端な斜視によって自分の中をのぞきこむことを宿命づけられた幼い頃。離婚した父親に対する複雑な思いと確執、そして受容に至るまでの長い道のり。母親に対する曇りも迷いもない愛情。レズビアンであることの目覚め。煙草を狂言回しにして綴られる家族の肖像。あらがいがたい死の誘惑――。ここにはレベッカ・ブラウンという一人の人間の来し方があります。それはレベッカ個人の経験であって、わたしのそれではありません。にもかかわらず、優れた文学がそうであるように、他者の物語を読むという体験が、いつしか自分の生を振り返ることに自然と重なっていく、そんな共感力に満ちています。読むことで自分自身の曖昧模糊としたかつてが、時々に覚えた強い感情を伴って少しずつ蘇ってくる、その喚起力の強さに心打たれる連作短篇集なのです。
たとえば、「ナンシー・ブース、あなたがどこにいるにせよ」という一篇。ガールスカウトのキャンプで思春期の〈私〉は、水泳を教える若い女性と出会います。他の子とはちょっと違うことにとまどいを覚え始めていた〈私〉に、〈この世界には私が生きうる、普通とは違うほかの生き方が――どんな生き方かはまだ神秘に包まれていたけれど――あるのだということを〉教えてくれる年上の女性。そんなナンシー・ブースのような心優しく忍耐強い導き手が、あなたの、わたしの、若い日々にもいなかったでしょうか。あるいは、かつてあんなにも屈折していた親に対する思いが、〈父の死から遠ざかれば遠ざかるほど、そして、私が父に求めた不可能な望みから醒めれば醒めるほど、私は父にだんだん共感できるようになっていく〉というふうに変わっていった経験を持つ人は、果たして少数派でしょうか。
若かった日々。読後、ぼんやりとしか思い出せないあの頃に焦点を合わせようと、かつてと今をつなぐ時間の流れをたどろうとしている自分に気づきます。〈自分が覚えていることを私は信じる。/自分が見たこと、したことが時を超えた場で続いていると、それがいまもあると私は信じる。/いまもあることは起きるのだと、これからもまた起きるのだと私は信じる。/自分に訪れた幻視を、自分に与えられた肉体を私は信じる。/自分が欲したことが愛として形を与えられたと私は信じる〉という言葉に後押しされて、来し方に向き合おうとする自分に気づきます。この本はレベッカからあなたへの“記憶の贈り物”なのです。
【この書評が収録されている書籍】
でも、いざ“来し方”を振り返ってみようとしても、ほんの少し向こうすら靄(もや)がかかってじれったい。子どもの頃、どんなことが怖くて、どんなことに笑ったのか、若かった頃、どんなことに怯えて、どんなことを夢みたのか。今いる自分がどうやって形作られて、ここまでどうやってたどりついたのか。断片的なシーンや感情がぽつんぽつんと浮かぶだけで、一向につながっていかない! 愕然とするわたしに手渡された一冊が、レベッカ・ブラウンの『若かった日々』だったのです。
生まれつきの極端な斜視によって自分の中をのぞきこむことを宿命づけられた幼い頃。離婚した父親に対する複雑な思いと確執、そして受容に至るまでの長い道のり。母親に対する曇りも迷いもない愛情。レズビアンであることの目覚め。煙草を狂言回しにして綴られる家族の肖像。あらがいがたい死の誘惑――。ここにはレベッカ・ブラウンという一人の人間の来し方があります。それはレベッカ個人の経験であって、わたしのそれではありません。にもかかわらず、優れた文学がそうであるように、他者の物語を読むという体験が、いつしか自分の生を振り返ることに自然と重なっていく、そんな共感力に満ちています。読むことで自分自身の曖昧模糊としたかつてが、時々に覚えた強い感情を伴って少しずつ蘇ってくる、その喚起力の強さに心打たれる連作短篇集なのです。
たとえば、「ナンシー・ブース、あなたがどこにいるにせよ」という一篇。ガールスカウトのキャンプで思春期の〈私〉は、水泳を教える若い女性と出会います。他の子とはちょっと違うことにとまどいを覚え始めていた〈私〉に、〈この世界には私が生きうる、普通とは違うほかの生き方が――どんな生き方かはまだ神秘に包まれていたけれど――あるのだということを〉教えてくれる年上の女性。そんなナンシー・ブースのような心優しく忍耐強い導き手が、あなたの、わたしの、若い日々にもいなかったでしょうか。あるいは、かつてあんなにも屈折していた親に対する思いが、〈父の死から遠ざかれば遠ざかるほど、そして、私が父に求めた不可能な望みから醒めれば醒めるほど、私は父にだんだん共感できるようになっていく〉というふうに変わっていった経験を持つ人は、果たして少数派でしょうか。
若かった日々。読後、ぼんやりとしか思い出せないあの頃に焦点を合わせようと、かつてと今をつなぐ時間の流れをたどろうとしている自分に気づきます。〈自分が覚えていることを私は信じる。/自分が見たこと、したことが時を超えた場で続いていると、それがいまもあると私は信じる。/いまもあることは起きるのだと、これからもまた起きるのだと私は信じる。/自分に訪れた幻視を、自分に与えられた肉体を私は信じる。/自分が欲したことが愛として形を与えられたと私は信じる〉という言葉に後押しされて、来し方に向き合おうとする自分に気づきます。この本はレベッカからあなたへの“記憶の贈り物”なのです。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
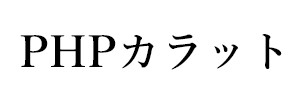
PHPカラット(終刊) 2005年2月号
ALL REVIEWSをフォローする



































