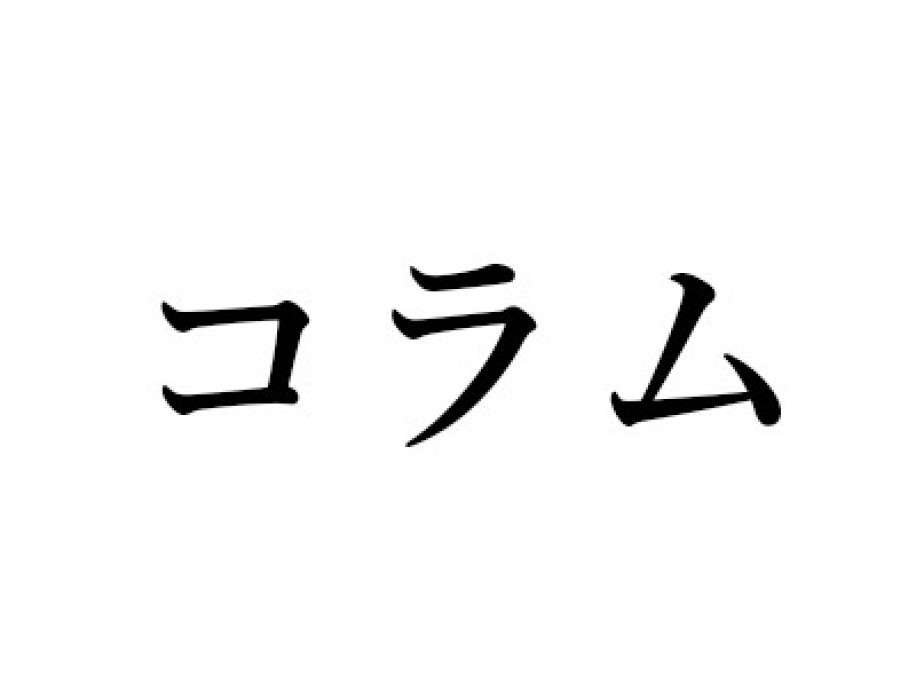本文抜粋
『大衆文化のなかの虫たちー文化昆虫学入門』(論創社)
古典作品や伝統文化のなかで論じられてきた従来の学問と異なり、大衆文化・サブカルチャーに特化した、目からうろこの文化昆虫学入門。明治・大正期のペット昆虫から、現代の特撮やアニメ・ゲーム、食品や身の回り品のモチーフとなった昆虫、二次元世界の文化蟬学まで、ユニークな研究成果を一挙公開!
以下、著者独特の主張と、興味深い調査内容を少しだけ紹介すると…
確かに世界に類を見ない昆虫文化が日本にあると言えるわけだが、つまるところ日本人の昆虫に対する愛情とは、自然生物として昆虫を尊重していると言うよりは、オモチャへの執着愛と言った方が正確である。和歌や短歌に昆虫を詠み込む創作活動は大層高尚な芸術文化と思いがちだが、何のことはない。余暇的文芸に必要な題材即ちオモチャである。一般的な日本人は決して保全生態学的な意味で昆虫を取り立てて尊重する民族ではない。
現在ホタルを買おうと思い立ち、夜店や一般ペットショップに足を運んだとしても大概は徒労に終わる。売っているはずもない。どうしても買いたければ極めて特殊な専門店に行くしかない。しかし、近代期の日本では縁日や街中で普通にホタルを買うことができた。では、ホタルは1頭如何ほどの価格で売られていたのか?
表(略)は拙文「明治百五拾年 近代日本ホタル売買・放虫史」で示した近代期ホタル価格表を一部改変したものである。比較対象としてスズムシとその年1月時点の東京朝日新聞1部の価格を併記した。当時のホタルがスズムシと比べると大幅に安価であったことは一目瞭然である。なお、一部の価格が小数点以下なのは厘(10厘=1銭)を銭の単位に変換したこと、あるいは原記事が「△頭〇銭」のように複数個体の価格表示であり、1頭当たりの価格に換算したが故である。
平成令和の現在、夏から初秋にホームセンター等で売っているスズムシはおおよそ1頭数百円だ。一方、同じくホタルを取り扱う専門店のウェブサイトをいくつか覗くと、ゲンジボタルやヘイケボタルも1頭数百円程度の価格が付けられていることがわかった。つまり昨今はスズムシとホタルの値段に大差はない。
次に現在大手新聞の朝刊が1部150円前後なので、スズムシは新聞1部の数倍程度の値段なわけだが、これは近代期も同様である。つまり、スズムシの商品としての価値は明治時代も現代も大きく変わっていない。逆に近代期のホタルの価格はその年の新聞代と比較すると非常に安価であることがわかる。現在の貨幣価値で言うならせいぜい数十円以下と考えればよいだろう。明治22年のホタルは1匹1厘(=0・1銭)。新聞1部のカネでホタルが10頭買えると言うのは、現在では到底ありえない安値である。近代期のホタルが如何に安かったかが窺い知れる。
縁日で売られていた鳴く虫は養殖個体と自然個体の両方であった、と前章で述べた。では、商品のホタルの出所はいずこであったか。明治前半期、市場に出回っていたホタルは甲州、武州大宮、宇都宮、目黒池上などで捕られた関東周辺の野外個体が主であった。一方、大正半ばには近江守山でホタルの人工増殖の研究が始まり、ほどなくして養殖技術が確立した。やがて東京や大阪の市場に十万単位の守山産養殖個体が全国の野外ホタルとともに出回るようになったのである。
[書き手]保科英人(ほしな・ひでと)
福井大学准教授・農学博士。専門は文化昆虫学、科学史、土壌性甲虫分類学。
以下、著者独特の主張と、興味深い調査内容を少しだけ紹介すると…
どうやら日本人の昆虫愛はオモチャへの愛と同質である
「カワイイは正義」との人類の普遍的価値観からすれば、抱擁の対象から昆虫が外されるのは当然だ。ここで改めて「日本人は虫好き」との根拠を思い返してもらいたい。奈良平安期の古典や和歌、武家政権時代の昆虫をモチーフとした武具、江戸市中のスズムシ売り、昆虫に物の哀れを見顕す俳句。現代のカブトムシペット産業、ムシキングに代表される昆虫ゲームの数々、オヤジ趣味と化しつつある昆虫採集。確かに世界に類を見ない昆虫文化が日本にあると言えるわけだが、つまるところ日本人の昆虫に対する愛情とは、自然生物として昆虫を尊重していると言うよりは、オモチャへの執着愛と言った方が正確である。和歌や短歌に昆虫を詠み込む創作活動は大層高尚な芸術文化と思いがちだが、何のことはない。余暇的文芸に必要な題材即ちオモチャである。一般的な日本人は決して保全生態学的な意味で昆虫を取り立てて尊重する民族ではない。
近代日本のホタルのお値段と出所
現在ホタルを買おうと思い立ち、夜店や一般ペットショップに足を運んだとしても大概は徒労に終わる。売っているはずもない。どうしても買いたければ極めて特殊な専門店に行くしかない。しかし、近代期の日本では縁日や街中で普通にホタルを買うことができた。では、ホタルは1頭如何ほどの価格で売られていたのか?
表(略)は拙文「明治百五拾年 近代日本ホタル売買・放虫史」で示した近代期ホタル価格表を一部改変したものである。比較対象としてスズムシとその年1月時点の東京朝日新聞1部の価格を併記した。当時のホタルがスズムシと比べると大幅に安価であったことは一目瞭然である。なお、一部の価格が小数点以下なのは厘(10厘=1銭)を銭の単位に変換したこと、あるいは原記事が「△頭〇銭」のように複数個体の価格表示であり、1頭当たりの価格に換算したが故である。
平成令和の現在、夏から初秋にホームセンター等で売っているスズムシはおおよそ1頭数百円だ。一方、同じくホタルを取り扱う専門店のウェブサイトをいくつか覗くと、ゲンジボタルやヘイケボタルも1頭数百円程度の価格が付けられていることがわかった。つまり昨今はスズムシとホタルの値段に大差はない。
次に現在大手新聞の朝刊が1部150円前後なので、スズムシは新聞1部の数倍程度の値段なわけだが、これは近代期も同様である。つまり、スズムシの商品としての価値は明治時代も現代も大きく変わっていない。逆に近代期のホタルの価格はその年の新聞代と比較すると非常に安価であることがわかる。現在の貨幣価値で言うならせいぜい数十円以下と考えればよいだろう。明治22年のホタルは1匹1厘(=0・1銭)。新聞1部のカネでホタルが10頭買えると言うのは、現在では到底ありえない安値である。近代期のホタルが如何に安かったかが窺い知れる。
縁日で売られていた鳴く虫は養殖個体と自然個体の両方であった、と前章で述べた。では、商品のホタルの出所はいずこであったか。明治前半期、市場に出回っていたホタルは甲州、武州大宮、宇都宮、目黒池上などで捕られた関東周辺の野外個体が主であった。一方、大正半ばには近江守山でホタルの人工増殖の研究が始まり、ほどなくして養殖技術が確立した。やがて東京や大阪の市場に十万単位の守山産養殖個体が全国の野外ホタルとともに出回るようになったのである。
[書き手]保科英人(ほしな・ひでと)
福井大学准教授・農学博士。専門は文化昆虫学、科学史、土壌性甲虫分類学。
ALL REVIEWSをフォローする