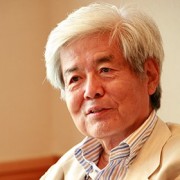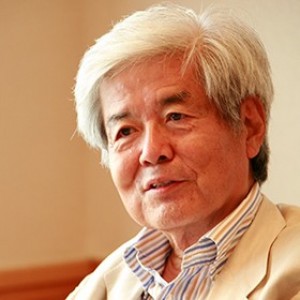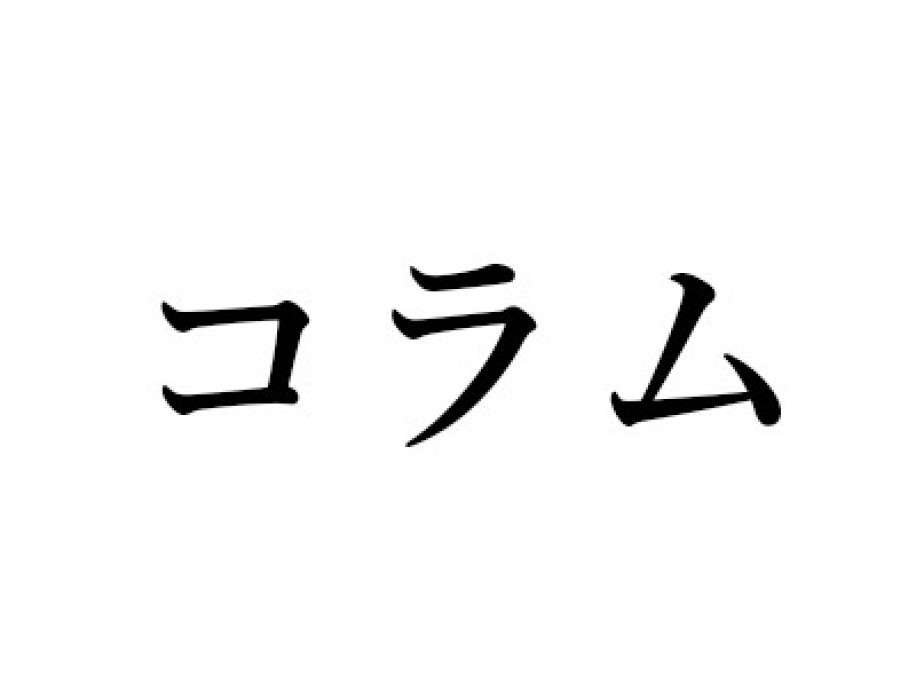書評
『チョウが語る自然史―南九州・琉球をめぐって―』(南方新社)
なぜ、そこに生涯かけ追い求め
南九州から琉球にかけての、チョウから見た自然の記述である。著者は地元の鹿児島で高校教師を長く務め、その傍らチョウの調査に励み、日本蝶類学会会長であった。現在八十六歳、評者の四年先輩にあたる。チョウを調べる人生の総まとめ、畢生(ひっせい)の労作と言うべきであろう。この書評欄で普通に紹介するような本ではない。多くの人にとって、ごく特殊な話題と感じられるだろうし、文体はゴツゴツして、著者の鹿児島訛りがそのまま聞こえてくるようである。地方創生が広く言われるこの時代だが、ひたすら「チョウはなぜここにいるのか、なぜいないのか」を生涯にわたって地元で追い続けた人生を、どれだけの人が真に共感し、理解するであろうか。
全体は三部構成で、第一部は「南九州と鹿児島県本土」、第二部は「南西諸島」、第三部は「ヒトが来た」である。最初の二部が分けられているのは当然で、世界的な生物分布からすれば、鹿児島県本土からトカラ列島の一部まではいわゆる旧北区、それ以南は東洋区に属すからである。第三部は自然に対するヒトの影響がいかに深刻かを論じ、今後どうすべきかまで、とくに教育の視点から語っている。
第一部序章はアサギマダラの移動から始まる。このチョウは春に南から発生して北上し、秋には北で発生したものが南下する。琉球生まれのチョウが、時には長野や関東まで、千キロを超えて移動する。この事実が判明したのは著者らの努力によるところが大きい。アサギマダラの翅(はね)にマークをつけて放蝶する。マークされた個体を誰かがどこかで再度捕獲すれば、移動の事実が判明する。まだネットがない時代に、著者は全国の同好者に呼び掛け、チョウの移動が判明していったのである。
自然史と題されているように、じつは著者はチョウに関する事実だけを記述しているのではない。むしろ主要な部分を占めているのは、南九州から南西諸島に至る、各領域の地史である。本書のいたるところに、鹿児島県だけではなく、アジア全体を含めた地図が描かれている。昆虫の分布が地史の影響を強く受けていることは常識化されていない。ある虫がある地域にいたり、いなかったりする。その背景には、場合によっては千万年の桁の地面の歴史、すなわち地史が関係している。そうした地史を、地元の人があんがい知らなかったりする。というより、まったく無知だと断定したくなることも多い。
とくに日本列島の場合、世界で唯一と言っていい、四つものプレートがぶつかる位置にある。そのため列島の構造は地史的に変化が著しく、さらに多くの火山活動が生じ、地表への影響、さらにはチョウや他の生物への影響が著しい。富士山が日本を代表するのは決して偶然ではない。鹿児島県では桜島に見られるように、七千三百年前の鬼界カルデラの噴火による火砕流の影響が今日にも大きく残っている。霧島山や開聞岳があり、北には阿蘇山という巨大火山がある。温泉につかるだけではなく、温泉の存在の意味を時には考えていただきたい。
巻末には丁寧に文献を記す。自然史は小さな事実の大きな積み重ねである。自然史とはなにかという質問に答えたミリアム・ロスチャイルドの言葉を繰り返しておこう。「自然史とは学校で教える教科のようなものではない。人の生き方そのものである」。ミリアムの父チャールズは銀行家であり、ノミの研究者。伯父のライオネル・ワルターは著名なチョウの蒐集家だった。
ALL REVIEWSをフォローする