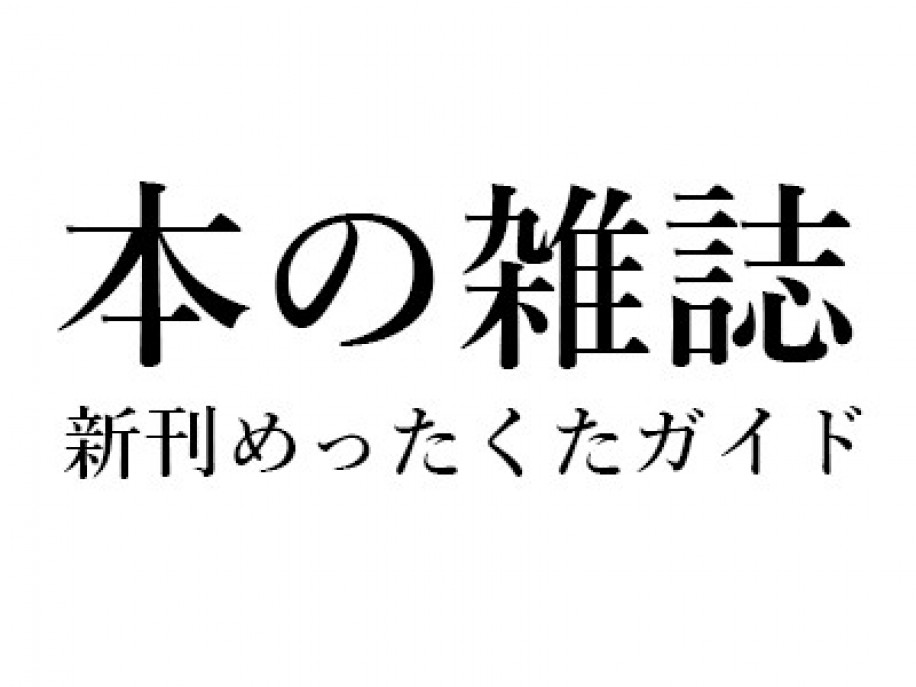書評
『ノーライフキング』(河出書房新社)
ニッポンの文壇村ではほとんど話題にも上がらなかったけれど、一般の小説ファンの間では「読んだ?」「ⅠからⅣまでバージョンがあって、それぞれ結末が違うらしいよ」「でね、主人公たちが死んじゃうVってバージョンがあって、それを買った人は最後まで読むとやっぱ呪われて死んじゃうんだって」などという「噂」が飛び交ったとか飛び交わなかったとか。いとうせいこうの傑作『ノーライフキング』のことである。
空前のヒット商品となったディス・コン(ゲーム機)のゲーム〈ライフキング〉には「呪われた第5のバージョンが存在する」という噂が子どもたちの間を駆けめぐり、大人たちの社会をも混乱に陥れる。自分たちと世界を救うために戦闘を開始する子どもたちの姿を通して「新しいリアル」に迫る――というのがこの物語の骨子だ。
考えてみれば、ファミコンゲームから始まってバーチャル・リアリティーの概念が一般に普及した今と、そんなものは存在すらしなかった過去。それぞれの「リアル」が同じだとは到底思えない。ラストで窓から顔を出した登場人物に「あ~、今日もお山がきれいだ」なんて言わせて物語を完結させる自然主義の文学や演劇がもたらしたリアルが、現代にも通用するはずはないのだ。
この小説の主人公の男の子たちは、前時代の生き物(つまり大人)が強要してくるリアルが、偽のリアルだということを体感している。そして、そこにあるはずなのに大人たちが見ようともしない新しいリアルを真剣に探すことが、今の時代を生き抜くための、たった一つの方法なのだということを理解している。
「ソトニデテミテクダサイ。リアルデスカ?」。ネットワークを通じて情報を交換している北海道の友からそんなメッセージをもらった主人公が、町のあちこちで小石を並べている同年代の子どもたちと出会うシーンが本当に美しい。ゲーム〈ライフキング〉の最後のダンジョン・暗黒迷宮に印されている赤い照明の配列を真似て小石を並べている子どもたち。そして、ライフキングのために自分を犠牲にして散っていく〈ハーフライフ〉に自分をなぞらえて、必要なデータを打ち込んでいく子どもたち。彼らの戦う真摯な姿勢とその凛々(りり)しさに感動しない人は、かつて子どもだったこともなければ、現在だって新しいリアルに感応することもできない鈍感でチープな大人たちに違いない。表現が荒削りという欠点もあるが、本書がわたしたちにとっての試金石ともいうべき新しい書物であることだけは間違いない。
空前のヒット商品となったディス・コン(ゲーム機)のゲーム〈ライフキング〉には「呪われた第5のバージョンが存在する」という噂が子どもたちの間を駆けめぐり、大人たちの社会をも混乱に陥れる。自分たちと世界を救うために戦闘を開始する子どもたちの姿を通して「新しいリアル」に迫る――というのがこの物語の骨子だ。
考えてみれば、ファミコンゲームから始まってバーチャル・リアリティーの概念が一般に普及した今と、そんなものは存在すらしなかった過去。それぞれの「リアル」が同じだとは到底思えない。ラストで窓から顔を出した登場人物に「あ~、今日もお山がきれいだ」なんて言わせて物語を完結させる自然主義の文学や演劇がもたらしたリアルが、現代にも通用するはずはないのだ。
この小説の主人公の男の子たちは、前時代の生き物(つまり大人)が強要してくるリアルが、偽のリアルだということを体感している。そして、そこにあるはずなのに大人たちが見ようともしない新しいリアルを真剣に探すことが、今の時代を生き抜くための、たった一つの方法なのだということを理解している。
「ソトニデテミテクダサイ。リアルデスカ?」。ネットワークを通じて情報を交換している北海道の友からそんなメッセージをもらった主人公が、町のあちこちで小石を並べている同年代の子どもたちと出会うシーンが本当に美しい。ゲーム〈ライフキング〉の最後のダンジョン・暗黒迷宮に印されている赤い照明の配列を真似て小石を並べている子どもたち。そして、ライフキングのために自分を犠牲にして散っていく〈ハーフライフ〉に自分をなぞらえて、必要なデータを打ち込んでいく子どもたち。彼らの戦う真摯な姿勢とその凛々(りり)しさに感動しない人は、かつて子どもだったこともなければ、現在だって新しいリアルに感応することもできない鈍感でチープな大人たちに違いない。表現が荒削りという欠点もあるが、本書がわたしたちにとっての試金石ともいうべき新しい書物であることだけは間違いない。
初出メディア

PASO(終刊) 1995年2月号
ALL REVIEWSをフォローする