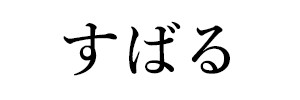書評
『小説禁止令に賛同する』(集英社)
小説と記憶の自由
本作の雑誌掲載と相前後して刊行された本がある。いとうせいこう氏が実際に足を運んだ現地報告の書、『「国境なき医師団」を見に行く』だ。いとうはこの本でハイチ、ギリシャ、フィリピン、ウガンダの現場を報告しているが、それはこんな感じだ。「水が落ちてくる仕掛けの部屋のシャワーを浴び、持っていた手ぬぐいで体を拭き、俺はもう一人の俺のことを考えていた。/そしてその人物なら、インベピ居住区で『風呂に入りたい』と言っていたダウディさんにこの水を分けてあげていたかもしれないと思うと、自分の取材が偽善に思えてならなくなった」ルポを読んでいて、右(ALL REVIEWS事務局注:上)のような記述に遭遇することは稀だろう。取材する自分とそれを冷静に眺める自分。「俺」の二重性はしかし現場の過酷さによって乗り越えられる。取材は続けるしかないし、文章は最後まで書くしかないのだ。「偽善だろうがなんだろうが」終えるのだ。
しかし小説は違う。『小説禁止令に賛同する』という小説(なのだと思う)は、主人公本人は小説ではなく随筆を書いている、と宣言している。小説ではないと書きながらそれが小説として読まれるという韜晦を読者はまず受け入れるのか……。結論を急がず、中身に入ろう。
独房に収監されている「わたし」が主人公。彼は、小冊子『やすらか』に文章を掲載して、読者に話しかける。舞台は二〇三六年の「東端列島」(日本のこと)。列島では一部が高濃度の放射能に汚染され、厳しい言論統制が敷かれ、「小説禁止令」が出されている。「わたし」は小説家だが、「禁止令」に積極的に賛成している。
しかし時代は小説に傾いた。二十一世紀の初頭、「電脳空間での短言板」が世界を席巻し、それが過熱するあまり、利用者は徐々に熱を冷ましてしまう。揺り戻しとして印刷された出版物に人気が集中、人がもう一度、書物へ向かう時代に……。そして「読みやすくて感情を燃え上がらせる稚拙な小説」が「力を持ってしまった」。「わたし」はそれを批判しつづける、というのが基本トーン。ただその後、「東端列島」では小説家の粛清が始まり、「わたし」も不当な形で投獄されてしまう(じつは亡き妻によって密告されたのが原因)……。
この作品には多くの議論すべきポイントが含まれているが、ここではひとまず三つほど挙げておく。一つは、「わたし」が放つ小説への強い批判だ。たとえば「『ああ、そうですね』/と声がする。今、わたしの肩の後ろから呼びかける者がいる」と書けば、そこには誰かがいるような気配が流れ始め、「わずかに小説らしくなる」と、「わたし」は指摘する。いかがわしい、と断ずる。小説の小説らしさを避けたい気持ちが「わたし」にある。それはおそらくいとうせいこうという作家の根本的なスタンスとも重なる部分だろう。
いとうは長い間、小説を書かない期間があった。二十世紀末からの十年以上の空白の時間については、この作品の中でも様々な形で変奏される。いとうが小説を書かなかった時期に没頭したのがチェスで(作中ではカタカナは政府によって禁じられているので「西洋将棋」と書かれる)、チェスの魔力にとりつかれたソシュールやベケット、あるいはデュシャンのことも頻繁に言及される(彼らの名もカタカナ表記できないので、ひどく遠回しな言い方で示される)。小説を書かない、あるいは書けないことの裏側には、小説という作り物を書く自分を批判するもうひとりの自分がいるのは自明で、ここで二重化する「わたし」は、過酷な現実を報告する「俺」とは違い、容易には乗り越えがたい。
二つめのポイントは、かなりの部分を割いて展開される小説論だろう。中上健次の『地の果て 至上の時』や夏目漱石の『行人』といった具体的な小説に即して、人称の問題や語りの孕むスリリングな読みを展開しているパートがある。こうした文芸批評的部分については賛否があるだろうが、この作品を「わたし」は執拗に「随筆」であり「小説」ではない、と言い続けているのだから、その流れの中の記述として読めばいいのだと思う。
三つめのポイントが、二〇二〇年代に発表され世界的に読まれた菫英明の『月宮殿暴走』をめぐる記述。「わたし」は小冊子に『月宮殿暴走』についてかなり詳細に論評するのだが、冊子の編集担当である梁氏からそんな小説は実在しない、という指摘を受ける。とすれば「わたし」がその小説を創作して述べたことになり、「わたし」は小説を書いたことになってしまう。その小説は本当にないのか、ないのにどうして「わたし」はあるものとして書いてしまったのか、そしてシノプシスを記した『月宮殿暴走』は「小説」と呼べるのか……。問いはもう一度、小説とは何かへと差し戻されるのだが、私はむしろここに読みたいと思ったのは、記憶によって物語を再現する行為のほうである。
いとうはたぶん小説が自由に書ける時代は終わる、と思っている。いやすでに終わりつつあると感じているのかも。小説は政権によって不都合な存在であり、弾圧の対象となろう。小説は書けないばかりか、読むことさえままならなくなるだろう。そのとき、私たちにできることは、記憶の中の小説を語ることだけだ。読めないし書けないのであれば、記憶を紐解くしかない。『月宮殿暴走』はその具体例ではないか。そして、この抜粋の面白そうなこと!
最後にひとつ。作品途中にロベルト・ボラーニョの『野生の探偵たち』の冒頭が引用されているが、あの有名な一行目の「はらわたリアリズム」を、カタカナ禁止で表記するとまったく別の書き出しのように読めて、思わず爆笑した。いとうの小説に欠かせない要素、笑いも随所に。
ALL REVIEWSをフォローする