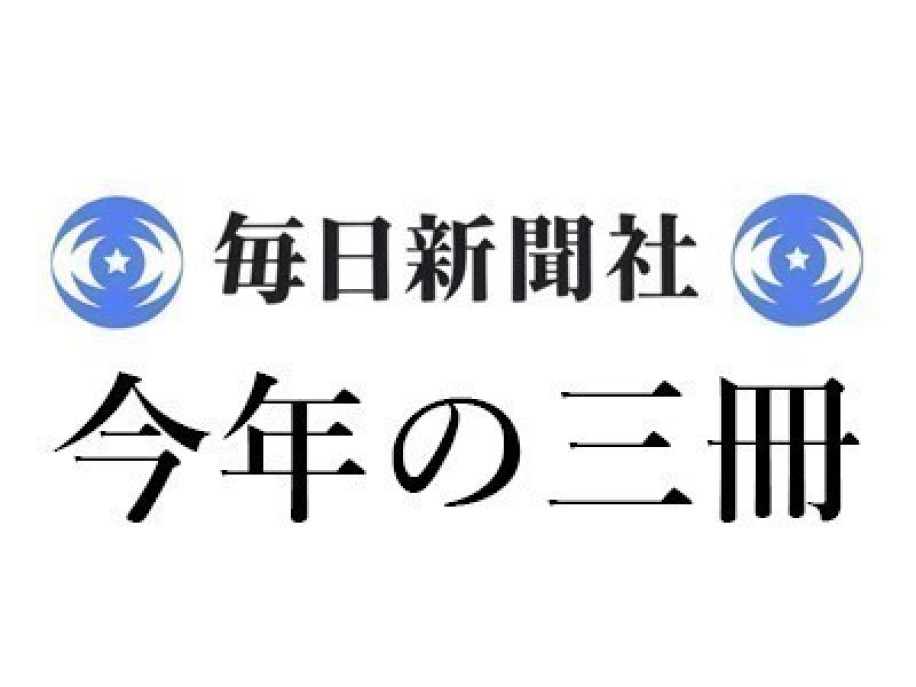書評
『あったとさ』(文藝春秋)
直木賞受賞作『佃島ふたり書房』をきっかけに、出久根達郎さんの世界に出会った人は多いと思う。
「へえっ、こんなおもしろい作家がいたんだ」と私のまわりでも評判だ。きのう、テレビで出久根さんを見ちゃったわ、今度ラジオドラマにもなるんだって、なんて声を聞くと思わず、
「ふっふっふ。私なんか三年前からファンやってるんだからね」と、ちょっと自慢したくなる。
知り合いの編集者から『古本綺譚』というエッセイ集を勧められて読んだのが、始めだった。すっかり虜になってしまった。
古本をめぐるさまざまな物語。話そのものがおもしろいのはもちろんだけれど、それ以上に作者の語り口が魅力的だった。いや、作者の語り口が軽妙だからこそ、話がこんなにおもしろくなるのだろう。
そして、ただ軽妙というだけではない。出久根さんの言葉は、ものすごくちゃんとした日本語、という感じがする。背筋がぴーんとしていて、気持ちがいい。そのうえ、ちょっと古風な味わいがある。
たとえば受賞第一作になる短編集『あったとさ』からひいてみよう。
この最後のところ。さりげないけれど、なかなかこんなふうには言えない。「挨拶した。」と「古本屋だと名のったのである。」の間というのは、日本語がきちんとしていないとうまく飛べない。そしてこういう表現だからこそ、小気味よいリズムが生まれる。「相手に私は古本屋だと挨拶した」では、まるでつまらないだろう。
『あったとさ』に収められた六つの短編のうち「くしゃみ」を除く五編には、それぞれ古本屋さんが登場する。出久根さんは、現実に古本屋さんだ。かつてエッセイを愛読していた私は、うひゃうひゃ笑いながら「小説みたいだなあ」と思っていた。けれど小説のほうを読むと「なるほど。こっちが小説というものだ」と思う(あたりまえだけれど)。
いずれの短編も、読み終えると、ちょっと不思議な気分になる。ありえないようなことが、それこそ「あったとさ」と語られて、知らず知らずその世界に引き込まれてしまうのだ。だから現実の世界に帰ってきたとき、違和感を覚えるのだろう。その瞬間が、またいい。
ただ「冬至の旅」という作品だけは、うまく小説の世界に入っていけなかった。語り手が若い女性なのだ。で、なんとなくその言葉遣いが、おじさんがセーラー服を着ているような感じ、なのです(わぁ、変なたとえでゴメンナサイ)。
ところで、冒頭に私は、三年前からファンをやっていると言った。実は、これがかなり行動派のファンで、会いに行っちゃったこともある。『古本綺譚』を勧めてくれた編集者が、出久根さんを知っていると聞いて、「えー、じゃあ会わせて会わせて。そうだ、出久根さんのお店に遊びに行きましょうよ。私、古本屋さんって大好きなの」とせがんだ。
たしか一九九〇年の暮れも押し迫ったころのことである。彼と二人で、高円寺に出かけて行った。
出久根さんのお店には、たくさんの本たちが「愛されています」という風情で並んでいた。本への愛情が、出久根さんの世界の基本なのだなあ、とあらためて思う。
私たちは大変な歓迎を受け、お宅にあがりこみ、奥さまの手料理までごちそうになった。
あつあつの揚げ物、こっくりの煮物、そして海の幸たっぷりの鍋を囲んでの宴会である。
(いま思い出すと、かなりあつかましいファンだ)
ほんものの出久根さんは、エッセイからの予想を上回るほど、愉快で気さくであたたかい人だった。
直木賞を受賞されたとき、私はあいにく海外にいて知らなかったのだが、帰国するなり母が教えてくれた。
「あなたの大好きな人が、直木賞よ!」
やったね、と思った。
【この書評が収録されている書籍】
「へえっ、こんなおもしろい作家がいたんだ」と私のまわりでも評判だ。きのう、テレビで出久根さんを見ちゃったわ、今度ラジオドラマにもなるんだって、なんて声を聞くと思わず、
「ふっふっふ。私なんか三年前からファンやってるんだからね」と、ちょっと自慢したくなる。
知り合いの編集者から『古本綺譚』というエッセイ集を勧められて読んだのが、始めだった。すっかり虜になってしまった。
古本をめぐるさまざまな物語。話そのものがおもしろいのはもちろんだけれど、それ以上に作者の語り口が魅力的だった。いや、作者の語り口が軽妙だからこそ、話がこんなにおもしろくなるのだろう。
そして、ただ軽妙というだけではない。出久根さんの言葉は、ものすごくちゃんとした日本語、という感じがする。背筋がぴーんとしていて、気持ちがいい。そのうえ、ちょっと古風な味わいがある。
たとえば受賞第一作になる短編集『あったとさ』からひいてみよう。
私が古本屋を開業したてのころ(中略)満載のリヤカーが置いてあって、通りすがりに目をやると、古い本の背中が見えた。商売気が出て自転車を止め、相手に挨拶した。
古本屋だと名のったのである。
この最後のところ。さりげないけれど、なかなかこんなふうには言えない。「挨拶した。」と「古本屋だと名のったのである。」の間というのは、日本語がきちんとしていないとうまく飛べない。そしてこういう表現だからこそ、小気味よいリズムが生まれる。「相手に私は古本屋だと挨拶した」では、まるでつまらないだろう。
『あったとさ』に収められた六つの短編のうち「くしゃみ」を除く五編には、それぞれ古本屋さんが登場する。出久根さんは、現実に古本屋さんだ。かつてエッセイを愛読していた私は、うひゃうひゃ笑いながら「小説みたいだなあ」と思っていた。けれど小説のほうを読むと「なるほど。こっちが小説というものだ」と思う(あたりまえだけれど)。
いずれの短編も、読み終えると、ちょっと不思議な気分になる。ありえないようなことが、それこそ「あったとさ」と語られて、知らず知らずその世界に引き込まれてしまうのだ。だから現実の世界に帰ってきたとき、違和感を覚えるのだろう。その瞬間が、またいい。
ただ「冬至の旅」という作品だけは、うまく小説の世界に入っていけなかった。語り手が若い女性なのだ。で、なんとなくその言葉遣いが、おじさんがセーラー服を着ているような感じ、なのです(わぁ、変なたとえでゴメンナサイ)。
ところで、冒頭に私は、三年前からファンをやっていると言った。実は、これがかなり行動派のファンで、会いに行っちゃったこともある。『古本綺譚』を勧めてくれた編集者が、出久根さんを知っていると聞いて、「えー、じゃあ会わせて会わせて。そうだ、出久根さんのお店に遊びに行きましょうよ。私、古本屋さんって大好きなの」とせがんだ。
たしか一九九〇年の暮れも押し迫ったころのことである。彼と二人で、高円寺に出かけて行った。
出久根さんのお店には、たくさんの本たちが「愛されています」という風情で並んでいた。本への愛情が、出久根さんの世界の基本なのだなあ、とあらためて思う。
私たちは大変な歓迎を受け、お宅にあがりこみ、奥さまの手料理までごちそうになった。
あつあつの揚げ物、こっくりの煮物、そして海の幸たっぷりの鍋を囲んでの宴会である。
(いま思い出すと、かなりあつかましいファンだ)
ほんものの出久根さんは、エッセイからの予想を上回るほど、愉快で気さくであたたかい人だった。
直木賞を受賞されたとき、私はあいにく海外にいて知らなかったのだが、帰国するなり母が教えてくれた。
「あなたの大好きな人が、直木賞よ!」
やったね、と思った。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
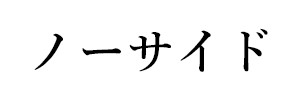
ノーサイド(終刊) 1992年11月号
ALL REVIEWSをフォローする