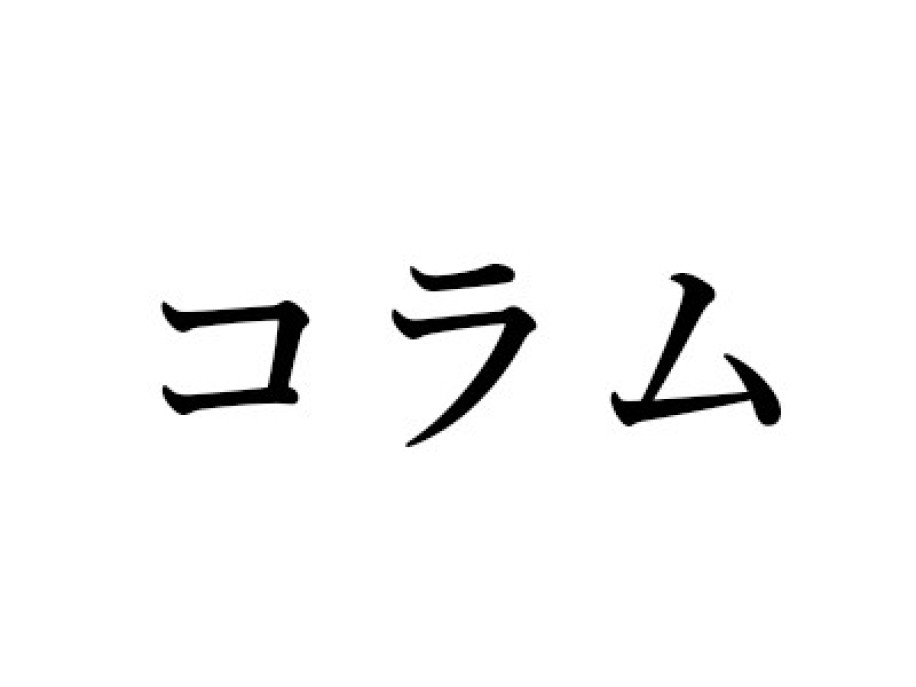後書き
『かーかん、はあい 子どもと本と私』(朝日新聞出版)
文庫版あとがき
久しぶりに本書を読み返して、息子と私とのあいだに常に絵本があった日々を、なつかしく思い出した。たとえば妖怪の本の影響で、息子がキジムナーに興味を持ち、キジムナーに会いたくて、初めて沖縄に行った。そこではイルカに夢中になり、今度はイルカの本を読み始める……そんなふうに、暮らしと本が、いつも一体だった幼年期。本という観点から言えば、とても豊かな時間を、息子は過ごせたのではないかと思う。
キジムナーのくだりで、私がことに深い感慨にとらわれたのにはわけがある。昨年の震災後、息子と私は沖縄へ避難した。山形空港で、羽田からの乗り継ぎ便を探していたとき「那覇(なは)便なら空きがある」と言われ、即決した。息子との楽しい思い出が胸中をよぎり、沖縄でなら前向きに過ごせそうだと思ったからだ。まったく未知のところへ行くよりも、いい。「おきなわ」と聞いて、息子の表情も、ぱっと明るくなったのを覚えている。
紆余曲折を経て、我々親子は、そのまま住みついてしまった。そもそも妖怪の本を読んだことが遠因だったかもしれないと思うと、人生は本当に不思議だ。息子は今、キジムナーさながら、木に登ったり、滝壼(たきつぼ)で泳いだりしている。
避難しはじめたころは、しばらく那覇のホテルにいた。毎日毎日、狭い部屋でテレビに見入っていたら、気持ちは暗くなるばかり。繰り返し流れる震災の映像を見ていたせいか、息子には赤ちゃんがえりのような症状が出はじめた。このままではマズイと思い、気晴らしに近くの本屋さんへ行ったのだが、これが本当によかった。
実感として「生き返った!」という感じ。息子は児童書のコーナーで、午後じゅう本を読みふけっていた。私自身も、本に囲まれた空間が、こんなに心に潤いをもたらしてくれるのかと思った。森林浴ならぬ「書籍浴」と名づけ、それからは毎日のように、本のパワーを浴びるため、書店へ通った。
そこで購入した日本の昔話や、なぞなぞの本、子どもむけの冒険談などを、ホテルの部屋で何度も読んだ。本を開けば、たちまち本の時間が流れはじめる。いつでも、どこにいても、それは同じ。息子と私は、本のおかげで、心穏やかなシェルターにいるような時間を過ごすことができた。テレビを消して本を読むことで、息子の状態も劇的によくなった。
その後、被災地へ絵本を贈ろうというプロジェクトがあることを知り、微力ながら私も協力した。「今は、絵本どころじゃない」という状況の人も大勢おられるだろうとは思ったが、食べ物や住むところと同じくらい、本は子どもたちにとって必要なものではないかとも思われた。本を読んでも、おなかはいっぱいにならない。けれど、現実をいったん離れて本の世界に遊ぶことは、子どもたちの心を満たしてくれることだろう。阪神淡路大震災のとき、知人が大量の花を持っていって、とても喜ばれたという話を思い出す。非常時ではあっても、いや非常時だからこそ、心のうるおいは人にとって大きな意味を持つ。被災地の子どもたちが、読みたいと思ったとき、そこに本がありますようにと願った。
ところで今、息子は小学三年生。本書で「ドラえもん」のことを紹介しているが、マンガ熱はますます高まっている。私自身は、それほどマンガを読んでこなかったので、はじめは戸惑いもあったが、マンガだからダメということはないだろう。文字の本だって玉石混淆(ぎょくせきこんこう)なのだから。
ただ、ほうっておくとマンガばかりになってしまいそうなので、息子とは一つの約束をした。
「マンガを読んだら、それと同じ時間、文字の本も読もうね」
シンプルな約束だが、息子も大いに納得。一時期は、マンガ読みたさに(?)文字の本を読んでいるようなところもあったのだが、最近では自分と相性のいいシリーズものなどに出会うと、マンガそっちのけで読みふけっている。頭からマンガを否定してしまわなくてよかったなと思う。
そして、今の小学生にとって、読書の時間を奪うものはマンガだけではない。近所のお母さんに「マンガだっていいわよ! 何か読んでくれれば。ウチはそれさえしないんだから……」と嘆いている人がいる。聞けば、敵はゲームだそうだ。
テレビやDVD、パソコンに加え、わくわくするようなゲームがたくさんある時代。その圧倒的な楽しさと手軽さに慣れてしまうと、読書なんておっくうになってしまうのだろう。こういう環境にあって、読書を続けるというのは、とても難しい。ある意味、子どもたちにとっては気の毒な状況かもしれない。
ゲームやパソコンについても、息子とはこんな約束をした。
「時間を決めようね。そしてその時間は、読書の時間より、ずっと少ないよ」
この提案に、はじめ息子は不満そうな顔をしたが、次のように説明した。
「お母さんは思うんだけど、ゲームって、おやつみたいなものなの。手軽に楽しめるし、今はいろんなものが工夫されていて、それはそれは面白いんだと思う。でも、心や頭の栄養を考えると、やっぱり本が主食、つまりごはんだと思う。朝ごはんにケーキ、昼ごはんにポテトチップス、夜ごはんにチョコレート……そんなことしてたら、からだ、どうなると思う? ゲームを、一切しちゃダメとは言わないけど、おやつを楽しんでいると思って、けじめをつけようね」
いろいろと誘惑の多い時代、ゲームなどをセーブするにも限界はある。やはり一番いいのは、我慢させることよりも、それ以上に夢中になれるものを見つけられるように、そばにいる大人が環境を整えてやることだろう。
マンガ以上にゲームには縁のない私なので、もしかしたら警戒しすぎだろうか。「からだにいいおやつ」というのも、あるのかもしれない。子どもと一緒に迷いながら考えながら、選んでいけたらと今は思っている。
「かーかん、はあい」を新聞に連載していたとき、そして単行本にしたときには、五味太郎さんの挿画が、ほんとうに素敵で楽しくて、文章を書くうえでもとても励まされた。今回は二冊分を一冊のハンディな文庫本にするということで(内容的にはオトクなのだが)、挿画は割愛ということになった。表紙が、連載当時の雰囲気を伝えてくれているが、もし機会があったら、図書館や本屋さんで単行本のほうも、手に取ってもらえたら嬉しい。
二〇一二年三月
俵万智
【単行本】
【この後書きが収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする