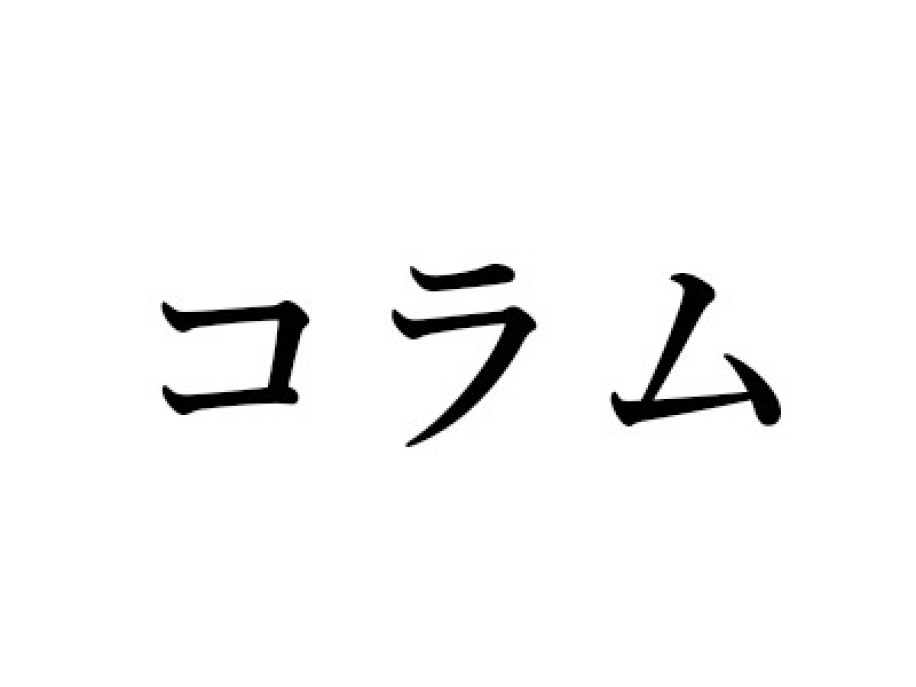書評
『残夢童女 石牟礼道子追悼文集』(平凡社)
ここにはいない人を引き寄せ その人は誰だったかを考え抜く
2018年2月に逝去した石牟礼道子を悼む文を編んだ一冊である。もう二年経ったのかと思い、まだ二年とも思い、しかし、歳月や距離などを超えて、こちらが求めればつねに身近に寄り添うのが石牟礼道子なのだと、あらためて思う。 38人による、38の追悼文。一編一編に接してまず感じるのは、石牟礼道子という存在のはかりしれなさである。言葉をあてがうと、大事な何かが逃げてゆくような心許なさ、肝心なものを取り逃がす怖れの感覚。そのうえで38人が38人とも自身の言葉をもって手向けとする、敬慕のおこないとしての追悼文だ。
三章によって構成される。
1「傍にて」。すぐそばで過ごした12人がそれぞれに石牟礼道子を語るのだが、冒頭、最大の理解者である思想史家・評論家の渡辺京二の言葉に触れ、粛然とする。
僕は「あなた方にお任せします」という気持ちでいる。みなさんの石牟礼道子です。(中略)「石牟礼道子のことは俺が一番分かっとっとぞ」という気持ちは全然ない。(中略)いま考えてみると、僕の手に負える人じゃなかったと思う。つまり天地から言葉を預かっている人。そういう存在はめったにいるもんじゃないから。
石牟礼道子資料保存会事務局長、阿南満昭「ワガママ、気まぐれ、思いつき大明神」。長男、道生「もう悶えないでゆっくりやすんでください、母さん」。あるいは、パートの女性による危篤から逝去までの二日間のなまなましい記録。新聞記者、熊本市内の書店店主、身辺の世話を13年にわたって引き受けてきた女性……身近な人々から浮かび上がる人間味が照らし出され、愛おしく、慕わしい。
2「渚の人の面影」。池澤夏樹ほか十一人の作家や写真家が、それぞれの視線を交差させる。水俣に生まれ、石牟礼道子自身が設立メンバーでもあった水俣病センター相思社で活動してきた永野三智の文章からは、生身の石牟礼道子の声が響いてくる。「文章を書くのにも無意識に花を咲かせている」
「怨旗を大切に、なるだけなら長くそのままの状態で保存してください」
「あなたは悶え加勢しておられるのね」
口からこぼれた言葉の数々やその背景をこうして語り伝えてもらえることが、あらたな理解を助け、人物研究に役立つと思うから、本当にありがたい。はかりしれない存在であるとしても、聖域のような場所に奉れば、思考停止に陥ってしまうと思うから。
3「石牟礼道子論」。赤坂憲雄、伊藤比呂美、臼井隆一郎、姜信子、三砂ちづる、齋藤愼爾、最首悟、辺見庸、松岡洋之助、中村桂子、高峰武、福元満治、松下純一郎、藤原新也、若松英輔ら十五人の考察が並ぶ。
追悼文がもたらす意味について、あらためて考える。悼む言葉は、もうここにはいない人を至近距離に引き寄せ、身罷(みまか)ったその人は果たして誰だったのか考え抜くこと、問い質すこと。それは、死者からの贈り物でもあるのだろう。
本書の題名「残夢童女」は、渡辺京二の示唆によるという。編集は熊本を拠点に活動する「石牟礼道子資料保存会」である。
ALL REVIEWSをフォローする