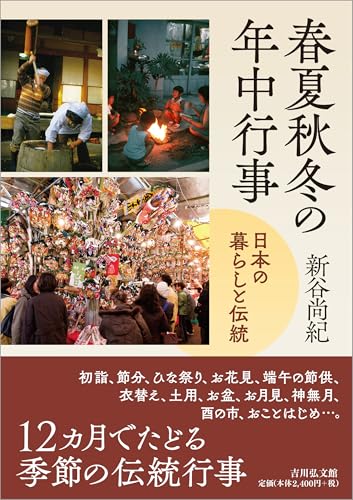書評
『透明な対象』(国書刊行会)
ある仕事を通じて、二十世紀の名作を読み直しているのだけれど、先入観を持たずに接すれば、文豪の作品もまた非常に近しいものとして気軽に楽しめることがわかったのは幸いだ。たとえば、ナボコフ。細部への徹底したこだわり、巧緻(こうち)な伏線、隠喩や押韻(おういん)を駆使した流麗知的な文体、厳密な審美眼など、衆人を震え上がらせる眩しいオーラをまとったこの“言語の魔術師”を、敬して遠ざけている読者は多いのではないか。が、恐るることなかれ。この『透明な対象』を読めば、ナボコフが親しみやすい貌(かお)を持った作家であることがわかるはずなのである。
主人公は文芸編集者のヒュー・パーソン。彼はこの本の中で四度スイスを訪れる。一度目は父と、二度目は気難しい大作家との打ち合わせのために。この時パーソンは、彼のファム・ファタール、アルマンドと出会う。そして、結婚。三度目は、アルマンドの母の見舞いに。しかし四度目は――。この中でナボコフは、シニカル、ユーモラス、アイロニカル、スラップスティックと、様々なレベルの“暗闇の中の笑い”を披露している。パーソンがホテルの整理棚で鉛筆を見つけ、一本の鉛筆の生涯を木が切り倒される瞬間にまで遡らせる偏執狂的な空想。不器用な父親がズボンの試着の最中に脳卒中で倒れるシーン。恋するパーソンがアルマンドと一緒にいたいがために過酷な山登りに挑戦するも、何とも情けない姿を見せてしまうくだり。結婚後、アルマンドの尻にしかれっぱなしのパーソンの悲哀。不眠症に悩むパーソンが反復して見る悪夢のグロテスクなイメージ。そして訪れる、唐突にして理不尽な悲劇。その中でナボコフは、一寸先は闇の中を歩むわたしたち誰もが覚える「なんで、こーなるの」という驚愕と、「やれやれ」と肩を落とさざるを得ない諦観を十全に描き出しているのだ。
さて、この物語の語り手は“我々”である。訳者の若島正さんが解説で書いているよう、たしかに本書の最大の謎は“我々”の正体であるに違いない。それを解き明かすことが、読者に課された務めでもあろう。でも、それはすでにナボコフが作中で明かしてはいないだろうか。つまり、パーソンが常に自分の背後にその存在を感じ続けていた「自分よりずっと大きくて、信じられないほど賢くて、冷静で道徳的にも優れた、達者な他者」。これを単純に神ととらえるか、もしくは登場人物にとっての作者と考えるか、それとも別な解釈を試みるかは読者の勝手。いや、もっと言えば、解釈しなくたって結構だとすらわたしは思うのだ。
それよりも何よりも、まず大切なのは、ナボコフが笑いたっぷりに作り上げてくれた、一人のパーソン(人間)の魅力に引きずり込まれてしまうことだと思う。畏れることは大切だけど、怖れることはない。まずは気軽に楽しむこと。ナボコフの扉はちょっと押しただけで開く。批評なんて大金槌ふるわなきゃ開けられないほど無粋な作家ではないはずだ。
【この書評が収録されている書籍】
主人公は文芸編集者のヒュー・パーソン。彼はこの本の中で四度スイスを訪れる。一度目は父と、二度目は気難しい大作家との打ち合わせのために。この時パーソンは、彼のファム・ファタール、アルマンドと出会う。そして、結婚。三度目は、アルマンドの母の見舞いに。しかし四度目は――。この中でナボコフは、シニカル、ユーモラス、アイロニカル、スラップスティックと、様々なレベルの“暗闇の中の笑い”を披露している。パーソンがホテルの整理棚で鉛筆を見つけ、一本の鉛筆の生涯を木が切り倒される瞬間にまで遡らせる偏執狂的な空想。不器用な父親がズボンの試着の最中に脳卒中で倒れるシーン。恋するパーソンがアルマンドと一緒にいたいがために過酷な山登りに挑戦するも、何とも情けない姿を見せてしまうくだり。結婚後、アルマンドの尻にしかれっぱなしのパーソンの悲哀。不眠症に悩むパーソンが反復して見る悪夢のグロテスクなイメージ。そして訪れる、唐突にして理不尽な悲劇。その中でナボコフは、一寸先は闇の中を歩むわたしたち誰もが覚える「なんで、こーなるの」という驚愕と、「やれやれ」と肩を落とさざるを得ない諦観を十全に描き出しているのだ。
さて、この物語の語り手は“我々”である。訳者の若島正さんが解説で書いているよう、たしかに本書の最大の謎は“我々”の正体であるに違いない。それを解き明かすことが、読者に課された務めでもあろう。でも、それはすでにナボコフが作中で明かしてはいないだろうか。つまり、パーソンが常に自分の背後にその存在を感じ続けていた「自分よりずっと大きくて、信じられないほど賢くて、冷静で道徳的にも優れた、達者な他者」。これを単純に神ととらえるか、もしくは登場人物にとっての作者と考えるか、それとも別な解釈を試みるかは読者の勝手。いや、もっと言えば、解釈しなくたって結構だとすらわたしは思うのだ。
それよりも何よりも、まず大切なのは、ナボコフが笑いたっぷりに作り上げてくれた、一人のパーソン(人間)の魅力に引きずり込まれてしまうことだと思う。畏れることは大切だけど、怖れることはない。まずは気軽に楽しむこと。ナボコフの扉はちょっと押しただけで開く。批評なんて大金槌ふるわなきゃ開けられないほど無粋な作家ではないはずだ。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア

レコレコ(終刊) 2003年3-4月号
ALL REVIEWSをフォローする