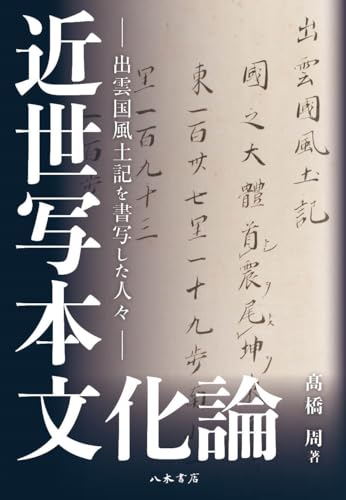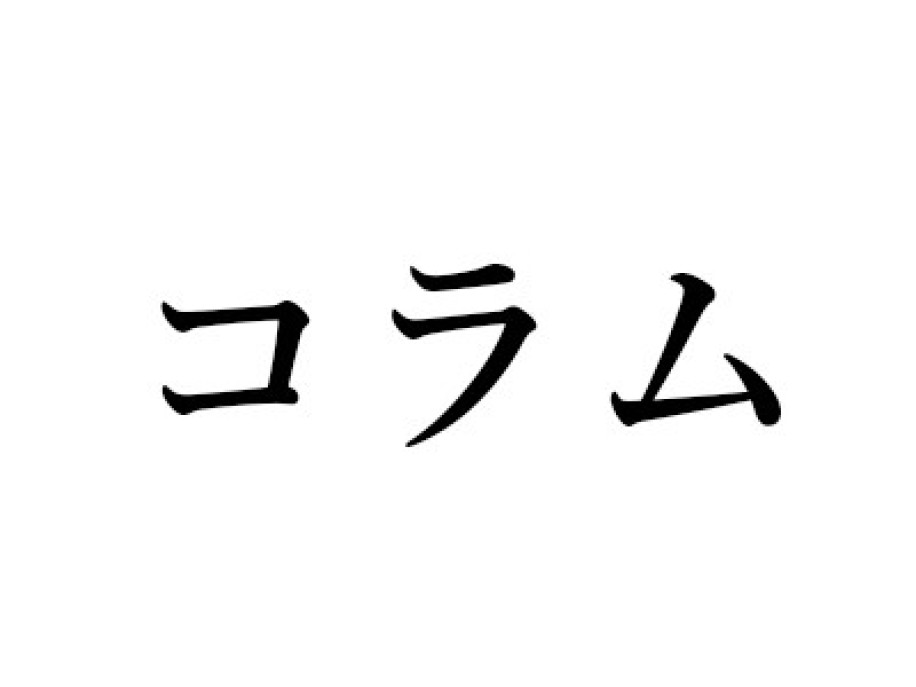書評
『歩哨の眼について』(筑摩書房)
幽霊の出る風景
前にこの欄で、少年時代僕は川釣り海釣り絶好の環境に生まれ育ったにもかかわらず、一匹も魚を釣りあげたことのないさびしさについて書いたが、嘘だろうという声が返ってきた。そんなアホな、と。しかし、ほんとうなのだからしかたがない。僕の郷里で農業や漁師をやっている幼なじみたちがよく証言してくれるはずだ。しかし、僕のような無念を抱えている人間、案外多いんじゃないだろうか。一本のヒットも打ったことがない、そういう草野球愛好家もいる。僕の義姉は一度も嘔吐を経験したことがない。しかも、それを自慢にしている。いろんな人がいるんだ。
ところで、僕が生まれ育った紀伊半島南部というのは古来幽霊跋扈(ばっこ)の地なのに、僕はまだ一度もそいつに出くわしたことがない。たとえば僕の従兄はある冬の夜、山の中をオートバイで走っていて、突然エンストをおこした。ガソリンはたっぷりある。どこもおかしいところはないのに、どうしてもエンジンがかからない。
そこへ提灯を持った小人のような老人が通りかかって、意味のわからぬ言葉をささやき、ペダルを軽く踏むとかんたんにエンジンがかかった。従兄がサドルにまたがって振り返ると、左手の方に提灯が遠ざかり、あるところでふっと灯が消えた。谷底の瀬音がいっぺんに大きくなってきこえた。
幽霊をみたことのない僕は、あきらめて、もっぱら本の中に幽霊を捜しにゆく。しかも天邪鬼(あまのじゃく)だから、まず最も幽霊の出そうにない作家のもとにそれを捜しにゆく。大岡昇平。
彼に「歩哨の眼について」というごく短い作品がある。彼が太平洋戦争に三十五歳で召集され、フィリピン、ミンダナオ島サンホセに駐屯して、毎夜歩哨に出た時の体験を描いたものだ。冒頭に『ファウスト』第二部、物見リュンコイスの「見るために生れ、見よと命ぜられ(略)幸福な両の眼よ」を引用して、ぼんやり遠くをみるのは誰でも気持のいいものである、と〈私〉につぶやかせる。
しかし、敵の出現を見張る歩哨の眼は遠くをはっきり見なければならない。となると楽な役目ではない。戦場が緊張してくると、雲が動いて星が上がったり下がったりするのを敵の曳光弾とみまちがえ、歩哨たちは恐怖をきたす。ある夜、歩哨にたった〈私〉もそれをみる。〈私〉は錯覚だと確信しているが、この時悪寒に似た不快な感じが背中を走る。〈私〉は学生の頃、幽霊をみたことを思い出す。暗い場所に立つちょうど女の丈ぐらいの一本の植木をじっとみているうちに、〈私〉はこう考える。
もしこれが本当に女の幽霊だとしたら、こうしてぼんやり立ち止っていることが、どんなに怖ろしいことかと思った。その時木が変貌した。(太字大岡)
この時、顔ののっぺらぼうな女の幽霊が出現した。〈私〉はぞっとする。二、三歩あるく。角度が変わって、木はもとの木にもどる。
星が動いて曳光弾に見えたのは、私がまず怖れ、次に見詰めすぎたからに相違ない。
(略)しかしもしあれが本当に曳光弾であったら大変である。(太字辻原)
大岡昇平の〈私〉は、ゴッホの細かく描きこまれた遠景こそ幽霊が立つにふさわしい場所だ、といっている。
物見リュンコイスもまた最後に悲痛な叫びをあげる。
「お前たち、目よ、これを見きわめねばならぬのか! おれたちはこんな遠目がきかなくてはならぬのか」
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする