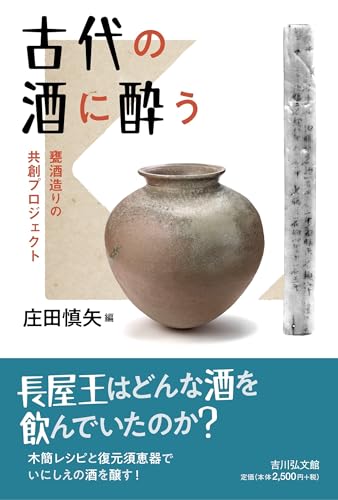書評
『天皇と倒錯―現代文学と共同体』(青土社)
吉田健一的狂気の生き方
丹生谷貴志はなぜ、「……」を多用したり余韻を持たせたりする文体で批評を書くのだろうか。端正に理論を語っているかと思えば、いきなり無根拠な印象を書きつけたりする。だが、私がそこに感じるのは、読んだり考えたりする自分に対するある種の誠実さである。思考の過程や飛躍を記述したように見えるから誠実なのではない。『天皇と倒錯』で取りあげられた作家のうち、丹生谷が最も肩入れしているように見える吉田健一の狂気を生きようとする態度が誠実なのだ。その吉田健一論を無理に要約してみると、まずサルトルを引き合いにした「I 余談」から始まる。今世紀における近代とは、個人が絶対を渇望しながらも自分は有限であることを思い知らされて欠如感の深淵に飲み込まれてゆく過程であり、サルトルらはそんな「精神分裂に至る神経症の世界」から脱出しようとしては失敗する。吉田健一はその世界から逃れるのではなく、さらに神経症から分裂病が発病する間際へと積極的に踏み出す。それは「外部と内部の葛藤亀裂が薄れ、内界と外界がぼんやりと連続する」不思議な安定期、中井久夫の言う「偽りの静穏期」であり、吉田はその「奇妙な静けさとざわめきとひしめき」に満ちた狂気に踏みとどまることで、逆に近代から癒されてゆこうとする。その狂気のありさまを丹生谷は、眠りに落ちる際に経験する、精神なのか事物としての闇なのかどっちつかずの状態にある曖昧な臨界として捉える。その臨界を越えれば人間は事物となって存在しなくなるという単なる行き止まりである以上、欠如感という深淵は存在せず、「欲望としてであれその外部になにものかの領域が表象されることは有り得ない」。そこでは一回きりの事物の感触が、無数に無限に規則性のないまま連鎖して現れる。ここに「解体と構成の危うい中間地帯を生き続ける」「緊迫した生の試み」が可能となる。
自分が読み思考し書くことも同様のことだと、丹生谷貴志は考えていると思う。あの文体もそこから立ち現れているはずである。文芸時評を集めた近著『死者の挨拶で夜がはじまる』の冒頭のインタビューでは、オウム事件に触れ、オウム信者や子どもたちは、するべきことを探さなくちゃ生きていることにならない、でもどうせ人は死ぬんだという思い込みから解放される必要があり、することはないという状態を普通のこととして生きる方法が求められている、と言っている。その答えが、吉田健一のぎりぎりの生き方なのだ。
『天皇と倒錯』で丹生谷が各作家に読んでいくのも、多くはこの「緊迫した生の試み」ないしはそれに近づこうとする「倒錯」した態度である。にもかかわらず、私が吉田健一論以外の丹生谷の文章に感じとるのは、吉田健一的狂気ではなく、ほどよい透明さである。この調子であればどんな作家でも論じることが可能なのではないかと思わせる万能さである。そして、そのことにもどかしいような隔離感を抱かせられる。三島由紀夫、石川淳、川端康成、安部公房等々、誰にしても丸ごと根本から論じられているようでありながら、そこには三島由紀夫も石川淳も川端康成も安部公房いないという感触を持つのだ。
吉田健一論の出だしがそうであったように、小説家を論じながら常に丹生谷の中核にあるのは抽象的な仮の地図を描くような思考である。それは仮説のように見えるが、証明するわけではないので仮説ではない。その仮の地図を他の思想の補助を借りながらたどることによって、各作家の姿勢と作品を読んだ自分の思考とを結びつけようとするのだ。 だが、思考の記述から、論じられている作家へと向き合うとき、丹生谷はその作家の全体像を明快な物語として説明するほうへ傾き、個々の作品のテクスト自体にはあまり触れない。あるいは触れても、仮の地図を描く思考から導き出されたことを傍証するだけに留まっていたりする。テクストの言葉そのものに引きずられたり、論じているものとは異なるものがテクストから露出したりといった危うさは少ない。だから、闊達自在に論じられているように見えてしまうのである。
書き下ろしである冒頭の序「天皇と文学」もそうである。天皇がいかに外部を消去させ忘却してきたかを語る部分も、その内容に異論はないのに、妙に口当たりのよい物語という印象を残す。「路地」の者たちが「外部」たる国土を初めて名付ける「詩」という血みどろの戦いを行い、「外部」を平定した後、天皇が「詩」とその担い手である「路地」の者たちを封じ込めたと説いても、それを説く文章には外部の感触がない。それは「詩の戦い」がいかなるものであるかを解き明かさないからだ。その戦いや外部の痕跡を持ったテクストを割り込ませていないからだ。私は、史的事実を持って実証せよといっているのではない。ただ、そのような外部の痕跡を感触として示さない限り、あるいはそれを書く言葉自体が外部とならない限り、内容とは裏腹にどうしても文章そのものの感触が丹生谷自身の言う天皇的忘却と似てきてしまう。テクストそのままの言葉を思考の形に収めようとするがために、読みとテクストの言葉そのものの間、思考とテクストの言葉自体との間にあるはずの断絶が見えなくなる。世界が抽象的に思えるというそれ自体は抽象的ではない感触にこだわり、それこそが思考の場であるとみなして思考を続けている、つまり吉田健一的狂気を生きようとしている丹生谷が、この断絶を滑らかにして書いてしまうことがもどかしい。
図書新聞 1999年11月6日号
週刊書評紙・図書新聞の創刊は1949年(昭和24年)。一貫して知のトレンドを練り続け、アヴァンギャルド・シーンを完全パック。「硬派書評紙(ゴリゴリ・レビュー)である。」をモットーに、人文社会科学系をはじめ、アート、エンターテインメントやサブカルチャーの情報も満載にお届けしております。2017年6月1日から発行元が武久出版株式会社となりました。
ALL REVIEWSをフォローする