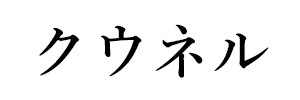書評
『その名にちなんで』(新潮社)
「やあ、ゴーゴリ」と小さく呼びかけながら、いばりくさった顔で産着にくるまれている息子をのぞき込む。「ゴーゴリ」と、もう一度口にする。いい感じだ。赤ん坊は、ああ、びっくり、と言いたそうに首をまわしてから、あくびをする。
小説を読んでいると、「ここなんだな」とピンとアンテナが立つことがある。それは自分の中に、その物語が棲みつき息づき始める瞬間だ。こうなれば、物語からわたしを引き離すことなんて誰にもできない。ただ、ひたすら読む。登場人物と共に物語世界を生きる。それが読書の醍醐味なのだし、その瞬間がいつまでたっても訪れない小説は、つまり自分にとって大切な一冊にはなり得ないのだと思う。カルカッタ出身のベンガル人の両親から生まれ、幼少時にアメリカに渡った移民第二世代の作家、ジュンパ・ラヒリの初長篇作品『その名にちなんで』が、わたしの心の中にしっかりと根づいたのが、冒頭に挙げた、主人公が父アショケ・ガングリーから最初の贈り物としての名前を与えられた場面だったのだ。
若き日に列車事故に巻き込まれ瀕死の重傷を負うも、手にしていたゴーゴリの短篇「外套」から破れた一ページを握りしめていたおかげで救助された経験を持つアショケ。そのアショケと見合い結婚をし、マサチューセッツ工科大学で博士号の取得を目指す夫につき従って渡米、慣れない土地で親しい人がいない中、初めての出産に臨もうとしている妻のアシマ。母語の通じない国で何とか自分の居場所を見つけようと努めつつ、望郷の念や親しい人たちへの想いに後ろ髪を引かれているアショケとアシマが、アメリカで初めて得たかけがえのないもの。その息子の名前がアショケの命の恩人、ロシアの文豪ゴーゴリの名にちなんでつけられた瞬間、わたしはこの物語の中に取り込まれ、ガングリー一家の人生の伴走者となったのである。
ところで、ベンガル式の命名法では一人の人間が「愛称」と「正式名」二つの名前が持てることになっている。だからゴーゴリは愛称で、正式名はニキル。自分の愛称の由来を父から聞かされていないゴーゴリは、物心がつき始めるとこの風変わりな愛称を嫌うようになる。十四歳の誕生日、アショケからゴーゴリの短篇集をプレゼントされた我らが主人公が、ゴーゴリがかの文豪のファーストネームですらないことを知り愕然とするシーンが可笑しい。じゃあ、ゴーゴリ・ガングリーって苗字と苗字なんじゃん! うんざりしたゴーゴリは大学に入る直前、家族に自分をニキルと呼ぶよう要求し、正式名の人生を歩み始めるのだ。
父や母が代表する移民第一世代と違ってアメリカの社会や文化を素直に受け入れながらも“ABCD”(=Amerian‐born confused deshi[アメリカ生まれで、わけがわからなくなっているインド系の人間])という言葉は自分にぴったりだと思っているゴーゴリは、その後、父祖の歴史や文化、習慣、価値観から遠く離れようと、“名誉白人”的な生き方を選択していく。両親に後ろめたい気持ちを抱きながらも白人女性とつきあい、彼女の裕福で知的な家庭こそが自分にとって居心地のいい場所と定める。ベンガル人同士で集まっては故郷の料理を食べ、洗練とはほど遠い生活を送る親世代の姿を、恥ずかしいと感じる。そして、ニキル・ゴーゴリの頭文字が示すとおり、青年期のゴーゴリの愛情生活はNGの連続となっていき――。
そんな迷い多きゴーゴリを中心に、移民第一世代と第二世代の断絶や葛藤を描いたこの物語には、常に二つの視点が同時に存在している。ベンガルとアメリカ、アショケ世代とゴーゴリ世代、愛称と正式名、アショケらが生きてきた過去とゴーゴリたちが生きる今。自身、移民第二世代であるラヒリは、いま・ここから、かつて・遠いところもしくは誰かを想うという遠近両用の視線と、中心をずれた場所から世界を見つめる異邦人の視線で物語を紡ぐ作家なのだ。それは、ピュリツァー賞ほか多数の新人賞を受賞したデビュー短篇集『停電の夜に』(新潮文庫)でも明らかな特徴として読みとることができる。
関係がぎくしゃくしている夫婦が、停電の夜ごとにささやかな秘密を打ち明けあう儀式を通じて、死産してしまった我が子の不在による哀しみを共有しあうに至る表題作や、内乱に揺れる祖国パキスタンに残してきた家族の身を案じる学者との交流を通して、初めてはるかに遠い人を思う気持ちを知る少女の話「ピルサドさんが食事に来たころ」をはじめ、収録されている九作どれもが溜息が出るほど巧い。こことは違うどこか、わたしとは違う誰かを遠景におきながら、いま・ここにある風景や出来事を描く手法が物語に奥行きをもたらす。読み心地は長篇小説に負けないくらい味わい深く、余韻がいつまでも響く。たとえてみれば、心の奥にあって忘れている小さな部屋のドアをノックされている、そんな感じ。読む前と読んだ後では世界の見え方や感じ方が変わってしまい、小さな部屋ひとつ開けた分、心が豊かになったように感じられるのだ。
ところで、この短篇集の最後に収められている「三度目で最後の大陸」は、いまや『その名にちなんで』の原型という読み方がされるべき一篇かもしれない。一九六四年インドを離れてイギリスに留学し、やがてカルカッタから嫁いできた妻と共に渡米し、大学の図書館職員として働くようになった〈私〉は、ラヒリ自身の父親とアショケを彷彿させる人物なのだから。物語の最後、一九六八年生まれ(ゴーゴリと同じ!)の大学生の息子を持つ〈私〉はこんな感慨をもらす。〈国を出て将来を求めたのは私ばかりではないのだし、もちろん私が最初ではない。それでも(中略)その一歩ずつの行程に、自分でも首をひねりたくなることがある。どれだけ普通に見えようと、私自身の想像を絶すると思うことがある〉。これはそのまま、アショケが口にしても違和感のない思いではないだろうか。
さて、アイデンティティを定められずNG気味の青春を過ごし、失意の三十二歳男となった我らがゴーゴリは、物語の最終章で、いままで読んだこともなく、まったく忘れていた本、「ゴーゴリ・ガングリーへ」「この男が名前をくれた――名前をつけた男より」という父の署名が入ったゴーゴリの短篇集を開く。大学四年生の時にようやく命名の由来を教えてくれて、「僕のせいで大惨事の夜を思い出す?」としょげるゴーゴリに、〈おまえを見て思い出すのは、事故よりあとの全部だ〉と言ってくれた優しい父はもうこの世にいない。その名にちなんだ作家の短篇集に読み耽るゴーゴリの姿を見て、ここまでガングリー一家の三十二年間に伴走してきたわたしは安心すると同時に淋しくてたまらなくなってしまう。名残惜しさで本を閉じることができなくなってしまう。その時、わたしもまた自分以外の誰か、ここではない遠くのどこかへと思いを飛ばす遠近両用の視線を獲得しているのだ。ジュンパ・ラヒリの作品を読むとは、そういう体験を指すのだと思う。
【文庫版】
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする