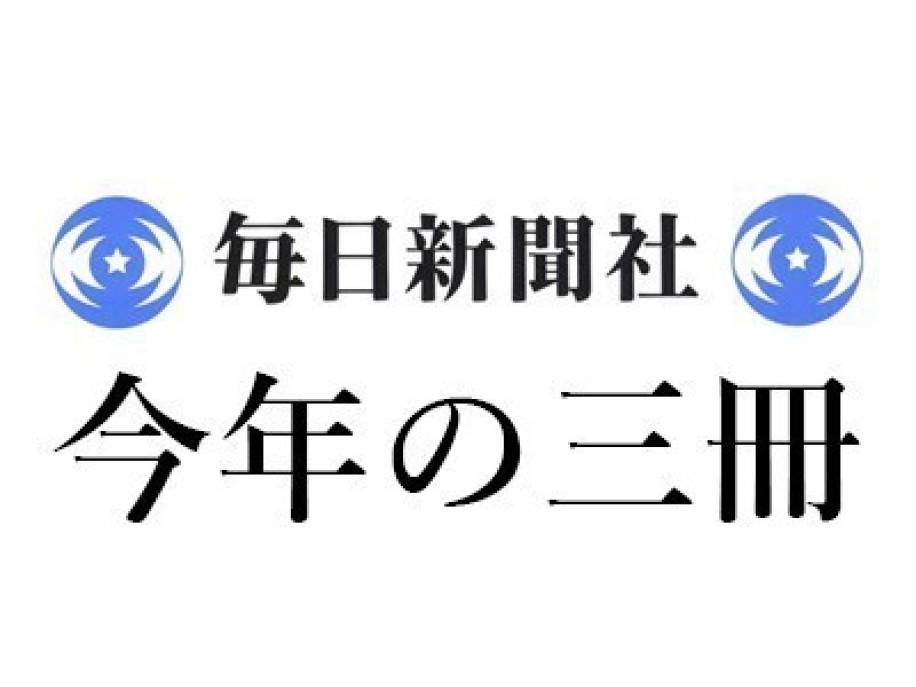書評
『イワナの夏』(筑摩書房)
紀伊半島の南端近く、切目(きりめ)川が平野の北側を真西に流れ、海をつい目と鼻の先にして急にいやいやするみたいに直角にカーブを切ると、湾沿いに一キロほど南下してようやく海に突き入る。川と海との間に南北に一キロの砂丘とハマボウの原生林と松林がある。このもったいつけた砂丘のうしろを南下する切目川にむかって、田圃や谷間を縫ってきた合計十二本もの小川が注ぐ。
僕はこの川のほとりで育った。少年時代のなによりの遊びは魚捕り、魚釣りだったはずだ。それなのに僕にはアユはもちろん、フナ一尾、ウナギ一尾、イナやボラ一尾釣りあげた覚えがない。魚がいないどころか、わんさといた川と海だったのに。
僕には決して魚は釣れない。その自覚はすでに子供の頃からあり、僕を悩ませ、おおげさにいえば劣等感のすっぱい芯(しん)になってゆく。
喜々として少年時代の釣果について語っているのは亡き植村直己。彼が語った時と場所は一九八三年五月のある日、千曲川の最上流のテントのシュラフの中だ。暗闇の中の話し相手は湯川豊という渓流の釣り師。
と湯川は書く。
翌八四年二月、植村直己はマッキンリー登頂後に行方不明になる。この湯川の文はその年の十月に書かれている。
翌日、湯川は一本のクルミの木の下の流れで釣りあげた二十センチほどのアマゴを、上顎に鉤が刺さったまま手で包むようにして、水を蹴ちらして植村のところまで走り、息を切らせ、ほら、アマゴと差し出す。
みごとな植村直己追悼文になっている「緑の中」と題された文章は、『イワナの夏』の中にある。美しい渓流と森のエッセンスを薫じこめたような一冊だ。ところで、陶淵明の「桃花源詩并記(とうかげんのうたならびにものがたり)」で、いまから二千年の昔、桃花源村に迷いこんだ男も渓流の釣り師だった。
魚に見放された僕だが、この本のおかげで、釣り師のよろこび悲しみを擬似体験することができた。ついでに、僕だけに魚の釣れない理由(わけ)もわかったが、これはちょっと明かせない。
うまく行くかどうかわからないが、これからしばらく本の流れに糸を垂らして、読むよろこび悲しみを追いかけてみるつもりだ。本に垂らした栞(しおり)の糸。遠い過去、近い過去の読書で、僕はどのページにどんな栞をはさんだのか。その栞をはさんだ動機となったのは、五月の渓のような美しい瞬間だったか、それとも……。湯川豊はまたじつにうまいことをいっている。「イワナのもっとも堅固な隠れ家は『昔』の中である」
【この書評が収録されている書籍】
僕はこの川のほとりで育った。少年時代のなによりの遊びは魚捕り、魚釣りだったはずだ。それなのに僕にはアユはもちろん、フナ一尾、ウナギ一尾、イナやボラ一尾釣りあげた覚えがない。魚がいないどころか、わんさといた川と海だったのに。
僕には決して魚は釣れない。その自覚はすでに子供の頃からあり、僕を悩ませ、おおげさにいえば劣等感のすっぱい芯(しん)になってゆく。
子供の頃はね、やっぱり魚捕りがいちばんの楽しみで、毎日のようにやってました。いろんな魚をとったなあ。五月頃、ちょうど今時分ですが、夕方、浅瀬に毛鉤を流すと、ハエっていってた、小さいきれいな魚がかかってきて……小さいけど、煮て食べるとけっこううまかったですよ。それから同じ毛鉤に、たまーにアユもかかったな。これはもう、家持って帰れば大喜びされる……
喜々として少年時代の釣果について語っているのは亡き植村直己。彼が語った時と場所は一九八三年五月のある日、千曲川の最上流のテントのシュラフの中だ。暗闇の中の話し相手は湯川豊という渓流の釣り師。
何年ぶりかで植村と山で遊ぶ。南極横断とビンソン・マッシフ登頂を断念し、三月に帰国していた植村をひっぱり出した。むろんそんなことで彼の深い失意を慰められるわけもないが、春の山麓でキャンプをし、山菜とイワナをとって食べる。僕のささやかな野外生活になぜかこの大冒険家を誘いたくなった。(略)一匹だけこの谷のヤマメかアマゴを釣ろう。それを彼に見せてやるのだ。(略)日本の五月の渓の、宝石のような生きものを彼に見せたいと思った。
と湯川は書く。
翌八四年二月、植村直己はマッキンリー登頂後に行方不明になる。この湯川の文はその年の十月に書かれている。
翌日、湯川は一本のクルミの木の下の流れで釣りあげた二十センチほどのアマゴを、上顎に鉤が刺さったまま手で包むようにして、水を蹴ちらして植村のところまで走り、息を切らせ、ほら、アマゴと差し出す。
みごとな植村直己追悼文になっている「緑の中」と題された文章は、『イワナの夏』の中にある。美しい渓流と森のエッセンスを薫じこめたような一冊だ。ところで、陶淵明の「桃花源詩并記(とうかげんのうたならびにものがたり)」で、いまから二千年の昔、桃花源村に迷いこんだ男も渓流の釣り師だった。
魚に見放された僕だが、この本のおかげで、釣り師のよろこび悲しみを擬似体験することができた。ついでに、僕だけに魚の釣れない理由(わけ)もわかったが、これはちょっと明かせない。
うまく行くかどうかわからないが、これからしばらく本の流れに糸を垂らして、読むよろこび悲しみを追いかけてみるつもりだ。本に垂らした栞(しおり)の糸。遠い過去、近い過去の読書で、僕はどのページにどんな栞をはさんだのか。その栞をはさんだ動機となったのは、五月の渓のような美しい瞬間だったか、それとも……。湯川豊はまたじつにうまいことをいっている。「イワナのもっとも堅固な隠れ家は『昔』の中である」
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする