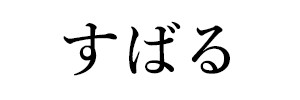書評
『サンクチュアリ』(筑摩書房)
一番身近な異文化を、自分でない人間、つまり他人とするなら、結婚は最も小さな単位の異文化の融合と言っていいだろう。融合の意思がある者同士の選択、と言うべきか。
岩城けいは、デビュー作『さようなら、オレンジ』から一貫して、異文化の中で生きる、または異文化に触れる人間の姿を描いてきた。そこには言葉と人、国と人は不可分なのかという問いが形を変えつつ必ず盛り込まれ、ひとつの国で、ひとつの言語だけで生きてきた(生きてこられた)わたしのような読者にも、登場人物たちがもがいた末に見出す光の尊さがありありと感じられた。
最新作『サンクチュアリ』で、著者は結婚をテーマのひとつに据えた。かつそれを「外国に住む外国人同士の結婚」に設定し、「異文化の層」を幾重にも施した。
「層」のルーツが、二つのエピグラフに示されている。一つ目は一九四八年のイギリス。戦争で父を失った少年が、オーストラリア行きの船に乗せられる。旧植民地諸国に貧困家庭などの子供たちが送られた、悪名高き「児童移民制度」による移送だ。二つ目は一九五九年、ある女性が代理結婚した夫に初めて会うため、異国に足を踏み入れる。オーストラリアがヨーロッパからの移民を盛んに募っていた時期だ。
本編の始まりは二〇一八年。第一のエピグラフの少年の息子と、第二のエピグラフの夫婦の孫娘が結婚し、メルボルンに暮らしている。夫の名はスティーブ、イギリス人。妻の名はルチア、イタリア人。この二人、ディクソン夫妻が物語の主人公だ。恋人時代から数えると二十年の時間を共に過ごしてきた夫婦は、今や乾いた倦怠を共有している。
〈中流と高級がブレンドされた瀟洒なスポット〉にあるそれなりに大きな家に住み、ティーンエージャーの二人の息子にはきちんとした教育を受けさせている。夫婦は異国での勝ち組だ。ルチアは夫が興した会社が軌道に乗るまで、看護師として働き家計を助けた。嫌々ながらではなく、ホスピタリティの高い彼女にとって看護師は天職だった。だから、経済的な心配はなくなったものの、専業主婦として過ごす毎日に諦念と失望と息苦しさを感じている。一方スティーブは、彼女の天性の献身性が自分の無能さを際立たせているように思え、そうとは認めたくないが劣等感を覚えている。天職を奪われてなお従順な妻の強靭さに、うっすら畏怖を抱いてもいる。
そんな夫婦のもとに、日本人のカレンがホームステイにやって来る。「丁寧語(マジック・ワード)」からは程遠い、タメ口の英語を話す無邪気であけっぴろげな二十歳。ホストファミリーのベテランである夫婦は、留学生を預かると陽気なオージーを演じる。隠れ蓑、カモフラージュだと自覚しながら〈共犯者のような後ろめたい絆で〉自分たちを結ぶ。異文化の鎧を進んで着るのだ。なぜならその異文化は、便利な「中立の場所」だから。
かつて祖父母を、親を、自分たちを「よそもの」扱いした移民の国。その国の人間を装うことに、スティーブもルチアももう慣れている。しかしカレンのような「さらなるよそもの」の存在は、慣れた行為の奥底をふと覗かせる。自宅で開いたバーベキューパーティーで、カレンと友人たちが日本語で騒ぐのを聞いたスティーブは、ルチアに苛立ちをぶつける。なぜ英語で話さないのか? 不愉快。迷惑。極めて単純なそれらの単語は、二人の間に長年埋まっていた齟齬と不満を掘り起こす火種になり、夫婦は激しく言い争ってしまう。
ルチアの大家族が晩夏に作る、オリジナルレシピの大量のトマトソース。にぎやかに飛び交うイタリア語。スティーブが抱き続けてきた疎外感の源は、自分のアイデンティティそのものだとルチアは知っている。ここはおれの家だ、主人の分からない言葉で話すなんて失礼だ、という言葉は、カレンを通り越して実は自分に向けられたものだということも。人のぬくもりのない家に育ったスティーブの孤独を理解してはいても、彼の父親に初めて会ったとき「この娘さんは英語が話せるのか?」とつぶやかれたことは忘れられない。慰撫し合えるはずの存在への攻撃は、次第に身内を擁護することとないまぜになってゆく。お互い「よそもの」同士であり、夫婦という同志でもあるのに傷つけ合ってしまうのは、この国で生まれて生きてきたのに、自分たちはどこから来たのかと未だに自問し続けているから。いや、させられ続けているからだ。そのことを十分知りながら、二人は分かり合えなさを怒りに変え、相手に投げつけることをやめられない。
家庭を築こうとするとき、そこが安全な保護区、サンクチュアリでありますようにと誰もが願い、そのような場所にしようと努力するだろう。「異文化の層」をまとっているスティーブとルチアにとって、願いは祈りに近いものだったに違いない。「私にはもうここしかないんだから!」と夫に向かってルチアは叫ぶ。「ここ」は、国であり家庭だ。どちらにも属していない、属しきっていないような心もとなさは、二十年経ってもお互いがお互いの「サンクチュアリ」では(まだ)ない証拠として二人の間に置かれている。その心もとなさと淋しさを埋めようとした自分のある行いを許せないと感じたルチアは、スティーブの目の前で突然自分を罰する行動に出る。
ルチアの祖母の言葉を、一年後の二人はある形で実行する。〈たがいの顔に、このうえなく美しいあきらめの表情が浮かんだ〉という記述が心に残る。この物語は、夫婦がその表情を獲得するまでの経緯だとも言える。格闘し模索した末の戦利品は、その時点での関係の到達点であり、この先の未来への通過点でもあるのだ。
岩城けいは、デビュー作『さようなら、オレンジ』から一貫して、異文化の中で生きる、または異文化に触れる人間の姿を描いてきた。そこには言葉と人、国と人は不可分なのかという問いが形を変えつつ必ず盛り込まれ、ひとつの国で、ひとつの言語だけで生きてきた(生きてこられた)わたしのような読者にも、登場人物たちがもがいた末に見出す光の尊さがありありと感じられた。
最新作『サンクチュアリ』で、著者は結婚をテーマのひとつに据えた。かつそれを「外国に住む外国人同士の結婚」に設定し、「異文化の層」を幾重にも施した。
「層」のルーツが、二つのエピグラフに示されている。一つ目は一九四八年のイギリス。戦争で父を失った少年が、オーストラリア行きの船に乗せられる。旧植民地諸国に貧困家庭などの子供たちが送られた、悪名高き「児童移民制度」による移送だ。二つ目は一九五九年、ある女性が代理結婚した夫に初めて会うため、異国に足を踏み入れる。オーストラリアがヨーロッパからの移民を盛んに募っていた時期だ。
本編の始まりは二〇一八年。第一のエピグラフの少年の息子と、第二のエピグラフの夫婦の孫娘が結婚し、メルボルンに暮らしている。夫の名はスティーブ、イギリス人。妻の名はルチア、イタリア人。この二人、ディクソン夫妻が物語の主人公だ。恋人時代から数えると二十年の時間を共に過ごしてきた夫婦は、今や乾いた倦怠を共有している。
〈中流と高級がブレンドされた瀟洒なスポット〉にあるそれなりに大きな家に住み、ティーンエージャーの二人の息子にはきちんとした教育を受けさせている。夫婦は異国での勝ち組だ。ルチアは夫が興した会社が軌道に乗るまで、看護師として働き家計を助けた。嫌々ながらではなく、ホスピタリティの高い彼女にとって看護師は天職だった。だから、経済的な心配はなくなったものの、専業主婦として過ごす毎日に諦念と失望と息苦しさを感じている。一方スティーブは、彼女の天性の献身性が自分の無能さを際立たせているように思え、そうとは認めたくないが劣等感を覚えている。天職を奪われてなお従順な妻の強靭さに、うっすら畏怖を抱いてもいる。
そんな夫婦のもとに、日本人のカレンがホームステイにやって来る。「丁寧語(マジック・ワード)」からは程遠い、タメ口の英語を話す無邪気であけっぴろげな二十歳。ホストファミリーのベテランである夫婦は、留学生を預かると陽気なオージーを演じる。隠れ蓑、カモフラージュだと自覚しながら〈共犯者のような後ろめたい絆で〉自分たちを結ぶ。異文化の鎧を進んで着るのだ。なぜならその異文化は、便利な「中立の場所」だから。
かつて祖父母を、親を、自分たちを「よそもの」扱いした移民の国。その国の人間を装うことに、スティーブもルチアももう慣れている。しかしカレンのような「さらなるよそもの」の存在は、慣れた行為の奥底をふと覗かせる。自宅で開いたバーベキューパーティーで、カレンと友人たちが日本語で騒ぐのを聞いたスティーブは、ルチアに苛立ちをぶつける。なぜ英語で話さないのか? 不愉快。迷惑。極めて単純なそれらの単語は、二人の間に長年埋まっていた齟齬と不満を掘り起こす火種になり、夫婦は激しく言い争ってしまう。
ルチアの大家族が晩夏に作る、オリジナルレシピの大量のトマトソース。にぎやかに飛び交うイタリア語。スティーブが抱き続けてきた疎外感の源は、自分のアイデンティティそのものだとルチアは知っている。ここはおれの家だ、主人の分からない言葉で話すなんて失礼だ、という言葉は、カレンを通り越して実は自分に向けられたものだということも。人のぬくもりのない家に育ったスティーブの孤独を理解してはいても、彼の父親に初めて会ったとき「この娘さんは英語が話せるのか?」とつぶやかれたことは忘れられない。慰撫し合えるはずの存在への攻撃は、次第に身内を擁護することとないまぜになってゆく。お互い「よそもの」同士であり、夫婦という同志でもあるのに傷つけ合ってしまうのは、この国で生まれて生きてきたのに、自分たちはどこから来たのかと未だに自問し続けているから。いや、させられ続けているからだ。そのことを十分知りながら、二人は分かり合えなさを怒りに変え、相手に投げつけることをやめられない。
家庭を築こうとするとき、そこが安全な保護区、サンクチュアリでありますようにと誰もが願い、そのような場所にしようと努力するだろう。「異文化の層」をまとっているスティーブとルチアにとって、願いは祈りに近いものだったに違いない。「私にはもうここしかないんだから!」と夫に向かってルチアは叫ぶ。「ここ」は、国であり家庭だ。どちらにも属していない、属しきっていないような心もとなさは、二十年経ってもお互いがお互いの「サンクチュアリ」では(まだ)ない証拠として二人の間に置かれている。その心もとなさと淋しさを埋めようとした自分のある行いを許せないと感じたルチアは、スティーブの目の前で突然自分を罰する行動に出る。
行ったことのないところには、行ってみるもんだ、そうすりゃ、自分がどこから来たのかわかるもんさ。
ルチアの祖母の言葉を、一年後の二人はある形で実行する。〈たがいの顔に、このうえなく美しいあきらめの表情が浮かんだ〉という記述が心に残る。この物語は、夫婦がその表情を獲得するまでの経緯だとも言える。格闘し模索した末の戦利品は、その時点での関係の到達点であり、この先の未来への通過点でもあるのだ。
ALL REVIEWSをフォローする