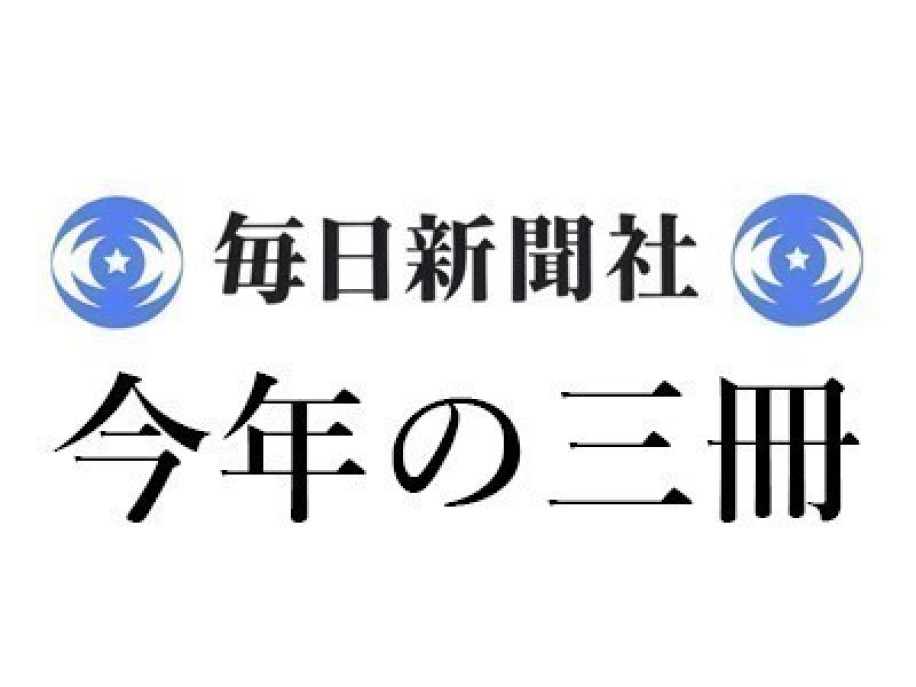書評
『平清盛 福原の夢』(講談社)
「平氏による新王朝」を目指したのか
初めての武家政権を形成し、その後の武家政権の基礎を築いた平清盛の生涯はどういうものであったか。それをどのように描くか。この問題は、『吾妻鏡』という詳細な史料が残る源頼朝を探るのとは違って、多くの難しさがある。まず清盛の肉声をほとんど知ることができない。清盛の出した文書もあまり残されていない。それなのに『平家物語』では清盛像がしっかりと造型されている。どうにも扱いにくいのである。
そこで著者は腰を据え、じっくり清盛を探ってきた。もう二十年以上も前になるが、これの前提になる『清盛以前』(平凡社。のち増補・改訂版、文理閣)(ALL REVIEWS編集部注:現在は平凡社)を著しており、それ以来、構想をあたためてきた。武士論を深めて新たな武士像を提出するなど、清新な研究を積み重ねてきた。
その間に清盛に関する著作がいくつか出版されており、また京の西八条や福原の都という清盛の重要な拠点の発掘が行われてきている。こうして満を持して出版したのが本書である。
それだけに清盛への思いに満ちた本となっており、このことは「福原の夢」という文学的な副題からも知られよう。
本書の特徴の第一は、これまでの研究文献をよく調べ、また丹念に記録類を掘り起こしていることである。
日本史の研究文献だけでなく、美術史や宗教史、さらには宋の歴史文献をも幅広く探っており、貴族の日記なども読み込んでいる。まさに長年の研究の蓄積がそこに盛り込まれているのである。
特徴の第二として、第一の特徴とも関連するのだが、考古学の発掘の成果をあますところなく取り込んでいる。これは単に調べて位置づけたというだけではなく、発掘や保存運動に深く関(かか)わってきてのものである。
JR京都駅の西に存在した西八条邸の発掘と保存、神戸大学の付属病院の建設にともなう福原の都の一部と見られる邸宅の発掘と保存に関わった経験が本書の基礎となっている。そのなかで考えてきたことが大きく採り入れられている。
特徴の第三は、『平家物語』などの文学作品に記されている記述を大胆に採り入れている点である。たとえば清盛が白河上皇の落胤(らくいん)であるという説を採用するなど、味気ない記録類から知られる事実にふくらみをもたらしている。
こうして実に読み応えがあるとともに、叙述も平明で、今後の研究の基本的文献となるものである。新たな知見も多く指摘されており、注もこまめにつけられているので、後学には大いに参考となる。
全体の内容を見ておこう。清盛は保元の乱後に権力への道を着実に歩んで、ついには太政大臣となって人臣の頂点にいたった。しかし病により出家すると、摂津の福原に退いて福原禅門と称され、その存在は後白河院政の支えとして政界に重きをなした。
福原では大輪田泊を整備して日宋貿易を展開するかたわら、京では娘を入内させて天皇の外戚(がいせき)となり、こうして清盛を中心とした武家政権は六波羅幕府とも称すべきものであったことなど指摘する。
この付近の分析は、福原の発掘など考古学的な知見とこれまでの研究成果とを駆使して、清盛の動きと考えを明快に捉(とら)え、多くの問題を発掘するとともに、新たな展望を示していて、きわめて説得力がある。
著者は、そこから清盛が新王朝の誕生へとさらに突き進んでいったとする。孫の安徳天皇を皇位につけ、平氏系の新王朝を開いたとするユニークな見解を提出する。そのために福原に都を遷(うつ)すことを早くから意図していたと見る。
ところが以仁王(もちひとおう)の乱が起きたために、熟さぬうちに慌てて遷都を意図せざるを得ず、こうして「福原の夢」は挫折してしまったと考えるのである。
しかし平氏による新王朝の誕生という指摘はどうであろうか。この付近の分析や叙述にはやや断定的な部分が目立つのも気がかりである。白河院の落胤から新王朝の形成までを一本調子に捉え、清盛の夢として考えているようにも見受けられる。
「福原の夢」とあるが、それは著者の見た夢ともとれそうであり、いうならば『平家物語』の史観を違った形でなぞっているように思えてならない。
このことは特徴の第三として指摘したこととも関連していよう。『平家物語』を愛読して育った著者にとって、それから離れて書くというのはとても難しいところだが、いちど徹底的に突き放してみるならば、また違った見方も生まれるのではなかろうか。
評者もかつて清盛について書いた経験があり、いささか批判がましい書評になったが、しかし以上の問題はあるにしても、本書には一気に読ませる力があり、清盛の研究がこれによって大きく前進したことは疑いない。
ALL REVIEWSをフォローする